[ 三妖神物語 第三話 女神乱舞 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第三章 天使襲撃
カッ!
太陽をはるかにしのぐ銀色の閃光の固まりが何百もの軌跡を描いて、黄金の幻獣に襲いかかる。
天使の手から放たれた光の矢は、獲物を逃がすことはない、数百発の閃光が幻獣に向かって殺到した。
これで勝負は付いたと、天使達の誰もが思った。だが、黄金の幻獣のスピードは彼らの想像さえ遥かに凌駕していたのだ。
軽く身を捻ってかわす。だが、かわされた光はすぐに方向を変えすさまじい早さで獲物を射止めようと追いかける。
後ろから追いすがる光。それを再び、紙一重で交わし、優雅に翼をはためかせ、方向を変える。
別の天使が放った光が右から襲いかかってくると、自らそれに向かう。
光が寸前まで迫ったとき、身体を半回転させ、小さな弧を描き、スピードを上げる。
突然の加速に光が対応しきれない、そのすぐ側を悠々とすり抜ける。
正面から迫ってきた光と後ろから追いかけてきた光が交錯し、軌跡を描いて再び獲物を追いかける。
黄金の輝きと銀の光が舞い踊る幻想的なその様子に、天使達はしばらく見とれていた。
しかし、銀の閃光の方が、黄金の輝きより速度で勝っている。そして、数も多い。
やがて閃光は、グリフォンを覆い尽くすかのようにその周りを固め、一斉に獲物に突き進む!
「決まったな」
「ああ、なかなか頑張ったな。楽しかった」
天使達は、そう語り合った。
なかなか楽しいショーだったが、これで終わりだと。そう天使の誰もが思った。
だが・・・
獲物に突き刺さったと思った次の瞬間。閃光が跡形もなく消え去ったのだ。
目標に命中したからではない、その一瞬前に空気に溶けるかのように消え去ったのだ。
「ばかな・・・・・・・・・・」
天使達は目を見張った。
かつて、この技を放って倒せなかった相手はいなかったのだ。
この世界の数多くの精霊も魔王も、この技で消してきた。
それが目の前の幻獣には全く通用しない。
”効ない”のではない、術そのものが、”通用しない”のだ。
効いていないなら、パワーを上げればいい。だが、術そのものが通用しないとなれば、いくらパワーを上げたところで全くの無駄だ。
自分達の前に立ちはだかったのが今までの者とは桁が違うことを天使達は知った。
同時に、楽しんでいたのは自分達ではなく、あの獲物の方だと気が付いた。
奴は、その気になればすぐにでも消せるものを、わざわざ遊んでいたのだ。
これは、彼らに対してのあからさまな挑戦だった。
目の前の相手が今までと違う相手であることを、天使達は思い知られた。
だが、それでも、天使達は彼女を”獲物”としてしか見ておらず、驚いてはいたが恐れてはいなかった。
奴に破られた技は確かに強力な術だが、彼らの切り札というわけではない。
それに技自体も力をセーブしていた。全力で放った訳でもない。
もし、彼らが全力で力を使ったりしたら、この小さな世界を破壊してしまいかねなかったからだ。
一つの閃光の力は、せいぜい大陸一つを消滅させる程度の力しか込められてはいなかったのだ。それは彼らにとって、ささやかな物でしかない。
その程度の力なら、万が一に地上に当たったとしても、被害が出る前に彼らの力で破壊を押さえることができる。それ以上の力を込めると、万が一の時に地上に致命的なダメージを与える可能性があった。
まがりなりにも天使である。その力は人間の想像を超えている。
わずかな力で、このちっぽけな星など粉々に砕くことも、この”世界”即ち、宇宙そのものにも大きな影響を与えるほどの力も彼らは持っていた。
故に、ここで本気を出すことはできなかった。
それは、天使としての慈愛の心・・・・などではない。
彼らは創造者”ヤフェイ”の下僕であり、その性格はヤフェイに酷似している。
人間など、どうなろうと彼らには関係がなかった。だが、無意味に人間を巻き込むこともしない、なぜなら、人間達は彼らの創造神”ヤフェイ”の大切な家畜だったからだ。
この異世界にわざわざ彼らが現れ、布教活動を行うのは、この世界をヤフェイの牧場とするためなのだ。
そして、そこに住む人間は全てヤフェイの家畜にすぎなかった。ヤフェイに力を与え、彼の野望を成就させるための大切な生け贄なのだ。
いずれは彼らの神が”家畜”を食することになるだろう、それまでは大切に保護してやるのが神に仕える彼らの責務なのだった。
とにかく、この場では本気ではやれない。天使達は苦々しげに目の前の獲物を睨む。
(何とかこの星からあやつをおびき出せないものか)
天使の一人が頭の中でそう呻いたとき、まるでそれが聞こえたかのように、グリフォンは一つ羽ばたくと、光の軌跡を描いてすさまじい勢いで天へと飛び立った。
これは、天使達にとって渡りに船である。
「追うぞ!」
リーダー格の天使−ミラヴィエル−は一言そう叫ぶと、純白の翼をはためかせ、すぐさまグリフォンを追いかけ始めた。
すさまじい速度で飛び去るグリフォンをかろうじて天使達は追いかけていた。
たかが、”獲物”一匹に天使達が総勢で追いかける。
自分達の力を打ち破った初めての相手に、興味もあった。だがそれ以上に、自分達の力をこの世界の幻獣に破られたことが、天使達の誇りを傷つけていた。
自分達の力を破った者をこのままにしてはおけなかった、たとえその術が本気の攻撃ではなかったとしても。
完全に冷静さを失い、目の色を変えてメイルを追いかける7人の天使達。彼らから少し遅れてもう一人の天使が天空をかける。だが、その瞳は冷静さを失った他の天使達と違い、あくまでも冷静なものだった。
やはりあのグリフォンはただ者ではない。天使達はそのことを思い知らされていた。
今まで、彼らから逃げ仰せたものはいなかった。
この世界に存在する幻獣や魔獣は、戦闘力においても、機動力においても、彼ら神の使徒の敵ではあり得なかった。
かろうじて竜族だけが彼らと互角に渡り合えただけであった。
その竜族もすでに、この世界には存在しないはずだ。
竜族を信奉する一族をことごとく惨殺し、竜族をこの世界から追い立てたのだ。
そして、もはやこの世界に、彼ら天使に逆らえる存在などいないはずであったのに・・・・
だが、彼らの前に立ちはだかったあのグリフォンは何者なのか。
天使たる自分達が必死に追いかけているというのに、追いつくどころか、引き離されかけている。
これほどの力を持つ者がこの世界にいるとは天使達の想像を超えていた。
必死の形相で追いかける天使達、彼らの力はすでに限界に近かった。
戦闘力で負けるとは思っていないが、機動力で自分達が劣っていることは認めざるを得なかった。そしてそれはあまりにも強すぎる彼らの自尊心をしたたかに傷つけていた。
(・・・・もう息切れとは・・・・な)
メイルは十分に手加減をしてやっていたつもりなのだが、下級神の使いと闘神とでは格が違いすぎるのだ、それでも、彼女はわずかに速度を落とし、後ろを振り返る。
必死に追いすがる天使達の後ろで、光の渦がぐんぐん小さくなって行く。
2000億の星の輝きに彩られた、彼女の主人が生きている世界、銀河系が。
光の早さを持ってしても、地球から銀河の外に飛び出すのには、最短距離でも数千年以上の時を要するはずである、少なくとも人間の常識から考えれば。
しかし、その常識を守る義務も義理もメイルにはなかった。そしてそれは天使達も同様だった。光の速度の壁も物理法則の常識も、遥かなる距離という名の空間も、彼女の手によって撃砕され、砕け散るだけであった。
しばらくして、彼女と、天使は再びまみえる。
そこは、空間自体が淡い光を発し、辺りを青白く染め上げていた。
この空間は、今だ人間の知らぬ世界。
人間の物理学の想像すら越えた世界であった。
宇宙の直径は相対性理論によると数千億光年と考えられている。
物理空間の歪みなどにより、観測することのできる空間がその程度とされていた。
そして、例え人類が宇宙に飛び出すことができたとしても、その物理空間を越えることはできないと言われている。
即ち、人間の物理学においての宇宙とは、たかだか数千億光年程度のものにすぎない。
しかし、いま、メイルと天使が対峙している空間は、直線距離(物理法則ともども空間もネジ曲がっているためこの表現は適切ではない)で地球から2000兆光年の距離にある。
人類が知りうる宇宙とは異質の物理法則が働く異空間が、彼女の選んだ戦いの場所であった。
宇宙は広大であるが一つの世界でしかない。
超次元を含む多重構造空間において、宇宙とは一冊の本を構成する1頁である。
その頁の中において、人間が観測し知覚しうる物理的宇宙とは、その頁にかかれた1文字にすぎない、そして、その近くに
メイルが戦いの場に定めたのは、ちょうど、文字と文字の間にある空白部分。二つの宇宙の物理法則がぶつかりあう干渉地帯ともいうべき場所である。
この異空間なら多少派手に暴れても、地球は勿論、地球が存在する
物理法則も空間を満たす物質も、地球があった宇宙とはまるで違うこの世界。
人間が作った存在なら、物理法則の違いによる歪みで瞬時に元素レベルで崩壊しているだろう。そんな危険きわまりない空間。
しかし、メイルも天使達にもそんなことは何の意味もなかった。
天使は再びメイルを取り囲み始める。
目の前の獲物を逃がすまいとしているかのようなその行動。そして瞳に宿る残忍な笑み、彼らはまさしく血と殺略に酔った存在だった。
天使達の包囲の鉄環が完成した。だが、やはり、一人だけ存在する女性体の天使は、その行為には加わらず少し離れた場所から仲間達の行動を見つめるだけだった。
その瞳にはやはり、悲しみなのか哀れみなのか、悲しげな光が宿っている。
天使達が突き出すように、左手をメイルに向けてのばす。
メイルに向けられた手のひらから先ほどと比較にならないほどのまぶしい光がほとばしった!
それは、強大な力を持つ光の固まりだった。
先ほど地球上で撃ち出されたものが”光の矢”ならば今度のは光の槍とも言うべき物だった。
素人が見ても、それが先ほどとは桁違いの力を持っていることは容易に想像が付く。
強大な光の槍は7条の軌跡を描いて、メイルに襲いかかった。
竜一と康夫が望みもしないデートの誘いを受けて、車に乗り込んでから、すでに30分が経過した。
車はすぐに高速道路にはいると、真っ直ぐに東京湾をめざしていた。
時間は午後2:00、通勤ラッシュから外れているとはいえ、東京の交通量はそれほど変わることはない。本来ならば、渋滞に巻き込まれろくに進めもしないはずであるのに、どういう訳か、この日に限って通行する車両は極めて少なく、道路に余裕があった。
「お気に召したかな、ミスター竜一。
君のために、このあたりの高速道路を借り受けたのだ」
男は自慢げに答えた、広い車の中で竜一に体毎向けて、にやりと笑う。
「貸し切ったわけではないんだな」
皮肉っぽく竜一が言うと、男は素直に頷いた。
「そこまであからさまにやっては人目に付きすぎるしな。
まあ、走りやすい程度の隙間はあけてもらわんと、日本の渋滞には我々は付いていけないのでね。
よく日本人はこんな状況を受け入れられるものだと感心するよ。忍耐強い国民だ」
その言葉の中には皮肉が込められていた。
どんなに歪んだ、住みにくい状況でも甘んじで受け入れられる、従順な種族だと。
「その点に関してだけは、全く同感」
康夫が力強く頷く。
「それは俺も認めるよ。
だが、銃を個人が所持するのが当たり前だと思っている国民もどうかと思うがね。
所詮、銃なんて物は、どんなに正当化しようと凶器にすぎない。
そんな物を持つことが、個人の自由の象徴だというのは狂気の沙汰だ。」
男は眉を微かに眉をしかめたが、気を取り直したように言葉を続けた。
「まあ、その点に関してはあまり偉そうにいえる立場ではないが、民族学を戦わせるために君たちを招いたわけではないからね。
この話題はこれくらいにしようではないか」
そっちからふっかけておきながらなんと言う言いぐさか。そう思ったが口には出さない。
出したところで、効果があるとは思えない。竜一は別の話題で彼らから情報を得ようと考えた。
「さて、我々としては、ミスター竜一に聞いておきたいことがある、素直に答えていただけるとこちらとしてはまことに助かるのだが、どうかね?」
「質問の内容によるな。知らないことを聞かれても答えようがないし、プライベートなことには答えたくないしな」
「素直に答えた方が君たちのためだよ。
そうでなければ、我々としては非友好的な手段に訴えねばならない。」
静かだが断固とした決意を含んで男は答えた。
「拷問でもするのか?」
竜一の確認に男は頷く。
「その程度ですめばいいがね、我々はいろいろな手段を持っている。
その中には自白剤という無粋な物もある。
これは便利な代物だが、いかんせん、この手の薬は人間の脳には余りよい物ではないからね。
最悪の場合、廃人にもなりうるのだ。我々としてはそこまでしたくはない」
さて、どうかな。
竜一は声に出さずに呟やいた。
先ほど死体でもかまわないと言い切った相手の言うことである、どこまで信じて良い物か。
だが、このまま黙っていても何の進展もないことは確かだ。ここは、うまく乗せられたふりをして情報を得た方が得策だろう。
竜一はそう結論づけた。ミューズとシリスもそれに賛同した。
もともと、探られても困るような秘密を彼女たちは持っていないのだ。それが秘密になるかどうかは、彼女達の主人である竜一が決めることである。
康夫を見ると竜一の方を興味津々と言わんばかりに見つめている。
彼も、こんな連中に狙われている竜一の秘密に無関心ではいられないらしい。
・・・・参ったなあ・・・・
今、誰が一番苦手かと誰かに問われたら、竜一は、迷わず康夫だと答えるだろう。
他の連中なら問答無用ではり倒せばすむことだ、相手が国家権力だろうが、神様だろうが、気に入らなければ叩き潰すだけである。が、康夫はそう言うわけには行かない。
なんと言っても親友である。誰かにそう言われてもお互い断固として認めないだろう。ただの喧嘩友達と言い張るかもしれないが、親友であることは、他の全ての人間が認めるところである。
「わかったよ、まあ、答えられる範囲で答えてやるさ」
「ふむ、まあいいだろう」
男は頷く。
「まず、我々はスポンサーから、君の身柄を拘束するように命令された。
その時、君にはとんでもない力を持つ”魔女”が付いていると聞いたが、それは何者かね?」
「そんなことを聞いても、あんた達に何のメリットがある?
その情報を得たら、スポンサーを乗り換えるかい?
もっと高く俺を買ってくれるところにでも」
「ほう?」
男は興味深げに竜一を見直した。
「それほどの価値があるという事だな、その”魔女”とやらには」
「まじか? 竜一?」
男と康夫が竜一を見つめる。
男はともかく、康夫が興味を持ったのは少々困りものだったが、このまま行けば、何かの弾みでばれる可能性もある。
竜一は腹をくくった。
「ある意味ではそうだろうな。
何しろ、世界をひっくり返すくらいの力は持っているはずだ」
「世界をひっくり返すとは?」
男の疑問に竜一は肩をすくめて答えた。
「言葉通りの意味さ。
彼女たちがその気になれば、地球の公転軌道だって変えられるし、アメリカ大陸をひっくり返すことだってできる」
「ふざけたことを!
なるほど、どうしても本当の事は言ってもらえないと言うことか」
男の怒声に、竜一は欠伸を一つすると、冷ややかな声で答えた。
「事実だ。もっとも、それを信じるかどうかはあんた達の自由だがな。」
男は、そのまま口をつぐんだ、全く信じていないのは、その表情から明らかであろう。
竜一の言葉は完全に事実であった。いや、事実より遥かに過小評価したものであったが、常識的な人間にしてみれば、からかわれたとしか思えないだろう。
男の瞳には、怒りが燃え上がっている。それは、自分が馬鹿にされたと信じた者の抗議の怒りだ。
しかし、他にいいようがないので、竜一は黙ることにした。
これ以上何を言っても、それが事実にそくしたものであればあるほど、彼の怒りを誘うことになる。
それにこの反応からすると、彼らはスポンサーとやらから、殆ど何も聞かされていないのだろう。
せいぜい、”奴は、強力な力を持つ魔女に守られているから気をつけろ”程度の情報しか与えられていないのに違いない。
それが何を意味するのか、彼らは何も知らされていないのだ。
”魔女達”がどれほど恐ろしい存在なのかと言うことを。
もっとも、それを知っていたら、最初から竜一には手を出すことなどなかっただろう、まともな感覚を持った人間ならば・・・・
「まあいい、いずれ目的地に着いたらゆっくりとお聞きすることにしよう。
もうすぐの辛抱だしな」
男は、それだけ言うと、黙ってしまった。
最も、竜一にしても男が何の情報も持っていないのであれば、話すだけ無駄だった。
男が黙り込んだのは、むしろありがたいほどであった。だが、男は黙り込んでも、黙らない者もいる。
竜一の頭痛の種とも言うべき男、康夫である。
「で? その魔女って女の子?」
「へ? 魔女って・・・・女に決まっているんじゃ?」
竜一の間の抜けた疑問に康夫は苦笑した。
「いや、俺も最近本で読んだんだが・・・・、魔女って言うのは必ずしも女性のことではないらしい」
つまりは、男の”魔女”も居ると言うことらしい。
男なのに魔女と言うのも奇妙な気もするが、そんな疑問は後回しだった。
竜一は康夫に素直に教えることにした。それを信じるかどうかは、康夫本人の意思しだいだったが・・・・
「まあ、そこのおっさんにも言ったが、よーするに、絶対無敵の守護女神が俺にはついているってことさ。
その気になれば、指一本で星さえ滅ぼすほどの力を持つとんでもないお嬢さん達がね」
男はその話を聞き流していた、明らかに無視している。だが、康夫はあっさりとうなずいた。
「なるほど。それを狙って訳のわからん連中がお前に接触してくると言う訳か・・・・」
その答えを聞いて、竜一は惚けたような顔で康夫を見つめた。
「どうした? 間の抜けた顔をして?」
康夫の問いに竜一は少しあきれ顔で答えた。
「そりゃ、こっちの台詞だな・・・・今の話を信じたのか?」
「なんだ? 嘘だったのか?」
「い、いや、本当だが・・・・普通、こんな話信じないと思うのだが」
半ば呟くような、うめくような竜一の言葉に、康夫は平然と答える。
「こういう状態でそんな冗談を言っても、この現実をどうにか出来る訳じゃないしな」
康夫はそう言うと、腕を組み、うんうんと一人でうなずきながら言葉を続ける。
「確かにそういう無敵の切り札があるのなら、こんな連中の無粋な招待を平気で受けられるわけだ」
かなわないな。
竜一はそう思う。
康夫という人間は、普段はむしろとぼけた、冗談の好きな男だが、こう言った状況の判断力の正しさにはすさまじいものがある。
そして、相手の言葉の中の嘘と真実を見抜く眼力にも非凡なものがあった。
普通なら絶対に信じられない、荒唐無稽とも言える竜一の言葉の真実を簡単に見抜けるのだから。
康夫のうなずきに露骨に侮蔑の視線を男は向けた。
「あきれたものだな・・・・、こんなばかばかしい話を信じたのか?
子どもの妄想だ・・・・」
その言葉にはいらだちと、微かな疲労感さえあった。
「ミスターX、世の中には常識や理屈では割り切れないこともあるのだよ」
澄まして康夫が言うと、男より先に竜一が問いかけた。
「おいおい、康夫。ミスターXって誰のことだ?」
「目の前の”おっさん”さ。
いつまでも名無しのゴンベじゃ可哀想だから、ミスターX」
目の前の男を指さして、康夫が答える。
「確かに、分からない存在にはXが妥当だけど・・・・ちょっと、格好良すぎないか?」
苦笑しつつ答える竜一、するときまじめに康夫は考え込んだ。あくまでも外見だけは・・・・
「そうだな、じゃ、住所不定、職業不明、本名不詳のA!」
危うく吹き出しそうになった竜一。必死に笑いをこらえているが、こらえきれ無いらしい。その証拠に肩を震わせながら、答える。
「何か、朝刊の記事みたいだな。
住所不定、無職のA(仮名)逮捕。逮捕容疑は拉致監禁!」
竜一の反撃に、康夫もプッと吹き出して、再反撃を試みた。
「どこぞの危ない宗教団体だぞ、そりゃ」
「やっていることは同じ様なもんだろ?
第一、細菌兵器を使って人を脅すところは完璧にそれもんだ」
たまらず、馬鹿笑いをする竜一と康夫。その時、怒声が車中に響いた。
「いい加減にしろ! ガキども!!」
どうやら、あまり気の長い方ではないらしい、怒鳴った男の右手にはすでに拳銃が握られ、銃口はしっかりと竜一をとらえていた。
「その、女神様とやらは、拳銃からも守ってくれるのかな?
ぜひ、試してみたいものだが・・・・」
「いいよ」
男の脅しに、信じられないほどあっさりと竜一は頷いて見せた。
平然としたその顔を見た男は、力無く銃をおろした。
「試さないのか? ただのはったりかもしれないぜ。」
「いや、いい」
竜一の言葉に、毒気を抜かれたと言うより、徒労感に満ちた口調で男は首を横に振った。
男にして見れば、たまらなかったに違いない。
今までもらったこともないような高額の報酬と、”魔女”という正体不明の敵の存在。
久しぶりに楽しそうな仕事だと思った。
今までの単純な要人暗殺や、小国に戦火の火種を作るためのテロ活動に秘密工作。
そんな仕事ばかりで、いい加減飽き飽きしていたところに、この仕事が舞い込んできたのだ。
危険は承知の上。
危険が大きいほど、仕事もおもしろいと思っていた彼は、敵の正体を探りながらこの仕事を楽しんでいたのだ。
だが、なんと言うことだろう。
楽しいはずの仕事が、いざふたを開けてみたら、ただの大学生を誘拐することだけだったとは。
そして、正体不明の敵などどこにもいない。
”魔女”など存在していなかったのだから。それはただの”ガキ”の妄想にすぎなかったのだ。
上からの情報では”魔女”の存在を示唆してはいたが、それは単なる誤認情報だったらしい。
確かに、危険はあった。
ただのガキと思っていた彼らは信じられないほどの武術の達人ではあったが、それだけだ。
結局、仕事の中身は、今までの仕事と同じようなものだった。
しかも、こんな妄想を喜ぶような”ガキ”の子守までしなければならないとは・・・・
あまりのばかばかしさに、泣きたくなる思いだった。
男のそんな思いに気づくことなく、二人は退屈そうに外の景色を眺めていた。
だが、男は幸運だった。
この場で彼が銃を撃っていたら、彼の命はその時、終わっていたはずなのだから。
銃口を竜一に向けていたとき、彼の肩に乗っていた美しい黒猫が、その神秘の瞳に剣呑な光を宿していたことに男は気づかなかった・・・・
徒労感と絶望で無口になった男を完璧に無視し、盛り上がっていた竜一と康夫、完全に自分達の置かれた状況を楽しんでいた彼らは、ハンドルを握っていた男の声に現実に帰った。
「そろそろ、着くぞ」
今まで、無言でハンドルを握っていた男は一言そう言うと再び沈黙に帰った。
もしかしたら、日本語を殆どしゃべれないのかもしれない。
竜一はそんなことまで考えていたが、さすがにそれを口にはしなかった。そんなことを言ったところで男達は無視したに違いない。
車は静かに港まで走る。
だが、港には何もない。
てっきり船にでも乗せられるものと思っていた竜一と康夫は、周りを見回した。
辺りには極普通の倉庫などが立ち並んでいるだけで、特別変わった建物など、無い。
「・・・・ひょっとして、貨物倉庫の中でいじましく活動しているとか?」
「貧乏な組織なんだなあ・・・・
まあ、無理もないか。ただでさえ物価の高い日本、しかも超円高の今日。
海外の諜報組織が財政難になっても仕方がないな」
康夫と竜一の同情に満ちた声が響く。
A(仮名)こと、拉致監禁グループのリーダーは、竜一達とつきあいだしてたびたび感じる頭痛に何とか耐えながら、二人を睨みつけた。
「少し静かにしていろ、すぐに迎えがくる!」
「迎えがくるとさ」
「きっと、人力車だぜ、でなけりゃ。ロープを持った二人組の男。」
「?」
竜一の言ったことがわからないらしい康夫が首を傾げた。がそれはすぐにとけ歌い出す。
それに竜一も唱和した。
「運転手は君だ、車掌は僕だ、あーとの二人は電車のお客う〜」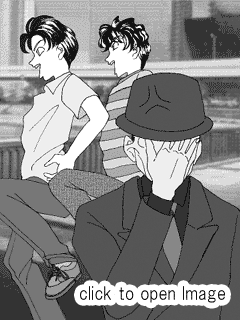
そこまで歌うと、ぷっと二人同時に吹き出す。
(相変わらずいいコンビだわ・・・・)
(仲がいいというのは良いことだとは思いますが・・・・
あまりにも緊張感がなさすぎます。
もう少し、考えてほしいものですが・・・・)
竜一と康夫の漫才にミューズは苦笑し、シリスが眉をひそめた。
(いいじゃない、あまり緊張しすぎて胃に穴が空くよりはましよ。)
からかうようなミューズにシリスはしばらく沈黙していたが、
(それはそうかもしれませんが・・・・相手を無用に刺激して、いらぬ危険を招くのも考え物です。)
そう反論した。
もっとも、二匹の会話も長くは続かなかった。
二匹はすでに、男が言った迎えの存在を察知していた。そして、その迎えを、その鋭敏な感覚で細かく調べていたのだ。
男は、額を押さえながらいっこうに静かにしない竜一と康夫に殺意のこもった目を向けていた。
早く迎えに来てほしいと心の底から願った。そうすれば、この馬鹿なガキどもから解放されると信じていたのだ。
1 / 2 / 3 / < 4 > / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15