[ 三妖神物語 第三話 女神乱舞 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第九章 雷神妖艶
「あーうっとおしい・・・・」
ミューズは目の前にいる新手の警備員達をにらみつけながらぼやいた。
既に何度目だろう? 五月蝿くつきまとう警備員達を吹き飛ばして研究所の奥に進む。
その度にわらわらとまるでゴキブリのようにわいてくるのだ。まあ、彼等もこれで給料をもらっているのだから仕方が無いとも言えるが・・・・
ミューズがこの中を目立つように、うろついていることに意味など無かった。
早い話が陽動兼嫌がらせである。
彼等のデータを手に入れるのにコンピュータの端末を触る必要もミューズにはない。
その気になれば人間の頭だろうが、コンピューターだろうが、直接中を覗けるミューズである。彼女の前に人間の機密など何一つ存在しない。
隠し通す方法など存在しないのだから・・・・
まあ、敵の実力を有る程度知ると言うことと、彼等に自分達の力を示しておくという示威的行為の意味もあったのだが・・・・
そして、お馴染みの光景。
突風が警備兵をなぎ倒し、叩き伏せる。
そんなことを何度かする内に、少し広めの部屋に入った時またしても新手が現れた。
彼等は今までの警備員達とは違っていた。
その服装も多少デザインが違っていたが、彼等の本質、常人の数百倍の強さを持つ生命力と精神力をミューズは見逃さなかった。
「おやおや、ようやく超能力者のお出ましね」
ミューズの顔に薄く浮かぶ笑み。
それをめざとく認めて超能力者達は戦闘態勢を整えた。
彼等もまたミューズの力が尋常ではないことに気が付いたのだ。
「ひいい!」
ミューズの顔を見るなり、12名いた超能力者の内の一人が、短い悲鳴を上げた。
声の主はまだ年端の行かぬ少女だった。
彼女は、悲鳴を上げながら、わき目もふらずに逃げ出した。
あまりにも鮮やかなその逃げっぷりに、他のメンバーは勿論、ミューズさえ、しばらく呆然としていたが、彼等の一人が吐き出した憎々しげな声に我に返る。
「役たたずめ! 力がないのなら、盾になるくらいの度胸を見せて見ろ!!」
「全く、あんな出来損ないが我々のメンバーだとは、情けない!」
口々に彼女を罵り笑う。
元々、小さな力しか持たないみそっかすのメンバーだった。足手まといが減っただけのことだが、あまりにも情けない。
気を取り直してリーダーが号令をかける。残った10人はその命令に従ってミューズの前で位置を定めた。
逃げたメンバーに対しての仲間達の評価は”出来そこ無いの役立たず”でしかなかったが、その様子を見て全く正反対の評価を下した者がいた。
言わずとしれたミューズである。
わき目もふらずに逃げ出した少女が、ミューズの視界から消えた後、彼女は内心感心していた。
大して役に立たない力しか持っていない超能力者達の中で、彼女の素質は極めて高度な物だったのだ。
少女の能力が優れていたからこそ、ミューズの力の本質を見抜いたのだ。
そして、ミューズが自分達の手に負える存在ではないことを見抜いた彼女は、あまりの恐怖に耐えかねて逃げ出した。
彼女の力が仲間に過小評価されていたのは、彼女ではなく、この研究所に責任があった。
彼等の超能力者育成プログラムでは、彼女のずば抜けた素質をのばすことが出来なかったのである。
そのために最も優れた素質を持ちながら、その力を発揮できなかったのだ。
ミューズはそれを見抜くと同時に感心した。
ミューズを見て何の抵抗もせず一目散に逃げ出した者は、この世界に来て始めてのことだ。
彼女の力を見ぬいた少女の力量は、あるいは自称”最強の魔道士”リザンをすら凌駕するかもしれない。
少女を罵ったメンバーもすぐに思い知る事になるだろう。
少女の選択こそが、ミューズに対して人間が成し得る唯一にして最善の手段であることを・・・・
気を取り直したメンバー達がフォーメーションを組み終わる。
別にそれを待ってやる義理はミューズにはなかった、元々”先手必勝”が座右の銘の彼女である。
だが、今回は相手に自分達の力を誇示するのも目的だから、あえて相手の出方を待ってやった。
彼等ご自慢の超能力部隊が、最善の方法と手段を持って挑もうと、自分に何の負担にもならないことを思い知らせてやるために・・・・
ミューズは相手の実力を知るためにあえて手を出さなかった。
そして、超能力者達はミューズの非常識きわまる力の大きさに、僅かだが戸惑い攻めあぐねていた。
素直に逃げれば良いのだろうが、彼等の感覚は逃げ出した少女ほど鋭敏ではなかったのだ。
任務への責任感と自分の力に対する過信、そして無益な自尊心が彼等の思考から”逃走”の文字を消し去っていた。
しばらく睨み合う両者。
だが、その状況も長くは続かない。
張りつめていた緊張感に耐えきれず、ついに一人の男がミューズに挑んだ。
「くらえ!!」
男のかけ声と同時に紅蓮の炎がミューズの視界を埋め尽くす、それを合図として他のメンバー達もその力の限界を極めた”必殺技(笑)”を繰り出してきた。
激しい閃光が、莫大な質量が、巨大な破壊力を秘めた力が、固まりとなってミューズに叩き付けられた!
けたたましくなり続ける非常警報。
地響きのような音を立てて駆け抜けてゆく警備員の大群。
小さなのぞき窓から外の様子を見て竜一が呟く。
「始まったな・・・・」
「何が?」
竜一のささやきを聞きつけて康夫が尋ねる。
「おいおい! お前の耳はどーゆー構造してんだ!」
他人には聞こえないはずの小さなささやきを耳ざとく聞きつけた相手に、竜一は思わず焦ってしまった。
しかし、竜一のつっこみを無視して、康夫は呟いた。
「何か面白そうな事が起きているようだ・・・・なあ、見物にいかねえか?」
「見物って・・・・ここが開かないとどうにもならないだろう?」
そう言いながら竜一は苦笑しながら扉を拳で軽く叩いた。
このコンテナは、壁も扉も厚さ100ミリの特殊セラミックとハイパーカーボンの複合素材で出来ていた。
並みの鋼鉄や強化コンクリートくらいなら、今の竜一でもどうにか出来ないでもない。ただし、その厚さが20ミリ程度ならばの話だ。
今回のように新型の複合素材、しかも自分の限界の5倍の厚さの扉となればお手上げである。
扉のロックも電子式であるから、針金や釘でこじ開けると言うわけにも行かない。
要するに、ここを誰かに開けてもらわないことには、ここから出ることは出来ないのだ。
竜一自身としては、ミューズが派手に暴れて発電システムを潰してくれることを期待していた。電子ロックは停電すれば全くのがらくたに成り下がる。
さらにそういう事態に陥れば、康夫にミューズ達のことを知られずにここから出ることもできるのだ。むしろ、現在の状況は竜一にとってはありがたい位だった。
あとは、ミューズが万事旨くやってくれるはずだ。
この建物の適当な人物を精神支配して自分達を無事に逃がす。そういう手はずになっているのである。これで四方丸く収まるはずだった。
しかし、その計画は思わぬ突発的要因で崩壊することになる。
「まあ、いい加減こんな所に押し込められるのにも飽きたところだしなあ。
出ようぜ竜一。」
「だから一体・・・・」
どうやって? そう言おうとした竜一は、目前で起きた現象に思考が麻痺してしまっていた。
とても本気でしたとは思えなかった。
軽くはたいた、そんな感じで康夫は扉を叩いた。そしてその瞬間、あろう事か、とてつもない悲鳴を上げて、特殊セラミックの頑丈な扉はひしゃげて外へとはじけ飛んでいたのである!!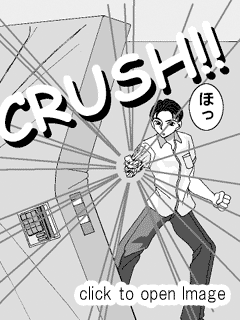
グワシャン! ガラングワン!!
「さあ、出ようぜ」
「・・・・・・・・・・・・・・・」
あまりと言えばあまりの展開に竜一は目を点にして硬直していた。
一体誰が想像できるだろうか?
複合素材の壁をいともたやすくぶち抜ける人間がいるなどと・・・・
特殊セラミックとハイパーカーボンの複合素材はその強度で鋼鉄を遥かに上回る。
しかも弾力性があり、与えられた衝撃を吸収する性質もあった。そんな代物を力でぶち抜くなど、人間業では絶対に不可能なはずなのだ。
勿論、竜一の身内(?)の彼女達にはたやすいことだが、彼女たちは人間ではない。
康夫の戦闘力が、人間離れしていることを竜一は知っていたつもりだった。
だが、それがまさしく”つもり”でしかなかった事を思い知らされたのである。
ようやく口を開いた竜一は思わず尋ねていた。
「お・・・・お前・・・・一体どういう手ぇしてるんだ?」
あまりの間抜けな質問に康夫が返した答えもまた、ふざけたものだった。
「こういう手ぇしてるんだ」
竜一に手の甲を見せながらひらひらと動かして見せる。
その手を見つめて竜一は、しげしげと自分の手と見比べていた。
・・・・まことに残念な事だったが、竜一には自分と康夫の手の違いを見いだすことは出来なかったのである。
「ば・・・・化け物め!」
月並みな台詞を恥ずかしげも無くはき捨てたのは、必殺技(笑)の数々をあっさりと破られたエリート超能力者達である。
「お願いだからもう少し独創的な捨てぜりふを言ってくれないかしら?」
ミューズが吐き出したその台詞は、憎悪に燃え上がっていた。
「・・・・今まで、私にその台詞を吐いて無傷でいられた奴はいないのよ・・・・」
瞳が殺意に輝く。
それは怪しい美しさ、危険な煌めきだった。
ひいいい!
超能力者達の上げた断末魔、それは声にさえならなかった。
ミューズは彼等に最後の一言を上げることさえ許さずに、一瞬のうちにその生命活動を停止させたのである。
巨大な結晶体がミューズの周りに林立する。
天井の明かりを反射し、あるいは屈折させて美しい光彩を放つ七色の結晶。
その数は11。
その結晶は素晴らしい透明度をもって、自らがとらえた獲物で自らを飾りたてているようにも思えた。
真紅、藍青、黄色、緑、紫、透明色・・・・
色とりどりの巨大な結晶、直径にして2m、高さ5mにも達するそれは、一見して色の付いたガラスのオブジェにも見える、しかし、そうでないことをモニター越しに見ていた科学者達は知る。
「・・・・これは一体どういう事だ? 氷付けにでもされたのか?」
「まて、すぐにレーザースペクトルの解析結果が出る」
モニターに映し出されている巨大な結晶体。レーザー光の屈折率と偏光率・音の反射など、あらゆる方法でその分子構造を解析し、正体を探るべく分析が行われる。
そして、コンピュータがはじき出した結論が別のモニターにコンピュータグラフィックスと共に表示される。
モニターに映し出された結論、一同はその結果に驚愕の声を上げた。
「・・・・青い結晶はサファイア、黄色はオパール、赤はルビー、緑はエメラルド、紫は紫水晶、透明な奴はダイヤモンド!?」
まるで、宝石鑑定でもしたかのような結果に科学者達は目をむいた。
「馬鹿な! 一体どんな理論で! どんな化学変化が起こればこんな現象が起こる!!
錬金術じゃあるまいし!」
「ありえん! 科学的に絶対にありえん!!
このデーターが間違っているのか、さもなくばシステムにバグがあるとしか思えん!」
そう否定の声を上げると、別の科学者が反論する。
「私達の作った物質解析システムに問題などありえん!
システムも解析プログラムも完璧だ!!」
「馬鹿を言うな!
この結果が正しいというなら、現在の物理学が根こそぎ崩壊するわい!!」
超能力によって物質変換もどきの現象が起こることも確認されてはいる。
例えば心霊治療などに見られる、人間の内蔵が動物の内蔵になると言った類の現象だ。
しかし、それはあくまでも人間の生体物質から動物の生体物質に変化したと言うだけで、蛋白質は蛋白質であり、鉄になると言うことは無い。
だが、目の前のデーターを信じるならば、彼女は大気中の酸素や窒素を鉱物に変換したことになる。
そんなでたらめな物質変換など現在の科学の常識ではあり得なかった。
「どこからか持ってきたのではありませんか?
例えばテレポートとか言う技で・・・・」
誰かがもらした呟きにさらに別の科学者が食って掛かる。
「それこそありえん!
そもそも空間を越えるなどと言うことが生物に出来るものか!
ただ空間を歪めるだけで、どれほど膨大なエネルギーが要求されると思っておる!
まして、あんな巨大な結晶をそれも複数を同時に運んでくるなど!
そんなことが出来るわけがない! それこそ、物理的に不可能だ!」
「だいたい、あんな巨大な結晶体で宝石が存在するはずがないわい!
地球上のどこを探せば、あんな巨大な結晶が無傷で埋まっていられるような、安定した地層があるというのだ!
あそこまで巨大に育つ前に何らかの外的要因で砕けるわ!」
「第一、テレポートで持ってきたのなら、メンバー達をどうやって宝石の中に封じ込んだのだ!
理論的に説明してみせろ!」
”学者が三人寄れば結論が出ない”という諺(?)通り、いったん付いた議論の炎は、瞬く間に部屋中の科学者に引火し、たちまち大火事となる。
けんけんがくがく、もはや当初の目的を見失い、不毛な論争に発展しかけた時、一人の科学者が奇跡的に我に返った。
「ここで、喚いていても結論など出るまいて。
当初の予定通り、あの女を捕らえて分析すれば答えも見えるだろう」
最も説得力に富んだその言葉に全員が冷静さを取り戻した。
「そうだな、それが一番手っ取り早い」
「しかし・・・・どうやってあの女を結界システムに案内するのだ?」
案内役のはずだった”新兵器達”は反撃どろこか逃走さえ許されずにあっさりと倒された。
琥珀に取り込まれた昆虫よろしく、宝石のオブジェと化した哀れな超能力者達。
彼等を一瞥するとミューズはさっさと歩き出した。
彼等はもはや死ぬことはない、だが、これから人として生きることもない。永遠に時を止めたまま彼等はここに在り続けるのだ。
雷神に戦いを挑んだ身の程を知らぬ愚か者。人間の愚考と傲慢さを象徴する永遠の記念碑として彼等はこの場に飾られる栄誉を得たのである。
・・・・それが彼等にとって幸せかどうかは、また別の問題であった・・・・
その有り様をモニターで睨みながら、科学者達が次ぎに出した結論は極めて安直な物だった。
「そうだな、こんな手が通じるかどうかはわからんが・・・・」
ライカークがそう呟き、操作パネルにあるスイッチの一つを軽く押す。
グオオオーーン!
重々しい音を響かせて、通路のあちらこちらで分厚いシャッターが動きだし、通路を遮断する。
それは、万が一事故が発生した場合を考えて設置されていた隔壁。
危険物が外や別のブロックに漏れ出すのを防ぐための物である。
全てのブロックが完全に閉ざされ、ミューズの目の前にも分厚いシャッターが立ちはだかった。
「さて、何を考えているのやら・・・・」
小さく首を傾げて周りを見る。
ちょうど分岐点でどちらへ行こうか思案している最中にいきなり隔壁が閉じたものだから、現在ミューズは隔壁によって作られた小さな部屋に閉じこめられる様な形になっていた。
「このまま、ここに毒ガスでも流す気なのか・・・・それとも・・・・」
余裕の表情で相手の出方を待つミューズ。
彼等が何を考えているかなど、その気になればすぐに知ることが出来るが、あえてそれはしない。
彼等が罠を張っているのは承知の上だった。
「せっかく無い知恵絞って罠を張っているんだろうし・・・・もう少しつきあってあげるわ」
これはミューズにとってはゲームに過ぎない。
マスターには少々気の毒だったが、少しばかり時間をかけて遊ぶことに彼女は決めていたのである。
しかし、それがたいへんな結果をもたらす事までは、さしもの彼女も気が付かなかったのだ。
ゴウウン・・・・
重苦しい音を立てて、閉じていたはずの隔壁の一枚が上がってゆく。
右の道が開かれたが、左側は相変わらず閉じたままだった。
「なるほど・・・・」
ミューズは納得した。
彼等は隔壁を使って道案内をするつもりなのだ。
隔壁や壁をぶち抜いて道を作ることもできるが、ミューズは素直にその案内に従った。わざと罠にかかってやるつもりだったから・・・・
やがて、ただっぴろい部屋にミューズはたどり着いていた。
広い、円形のホールのような場所。直径は20m近くあるだろう、その何もない殺風景な空間にミューズは視線を投げかけた。
「いかにも、ここに罠がありますよ、と言わんばかりねえ・・・・」
床からエネルギーの流れを感じる。かなりの電力がこの下に蓄えられていることをミューズは感じとっていた。
これだけの電力を必要とするシステムが床暖房や、空冷施設の配線などであるはずがない。
「・・・・さて、どんな出し物があるか・・・・
床全面がレーザー砲の偏光レンズに化けるのかしら?
それともマイクロウエーブで黒こげかな?
案外、意表を突いて重力兵器なんてしゃれた物を出すかな?」
完全に見物を決め込んで、ゆっくりと、ホールの中央に向かって歩き続ける。
ヴヴヴヴヴ・・・・
ミューズが中央まで来ると、いきなり床下から腹に響く重低音が流れ出す。
それは彼女に対しての人類科学の挑戦状であった。
「目標、結界中央部に到達!」
「結界システム始動!」
唱和に続いてスイッチが押され、莫大な電力が超伝導を利用して作られた巨大なシステムにそそぎ込まれる。
膨大なエネルギーを貪欲に飲み干し、その巨大なシステムは目覚め、動き出す。
そして、強力な磁界が、一つの小世界をこの世界から擬似的に切り放そうとうごめきだした。
「しかし、こうもあっさり引っかかるとは・・・・拍子抜けですなあ・・・・」
「よほど自分の力に自信があるのか・・・・唯の馬鹿か・・・・」
「しかし、その自信もこれまでだ。私のシステムは一介の魔女ごときに破られる物ではない」
ミューズの行動をモニターで観察していた科学者達は、あまりにあっさりと罠にかかった彼女に拍子抜けしていた。
もう少し、こちらの行動を警戒するなり裏をかくなりするだろうと考えていた彼等は、あまりにも簡単に事が成ったことに居心地の悪さを感じていた。
「力におぼれて大局を見誤るか・・・・」
落胆した呟きをもらしたのは、ライカークであった。
彼はミューズに幻想を抱いていた。名高い”御使いの騎士”を再起不能に追い込んだ”魔女”を彼なりに高く評価していたのである。
はじめはロドリマンに言った通り、誤認情報がデマかと思っていた。しかし、目の前で、数々の”奇跡”を見せられては信じるほか無い。
そして、その力に憧憬さえ抱いていたのだ。
しかし、これでは拍子抜けである。
少なくとも、自ら罠にはまるような思慮無しでは、彼の幻想は砕け散るのは仕方がなかったのだろう。
まあ、ミューズに言わせれば、見ず知らずのマッドサイエンティストの期待に応える義理はないという所だろうが・・・・
ヴヴヴ・・・・ィヴィヴィヴィィ・・・・
ヴオオオオオオオンン!!
いかにも、眠りから目覚めたと言わんばかりにシステムは寝ぼけた音から、力のこもった音へと変化する。
それと同時に、床下から奔流となって天井へと飛び出す無数のエネルギーの流れ、磁力の帯をミューズの視界は捕らえていた。
「何かと思えば・・・・磁界による結界? なんとまあ古風な・・・・」
磁界による結界は、実は魔術においては最も古いタイプの物だ。
それは、基本的に大地の精霊の力を借りて、地磁気を一時的に増幅し目的の物を封じると言う物である。
術の組立やその呪文、文様などに色々なバリエーションがあるが、基本は変わらない。
ただ、古い物であるから、それだけ色々と研究されているし、種類も豊富である。
そして、十分に練られ、研究された物ならば強大な力を発揮することもあった。
一見して、このシステムの作り出す結界は、かなりおおざっぱな物であった。
それでも、供給される電力が非常識なほどに莫大であるためか、その力はかなり強い。
「くははは! やった、やったぞ!!
見てみるが良い! あの”魔女”が手を出しかねておるわ!!
やはり、科学こそが力よ!!
超能力だの魔法だの、そんな物は何の役にもたたぬのだ!」
己の勝利を高らかと宣言したのは言うまでもなくフォルティン教授であった。
「しかし教授、まだ奴が無力になったと決まった訳では・・・・」
慎重論を唱えた助手を無視して、フォルティンは、自分の席から立ち上がると、出口へと歩き出した。
「どうなさるおつもりかな、フォルティン教授?」
「あの”魔女”を身近で観察するのだ。なかなか興味深い存在だからな」
そこで言葉を区切って、フォルティンはライカークに笑いった。
「君たちと違って私はあの美しい体の方に興味があるがね」
そう言うと、さっさと外に出ていった。
「あ、私も興味があります」
「あ、俺も」
そう言うと、何人かの研究員がフォルティンの後を追いかけた。
「本当に上手くいったのだろうか・・・・」
呟きながら、モニターを見つめるライカーク。
超常現象を軽んじるフォルティンと違い、超能力部門の責任者であるライカークは慎重だった。
彼はこれまで見てきた奇跡の数々から”魔女”の力はこんな物ではないと考えていたのだ。あるいは、そう信じたかったかもしれない。
”魔女”に幻想を抱き始めていた彼はその思いを捨て切れていなかった。そして、それは結果として完全に正しかったのである・・・・
無人となった通路を二つの影が走り抜ける。
普通ならば、部外者が施設内をうろついていれば、警備員に見つかるなり、警報装置が鳴るなりするはずなのだが、現在の所、彼等は全くそれらしい妨害もうけずに、どんどんと施設の奥へと進んでいた。
「ありゃりゃ」
一人が、気の抜けた声を出す。
「これで20組目か・・・・」
もう一人もそれを見てあきれたように頷いた。
彼等は、ここへ来るまでに既に何十組みの警備員に出会っていた。
しかし、警告を受けることも拘束されることもなかった。
なぜなら、全ての警備員が気を失い戦闘不能状態であったからである。
それは言うまでもなく人の姿をした巨大な台風(!)が暴れまくった結果であった。
その台風の被害状況は尋常ならざる物である。
警備員の障害手当だけでも、すさまじいまでの損害をこの研究所に要求することになるだろう。
だが、その程度ですむならむしろ安いくらいだと、走りながら竜一は思った。
「しっかし、一体何が起きてんだろうな? まるで、台風でも暴れたみたいだ」
もう一人の男、康夫が心底感心したように言う。その原因を知っている竜一は苦笑するしかない。
その時、竜一の右肩に座っていたミューズの影が、一瞬揺らいだように見えた。
(え?)
慌てて目を凝らすが影は何事もなく、そこに変わらず存在している、だが・・・・
竜一が怪訝に思うと、シリスが竜一に話しかける。
(今一時的にミューズの力が不安定になりました。
ミューズの身に何かが起こったようですわね)
(ミューズに? 何かやばい状況にでも成ったかな)
(気になりますか?)
(ああ・・・・切れてなきゃいいが)
竜一もシリスもミューズの身の心配はしない。この世界で彼女に危害を加えられる存在がいるとすれば、メイルくらいのものだ。
だから、ミューズの身に何かが起こったとすれば、危険はむしろ彼女の敵にこそ有るのだ。
冷静な状態のミューズならば力を完全にコントロールしている。その状況なら大抵の妨害は簡単に破ってしまう。
だが、逆上したミューズは力のコントロールが甘くなる。
もしも、影が一瞬揺らいだのが、感情の高ぶりによる魔力のコントロールミスなら、最悪の状況となる可能性さえあるのだ。
(まずいかもしれんな・・・・)
「おい! 康夫、少し休もうぜ、俺疲れたよ」
「馬鹿ぬかせ、もう少しでゴールだ! 気張れ!!」
康夫のハッパに竜一は仰天した。
「マジ?」
「ああ、人の気配がする、もう少しだ」
康夫は断言した。
竜一には分からなかったが、康夫にはそれが感じとれるらしい。
そして、それが騒ぎの中心、一番面白いことであることを彼はその鍛えぬかれた第六感で感じとっていたのだ。
(まずい!)
竜一は焦燥感に駆られた。
もしも、予想通りミューズが切れかけていたら、どんなことになるか分からないのだ。
巻き込まれないようにした方が無難である。
何とか康夫を止めようとするが、しかし康夫には既に聞こえていなかった。
(仕方ねえ、シリス! ミューズを呼び出してくれ!!)
(先ほどからやっているのですが・・・・無視しているのか・・・・聞こえていないのか・・・・)
(ちい!)
竜一は内心で舌打ちした。
無視しているならともかく、感情が高ぶって聞こえていないとなると、これは最悪である。
かなり先に行ってしまった康夫の背中を探しながら、竜一は焦っていた。
「ひょおおおおお!」
感嘆の声をあげたのは最初にそこに飛び込んだ康夫だった。
少し広めの部屋。何もない殺風景なその部屋に巨大な結晶が立ち並んでいた。
「氷かな?」
そう思った康夫が触ってみると、ひんやりとして気持ちがいい。だが、氷とは少し感触が違う。
「氷とは少し・・・・にゅおおおおお!!」
「何アホな声を出してんだ?」
素っ頓狂な声にようやく追いついた竜一はそれを見た。
「人間の標本なんて・・・・始めてみた」
康夫が呟く。
康夫の言う通りそれはまさに人間の標本だった。
色とりどりのガラスのような透明な結晶、その中に人間が生きた姿のままで飾られている。
驚愕と恐怖に歪んだ醜悪な顔と美しい結晶の輝きのアンバランスさが奇妙に滑稽だ。
それがミューズの仕業であることは一目瞭然。竜一はそれを見て呟いた。
「馬鹿な連中だ・・・・」
彼等が何者か竜一は薄々分かっていた。
数百人もの警備員を叩き伏せたミューズ、その彼女を阻止するために来たにしては、武器らしい物を持っていない所から見ても、彼等が特殊なメンバーである事は疑いようがない。
おそらくは、この組織が作っていたという人造超能力者達だろう。
山勘に毛が生えた程度−ミューズ達のレベルから見ればの話であり、普通なら、一個大隊の戦力に勝るであろう存在−の超能力者をかき集めたところで、ミューズに対抗することなど不可能であるのに、彼等は無謀な挑戦をしたのだ。
その結末がこれである。
あまりにも当たり前すぎる結果であり、あまりにも愚かすぎる結末であった。
竜一には同情する気にさえなれない。
「阿呆が。素直に逃げれば良かったものを・・・・」
人間とはなんと愚かな存在なのか。
己の力を知識を過信しすぎて、己より遥かに巨大な存在に無謀な挑戦を挑む。
その結果がどれほど悲惨なものになるか考えもせず・・・・
感傷に浸っていた竜一に康夫が声をかける。
「おい、何してるんだ行くぞ!!」
「あ、おい、一寸待てって。こ・・・・これ宝石みたいだぞ。
どうだ、欠片だけでも持って帰らないか」
康夫の気をそらそうと必死に話しかける竜一だが、康夫の答えは淡泊だった。
「宝石なんぞより、あっちの方が面白そうだ!」
「相変わらず・・・・無欲な奴・・・・」
普段は美徳中の美徳の康夫の性癖だが、今回ばかりはその性格を恨んだ竜一だった。
(シリス、ミューズにさっさと終わらせろと連絡してくれ)
竜一はシリスにそう頼んだが、シリスはため息を付くだけだった。
(先ほどから試しているのですが・・・・ミューズは応じてくれません。
私の忠告を聞いていないようなのです・・・・おそらく、手遅れでしょう・・・・)
「そ・・・・そんなああ!」
竜一は、康夫を連れてきたことを死ぬほど後悔した。
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / < 10 > / 11 / 12 / 13 / 14 / 15