[ 三妖神物語 第四話 女神帰還 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第八章 償い。
1
「遅いわよ、シリス」
シリスの姿を認めてミューズが声をかける。
メイルとミューズは待ち合わせの場所に既にそろっていた。二人でシリスを待っていたのである。
「楽しかったか?」
メイルの言葉にシリスは頷いた。
「ええ、意外な人物とも再会できましたし」
シリスがそう言うと、ミューズが興味を引かれたようにその人物について聞きたがったがシリスはそれには答えなかった。
「ミューズ、あなたの方はどうでしたか?」
「・・・・まあ、滑稽だったわね。
別に人間に何の恩恵も与える気はないのに、私のことありがたがっちゃってさ。
笑っちゃうわ」
口調は辛辣だが、まんざらでもなかったようだ。それに、ミューズも十分に人間達に恩恵を与えている。
三妖神たる彼女達がいるからこそ、ヤフェイの野望に人間達が利用されずにすんでいるのだ。
その意味では、彼女も十分に信仰されてしかるべき存在なのだ。
ミューズはこの世界の人間を嫌っていた。だが、最近少しだけ考えを改めるようになっていた。
この世界の人間は主人たるマスタードラゴンを追放する原因となった。だが、そのおかげで、魔法と縁の薄い世界。彼を奇異な目で見ない世界に生まれるきっかけを作ったのだ。ある意味ではそのおかげで、今の彼は救われているかも知れない。
一見矛盾しているようだが、もしもニューデランがこのガルフェスール同様、魔法技術が発達した世界だったなら、マスタードラゴンの封じられている力を感知し干渉しようとする者は後を絶たなかっただろう。
魔法に対する知識のない世界だからこそ、力を封じている竜一の存在に殆どの者が気が付かなかった。そのおかげで、無用な干渉も殆ど無く、普通の人間として暮らすことが出来たのだ。
まあ、例外も多少いたようだが・・・・。
勿論、力が目覚めたなら、それ相応に問題も起こるだろうが、それはこの世界でも同じ事だ。魔法技術の発達したこの世界においてさえ、マスタードラゴンの力は異常すぎるものなのだ。
「先に戻る」
二人の意外に長いやりとりに業を煮やしてメイルが呟く。そして二人にかまわずに竜一の元に戻ろうと翼を広げた。
彼女の黄金の翼に、沈みかけた黄昏の日差しが反射して、あたりを朱金の輝きで染め上げる。
「もう、せっかちなんだから」
ミューズがそれに気がついて漆黒の翼を大きく広げる。二対の極黒の翼はそこだけに既に夜の帳が降りたような錯覚にさせる。ミューズに続いてシリスも白銀の翼を翻す。
本来は白銀の輝きを持つ翼はあたりの色を反射して、微妙に濃さの違う銀赤色に輝いていた。
「御主人様が心配です。急ぎましょう」
シリスはそう言って、いきなり術を使い、竜一の居る社へと転移する。てっきり飛んで帰るとばかり思っていた二人は唖然としていたが、直ぐに気を取り直しミューズが転移呪文を使いだした。
「何をあわてているのやら」
ミューズのその呟きを聞いてメイルは呟く。
「盟主、酒が飲めるようになったかな」
それこそが二人にとって最大の問題だった。
そして、程なく二人も転移呪文により、その場から消え去った。
二人が社の前に降り立つと、先に帰ってきたシリスは玄関前に立つ七人の女性と立ち話をしていた。その七人は二人にとっても顔見知りだった。
「お久しぶりですね」
「ええ」
赤い髪をした少年のように見える中性的な女性がミューズとメイルに声をかけ、それにミューズが答える。
「会ったか? 盟主に」
メイルの問いに首を振る。
「それどころじゃないようだよ」
「覗いてみれば分かります」
白い髪のたおやかな女性が複雑な表情で声をかけた。
シリスは渋い顔をして社を指さす。二人は顔を見合わせて、社を覗いた。
「さああ! 飲めえ! 飲むのよおおぉぉ!!」
「か・・・・勘弁・・・・して・・・・下さ・・・・い・・・・」
脅迫まがいの要求に涙を流しながら、息も絶え絶えに呻く竜一。
なんと、まるまる半日もの間、竜一は紅竜十二神将、炎那の責め苦を受けていたのであった。
竜王十二神将の責め苦、それはこの世で最も恐ろしく、最も厳しい拷問であった。
「炎那殿! 無茶はおやめ下さい!!」
慌ててメイルが間に入り竜一をひっぺがした。
「マスター、大丈夫?」
ミューズが竜一を抱き抱えて顔をのぞき込むと、彼の瞳が急速に光を失っていく。
まずいと感じたミューズは、ぺちぺちと軽く頬を叩いてみるが、反応が返ってこない。
慌てて襟首をつかんでがくがく揺すってやる。すると、光を失いかけていた瞳が見開かれ、竜一は頭を抱えてうずくまった。
「嫌だよお! 酒なんか嫌いだ!! 大っ嫌いだぁ!! お家にかえるう!!」
酒の恐怖に錯乱した竜一は完全に幼児に退行していた。大声で泣き出してしまう。
ミューズは自分の計画が裏目に出たことを今更ながら思い知らされたのであった。
「・・・・ですから、無茶をしないようにと・・・・」
シリスの苦悩の声に、ミューズは頭を抱えてしまった。
「・・・・うう、帰りたいよう。
ここはもうやだよう・・・・酒が追いかけてくるよう・・・・食べられちゃうよぉ・・・・」
幼児退行したまま現実から逃避して泣いている竜一をシリスが必死になだめているが、状況は一向に改善されなかった。
竜一とシリスを他の部屋に移した後、竜族の四人とメイルとミューズは宴会場だった部屋に残った。
半眼でメイルが炎那を睨む。酔いが覚めた彼女は流石にすまないと思ったのか、身体を縮めて落ち込んでいた。
「だいたい、他の方々が付いていながら、何をしていたのですか?」
ミューズが呆れたように他の三人を眺めると、三人は何とも言えない情けない顔をした。
「面目ない」
「私達も彼がディヴ・フェールだなんて信じられなかったから、もしかしたら、これで直るのかと思って・・・・」
「で、放っておいたのですが・・・・そのうちに、私達も宴会に突入してしまって気が付いた時には・・・・その・・・・」
三人の言葉と表情からミューズは呟いた。
「私達が来るまで気が付かなかったと言う訳ね・・・・」
ほとほとあきれ果ててミューズは頭を抱えた。
「り・・・・竜王十二神将ともあろうお方が・・・・偉大なる四十八貴竜とも有ろうお方達が・・・・」
メイルもあまりの事に呆然と呟いていた。
宴会と酒が大好きな竜族だ。しかも人間とは違い正真正銘底なしである。一度宴会に突入してしまったら最後、酒が切れるまで酒宴が終わる事はない。
いかに竜王十二神将といえども、酒については全く他の竜族と変わらない。ただ、竜族の中にも酒を好まない者もいるが、そういう者達は初めから宴会などには参加しない。
旧友を訪ねて酒盛りしようと企んだ彼等が酒嫌いなわけがなく、結果として乗りは悪乗りを、酔いは悪酔いを招き、このような事態に陥ったのである。
「ところで、
メイルはいつもならいるはずの見知った顔が欠けていることに疑問を感じていた。
「そういえば、気配もしませんね・・・・どうしたのかしら?」
ミューズも不思議そうに首を傾げる。
黒竜十二神将第四位、沙鋼。
竜族の中で、最もマスタードラゴンと親しい大親友である。
その昔、マスタードラゴンにシリスの存在を教えたのも彼だった。
もしもこの場に彼がいれば、ここまで無茶なことにはならなかっただろう。
メイルとミューズの疑問に、黒竜王十二神将第八位、紅銅 が答える。
「沙鋼殿は黒竜王陛下の命令で別の世界に出かけている。
いつ戻るのかは聞いていない」
彼の言葉にミューズとメイルは互いの顔を見合わせた。
しばらくして、ぽつりとミューズがもらす。
「・・・・今、彼がどこにいるのか、分かったような気がするわ」
「どう言うことだ?」
ミューズの言葉にメイルは首を傾げた。
しかし、ミューズはそんなメイルの言葉を無視して、自分の推理を検証する。
そして、一つの結論に達した。
「・・・・どうりで、普通じゃないとは思ったけど・・・・なるほど、そう言うことだったの」
しきりに、一人で納得したように頷くミューズ。
彼女の脳裏には有る一人の人物の顔が浮かんでいた。性格も能力もおよそ常識を外れた一人の人物が・・・・。
十二神将が竜界に戻ってからも竜一の幼児退行及び現実逃避は改善されなかった。
無理に正気づかせるのは危険と判断したシリスは、竜一を休ませるために奥の部屋に引きこもったまま出てこない。それを見て二人はレインボーシスターズとの対面を遅らせる以外にないと判断した。
「せっかくレインボーシスターズが来てくれたのに・・・・これじゃあ挨拶もできやしない」
久しぶりにマスタードラゴンと会える事を喜んでいた彼女達にどう説明すればいいのか、ミューズは苦いため息をついた。
「盟主が落ちつくまで待とう」
メイルの意見にミューズは頷いた。それしか無かったのだ。
2
「お久しぶりですね、マスタードラゴン」
「う・・・・うん・・・・」
やっとの事で正気に戻った竜一の前に新しい拷問、もとい、相手が待っていた。
「私達のことを覚えておいでですか?」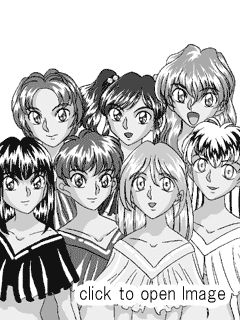
青い髪の女性が笑いかけるが、竜一は硬い表情で頷くだけだった。
「・・・・あ・・・・ああ」
「マスター、随分と堅くなっていますね」
「当たり前だろうが! ・・・・うう・・・・胃が痛い」
ミューズに怒鳴り、右手で胃の辺りをなでる。昨日から痛んでいた竜一の胃の痛みは、今日、最高潮に達していた。
それは、まさしく針の筵だった。
彼の目の前に並ぶ七人の女性。
竜族同様、竜一に、いや、マスタードラゴンにとって最も親しい相手。そして、償い切れぬ罪を負ってしまった相手。彼の罪をその身に刻み込んだ者達。
彼女達に対しては自分は神崎竜一ではなく、マスタードラゴンなのだ。逃げることは許されない。
彼女達に何を言えばいいのか、竜一には分からなかった。
遠い昔。親しく愛していた彼女達に償い切れぬ負債を負った。その償いは未だ終わらない。それなのに、自分はこの世界にいる。罪にまみれたままで。
こばわった顔で自分達を見つめる彼に、彼女達は彼が未だに罪の意識を引きずっている事を知った。
困った顔で七人の美女は顔を見合わせる。彼の心身の負担を何とか取ってやりたいとは思っているのだが、その有効な手段が見つからない。と、漆黒の髪を持つ女性が他の六人を押しのけるように前に出て竜一を見据える。
そして、表情を消した顔で竜一を糾弾し出した。
「確かにお前は私達に大きな罪を犯したわ。その償いはしてもらわなくてはね」
冷たい口調でそう竜一に言う。
「・・・・ええ、私は罪人です。どのような償いも、しなくてはなりません。
その覚悟は出来ています」
竜一は死刑囚のようにどん底に落ち込んだ表情を見せ、硬い口調で答える。
口調も竜一と言うよりマスタードラゴンになっていた。
シリスとメイルはその厳しい言葉に眉をひそめる。聖霊の彼女がそんなに厳しい事を言うとは思ってもいなかったのだ。
他の者達も、黒髪の聖霊の言葉に驚いていた。
「おい、何もそこまで言わなくとも・・・・」
赤い髪の女性が止めようと腕をつかむが、それをふりほどいて黒髪の女性が詰め寄った。
まっすぐに竜一を見据えて、言う。
「お前は私達と盟約を結び、友情を誓った。
にもかかわらず、挨拶もなくこの世界から姿を消し、その後も何の連絡もよこさないのは、明確な盟約違反。
この罪、どのように償ってもらえるのだ?」
「おお! それはそのとーりだ!」
「確かに、盟約違反ですね」
「責任者出てこーい!」
「ぜひ、マスタードラゴンの弁明を聞いてみたいものね」
彼女の言葉にいきなり他の女性達も賛同した。
「あ・・・・あの・・・・罪って・・・・」
竜一はめんくらってしまい、何を言えばいいのかまるで分からなかった。
こういう方向から攻撃されるとは考えてもいなかったのだ。
「なるほど、考えたわね」
ミューズが面白そうに笑う。
「これは、なかなか手強いですわね」
「やれやれ」
シリスとメイルも苦笑いする。
彼女達はつまらない罪悪感にとらわれ、この世界から逃げたがっている竜一を別の方向から牽制しているのである。それも、極めて理にかなった方向から。これでは、竜一は逃げられない。
「私は、己の力でこの世界を滅ぼしかけました。
その現実がある限り、この世界において私の罪は深く、許されるものではありません。
私の罪が許されると言うことは、ヤフェイの罪も許されると言うこと、それはこの世界にとって好ましいことではないはず」
ヤフェイは己の欲望によって、この世界を支配し均衡と秩序を破壊しようとした。そして、自分――マスタードラゴン――も怒りに己を見失い、この世界を滅ぼしかけたことがあった。
自分の罪はヤフェイの罪にも等しい。その自分が許されてはヤフェイをも許すことになる。それに自分は耐えられ無い。
自分の存在がヤフェイの罪を許す大義名分にされるのを彼は恐れていたのだ。
もしも彼の、マスタードラゴンの罪が許されれば、ヤフェイは必ず自分への処罰に対して不満を持つだろう。
「人の身でありながら現界を滅ぼしかけた邪悪な存在を許し、何故、それを阻止するために戦った私が処罰されなければならない!
私は神の威光を傷つけようとした邪悪な存在を抹殺するために戦ったというのに!!
何故、誰も私の功を認めようとしないのか!!」と。
ヤフェイにとって自分が現界にどのように干渉し何をなしたかなど、知らぬ顔で自分の功績のみを並べ立てることだろう。彼の脳に反省や自戒という言葉は登録されていないのだ。
そんな彼のことである、自分の罪を棚に上げて己の権威を、人間の支配神としての地位を返せと騒ぐに違いない。そして、マスタードラゴンという特例を作る事により神々もヤフェイに対し断固とした態度をとれなくなるのではないのか?
それがマスタードラゴンの苦悩だった。
竜一の言葉に柳眉をしかめて白い髪の女性が口を開く。
「あなたは重大な勘違いをしています。
あなたとヤフェイの罪は等しく無いと言うことを。
彼の罪が罪たる最大の理由は、己の罪を認めず神の地位を振りかざしていることなのですから」
ヤフェイはこの世界を破滅の縁に追いやろうとした、元々、マスタードラゴンがこの世界を破滅させかけたのもヤフェイのつまらない干渉が原因である。
だが、ヤフェイはその事を全く反省していない。いや、そもそも、罪を犯したという自覚さえなかった。
彼にとって、神である自分の権勢を高めることが全てであり、最高神になることが正義であった。その正義をなすためならどんな事をしてもかまわないと心の底から信じているのだ。それゆえに、彼は未だに自分の処遇に納得できず、事ある事に上級神族に対する不平不満を募らせているのである。
それに対して、マスタードラゴンは不必要なほどに自分の罪を重く考えていた。
元々ヤフェイの干渉の為に理性で押さえていた力が暴走してしまったのだから、マスタードラゴン本人も被害者と言っても良いくらいだ。それなのに、過剰なまでの罪悪感を持ち、この世界から追放されることを自ら望んだのだ。神々や魔族が猛反対したというのに。
神々にとって三妖神とマスタードラゴンは貴重な戦力である。虚無世界の邪神と戦うために無くてはならない存在だった。
絶対的な力を有する竜王と竜族が存在する間は心配はない。
しかし、竜族はあまりにも強すぎる力を持つ。そのため、その存在自体がこの世界に負担を与える。その結果、竜王や竜族が長期間この世界で活動することは困難となる。
竜族が居るうちは良い。だが、彼等が休眠期に入った時、マスタードラゴンと三妖神が居なければ、結局この世界は破滅の危機にさらされる。
彼がこの世界から居なくなると言うことは、それだけでも大きな罪になるのだ
が、困ったことにマスタードラゴンは自分の価値を正当に評価してはいなかった。
そのために、どれほど神々や魔族が彼がこの世界に残ることを欲していたか、まるで理解していなかったのである。
いや、多少は知っていたのかも知れない。だが、特別な力を持つから、特権を持つからという理由だけで自分が特別扱いを受けることを彼自身が許せなかったのだ。
”罪には罰を持って。”それが彼の考え方である。
例え神であろうと、罪を犯したのなら裁かれなければならない。この世界を守る力を持っていても罪を犯した者がその力を盾に罰から逃れることは許されない。
それが、彼の考えであり、彼は自分の考えに素直に従ったのだ。
その時、自分の使い魔たる三妖神をこの世界に残したのは、罪を犯した自分に付き合わせたく無かった事と、何より邪神に対抗するためであった。
だが、神々や魔族が彼の罪を不問にしようとしたのはただ単に戦力としてだけではなく彼と言う存在を愛していたからだ。
そして、聖霊達も彼を愛していた。そうでもなければ契約などするはずがない。
その愛する者が自分達の知らぬ間にこの世界から姿を消していた。それも、自分達が眠っている間に。これが許されることだろうか? いいや、断じて許されることではない。
自分達から彼を奪おうとしたヤフェイも、自分達との契約を一方的に破棄しこの世界から逃亡してしまった彼自身も。
だから、償わせる。そして、この世界に戻ってくるようにしむけるのだ。
「あなたは今、ヤフェイと同じ過ちを犯そうとしています」
白い髪の女性にそう言われて竜一は一瞬動揺した。
「過ち・・・・?」
「そうです。
あなたは自分の勝手な思いこみにとらわれ、他人の意見に耳を傾けようとしない。
それは、自分の欲望におぼれ他人の諌言に従わないヤフェイと同じではありませんか?」
それは、竜一にとって大きな驚きだった。自分は罪を認めそれを償うことが贖罪になると思っていたのに、それが彼女達にとっては裏切り行為に等しかったのである。
「私は・・・・どうすればよいのです?」
途方に暮れた竜一、いや、マスタードラゴンに聖霊達は笑顔で自分達に対しての償いを要求した。
「そうね、向こうの世界でどんな生活をしていたのか、まず、それから話してもらいましょう・・・・」
3
竜一のお守りを聖霊達にまかせて、再び三妖神は現界を回ることにした。
「今日は少し遅くなるわ」
「わたくしも私用がありますから・・・・」
ミューズとシリスの言葉にメイルが眉をひそめる。
「爛華と麗華をメセルリュース様に会わせる必要があるの」
「わたくしは竜王様にお話が・・・・」
それ以上の事をメイルは聞かなかった。二人にはそれぞれ胸に何事かを秘めているらしいが、それが盟主マスタードラゴンに不利益になるようなことはないとメイルは確信していた。二人ともマスタードラゴンに対する忠誠心と愛情は強固な物なのだ。
「わかった、なるべく早く戻れ」
そう言うとメイルは黄金の翼で天に駆け上がり、すぐに視界から消え去った。
「さて、私も行くわね」
「ええ、それでは」
二人も頷いてその場から消え去った。
4
赤い髪と朱色の瞳を持つ勝ち気な感じの美少女が歪んだ空間にたたずんでいた。
ここは精霊界と黎明界の中心に位置する狭間。
「姉さん・・・・」
静かに呟く。
ここで彼女の姉は消え去った。その時、双子の彼女だけがそれに気が付いた時、彼女自身も激痛にさいなまれた。
その苦痛から解放されたのは実に数万年もの時を必要とした。
そして、動けるようになってから、その原因を、姉を消滅させた存在を探し続け、ついにそれを見つけた。だが・・・・・
「・・・・今更・・・・復讐なんて・・・・ね」
悲しそうな微笑みを浮かべて進む。姉の意識が消えた場所、姉の声を聞いた最後の場所に。
そこに、先客がいた。
白銀の美しい髪がその背中を覆い隠してはいるが、その独特の気配はすぐに分かる。だてにミューズの部下を長年やっていた訳ではないのだ。
「・・・・シリス様・・・・、何故こんな所に・・・・」
そこにたたずんでいたのは薬神シリス。
銀の女神はその足下に花束を添えていた。
死者に花束を手向けるのは人間の風習だった。だが、彼女はその行為をこの世界、精霊と神の世界の入り口の狭間で行っていたのだ。
普通なら、現界の花を物理法則の違うこの場所に持ってくることは出来ない。
普通の物質ではその形を維持できないのだ。
シリスが持ってきた花は本物の花ではない。いかに死者のためとは言え今生きている花を手折ることはシリスにはできない。だから、花達の精気をほんの少し分けてもらい、それを自らの力で具現化したのだ。
人間達の間では”霊花”とも”聖花”とも呼ばれ、奇跡の花と珍重される物である。
「・・・・朱雀、あなたへの贖罪の時が来たのかも知れませんね」
「贖罪と申されますと?」
硬い口調で朱雀が答える。それに、シリスは静かに答えた。
「あなたの姉。聖火さんを死なせてしまったのは私の罪です。
その償いをしなければなりません」
朱雀はその言葉を呆然と聞いていた。
精霊・
彼女はその日、上級精霊となったため、神々への挨拶をするために黎明界を訪れようとした。それは不運だった。
その日、狭間の空間、神々の結界が破られ、そこからバシリスクの末裔。シリスが現れたのだから。
狭間の空間に漏れ出たシリスの力はごくごく僅かな物だった。だが、それでも精霊の存在を消し去るには充分すぎた。
狭間を通る瞬間。彼女はシリスの毒気に当てられ、精霊界からも黎明界からも消滅してしまったのだ、永遠に。
「何時から、気づいて居られました? 私が聖火と姉妹だと・・・・」
「それほど昔ではありません。御主人様に力を封じていただいた後、この世界を色々と見て回った時に、この空間で精霊が一人亡くなられたと聞きました。
その後、色々な方々から話を聞く内に・・・・」
重い言葉を吐き出す。
「それでは、私がお仕えする事を拒絶なさったのは?」
朱雀は長い間心に持っていた疑問を口にした。
遥かな昔、薬神シリスに仕えることを望んだ彼女だが、シリスはそれを断ったのだ。
「あなただけではなく他の者達の従属も拒否していたのは知っていますね」
シリスの言葉に朱雀は大きく頷く。
「あなたを拒否したのは他の者達と全く同じ理由です。
確かにわたくしに従属することを願う者達は大勢いました。
いえ、今もいるかも知れません。
ですが、それはあくまでも”薬神”シリスに対しての事。
わたくし自身。”魔獣バシリスク”の末裔、シリスに対しては一人もいません。
何時か、わたくしに施された御主人様の封印が効力を失い、薬神から魔獣に戻った時、薬神にあこがれた者達はどう感じるでしょうか?」
淡々とシリスは語り続ける。
「所詮、薬神シリスとは虚像に過ぎないのです。
その虚像に惑わされ、わたくしの本質を知らない者にわたくしに仕えることは出来ないのです」
”薬神”はシリス自身にとって虚像だった。シリスにとって、それはマスタードラゴンに与えられた姿であり、自分自身ではないのだ。
虚像に惑わされ、それしか見えていない者が自分に仕えた時、薬神の虚像が失われたらその者達はどう思うだろうか?
裏切られたと思うだろう。自分自身の勝手な思い込みによって。
だから、シリスは誰も部下にしない、誰も部下になる資格がなかったのだ。
彼女に仕えることを許されるのは、本来、彼女の本当の姿を知り、なおそれを受け入れた者だけなのだから。
人間の信者達は例外なのだ。
人間達の間で薬神シリスの名が高まれば、彼女の主人たるマスタードラゴンの名も上がる。そうなれば、例えマスタードラゴンの力が嫌悪されていても人間界に存在することを彼は許されるだろう。
シリスは自分自身のためではなく、主であるマスタードラゴンの生きる場所を作るために”人間にとって理想的な女神”薬神シリスとして振る舞っている、とはシリスのいつもの言い分なのだった。
・・・・だが、三妖神の一人、雷神ミューズはそれを殆ど信じてはいなかった。確かにマスタードラゴンがいた頃にはその効果もあった。それは認めるが、今マスタードラゴンはこの世界にはいない。さらに言えば彼の存在もマスタードラゴン自身の手によって抹消されている。
そのために一般の人間は彼の存在を知らない。神官や魔術師、そしてトリニティアの歴代皇帝だけがその存在を記憶に止めているだけだ。すなわち、今現在に置いてシリスの言い分は全く意味をなしていないのである。
結局、何だかんだと言い訳をしてはいるが、シリスが病に苦しむ者を見捨てられない性格だったと言うのが事実であろう・・・・
「では、私がシリス様に復讐するために近づいたのを見抜いていたわけでは」
朱雀の言葉にシリスは頷いた。
「わたくしがあなたと聖火さんの事を知ったのはもっと後のことでした。
勿論、あなたが復讐の機会をうかがっていたことを知るのはもう少ししてからでしたし・・・・
あなたがわたくしに仕える事を拒絶した理由は先ほど話したとおりです」
「でも、どうして・・・・
どうして今頃になって・・・・」
戸惑いながら問う朱雀にシリスは寂しそうに微笑む。
「もう、わたくしの存在は御主人様に必要ではありませんから・・・・」
自分は、現界に生きる意味を見いだせなかったマスタードラゴンの命をつなぎ止める為の存在だと、彼女自身思っていた。
彼女を、その力を必要としていた者は大勢居た。神々も魔族も彼女の力を貴重な存在と思っていたが、彼女そのものを必要としていたのはマスタードラゴンだけだった。
彼は彼女を守ることが自分の存在意義だと思っていた。彼の強大な力はそのために必要不可欠の物だった。
マスタードラゴンの竜王にさえ匹敵する絶大な力がなければ、神をも滅ぼすシリスの力を封じることなど出来なかっただろう。それは、運命の皮肉だった。
だが、今、強大にして危険極まりない彼の力は安全なレベルに封印されていた。
ヤフェイのくだらない策謀により、彼はこの世界にいられなくなったが、その時、ミューズの機転によってその力を封印することに成功したのだ。これもまた、運命の皮肉だった。
ヤフェイがくだらない策を労しなければ、今なお彼は強大な力を持て余し苦しみながらも、かりそめの平安の日々を生きていたことだろう。
ヤフェイの汚れた欲望が結果として彼を苦悩から救ったのだ。それは、皮肉な運命と言うには、あまりにも歪んだ結末だった。
そして、別の世界で、彼は人として生きる喜びを見いだした。もう、自分の力におびえることもない。己の命を軽んじて自ら絶つ事も無いだろう。
向こうの世界、ニューデランで初めて目にしたマスタードラゴン、いや、神崎竜一の生き生きとした表情を見て、シリスは自分の役目が半ば終わったのだと感じていた。
だから、清算するつもりだった。自分の最後の罪を。
自分の力の犠牲になった、唯一の存在に対しての贖罪をこの場でするつもりだったのだ。
「わたくしの存在は、もう、御主人様には不要なのです。
あなたの望みを邪魔する者もここには居りません。
この剣をお使いなさい、そうすれば、わたくしの邪悪な力を漏らすことなく、わたくしの命を絶つことが出来ます」
そう言って、一振りの短剣を朱雀に手渡した。
朱雀は自分の手の中にある短剣を見る。鋭い刃には冷たい光が宿り、その側面には剣先から鍔もとまで、びっしりと細かい文様が彫られている。
それは、竜族が生み出した最高の魔力を秘めた言語。”ドラゴンルーン――竜神呪術文字――”。
それを使いこなせる者は竜族を除けばマスタードラゴンと雷神ミューズのみと言われている。それ程の難易度を誇る最強呪文。
それは、遥かな昔、シリスの護身用にとマスタードラゴンが彼女に与えた物。
万が一、彼女の力が漏れ出たときのために与えた物。補助結界を作るためのお守りのような物だった。
確かにこの剣ならシリスを傷つけても彼女の悪しき力を封じることが出来るはずだ。
「わたくしの覚悟は出来ております。さあ、あなたの望みを果たしなさい」
優しく促すシリスに朱雀はしばし呆然と自分の手の中にある短剣の重みを感じていたが、顔を上げてシリスを見ると静かに頭を振った。
「いいえ、シリス様を傷つけることなど出来ません」
そう言った朱雀の表情は晴れやかなものだった。
「シリス様はご自身を過小評価しすぎです。
私がもしもシリス様にかすり傷でも付けようものなら、天界・魔界・現界の住人達、そしてなにより、精霊界の知り合いたちから、よってたかって袋叩きにされてしまいます」
おどけた表情で肩をすくめる。
朱雀はちゃかしていたがそれは完全な現実である。いや、もしも本当にシリスを傷つけでもしたら、袋叩きくらいではすまないに違いない。
神と魔王、竜族や精霊、妖魔に妖精。そして、強欲な人間達。あらゆる存在に愛される存在。それが薬神シリスなのだ。困ったことにその事を本人は殆ど自覚していなかった・・・・。
「それに、シリス様の役目、ドラゴン様のお守りと他のお二人の監視の役目はまだ終わっていないはずです。
力を失った今のドラゴン様にあのお二人を止められるとお思いですか?」
ミューズとメイル。あの二人を諌められる者は今やシリスのみであろう。
この世界なら竜王が居る。しかし、竜一達が暮らす世界”ニューデラン”には、二人を止められるような存在は居ない。
少なくとも朱雀の知る限りにおいては、シリスだけが二人を抑えられる存在なのだから。
言葉無く彼女を見つめるシリスに朱雀はいきなり悪戯っぽい笑いを向けた。
「それに、いくら私達、精霊が人間より長い時を生きる存在でも、心の傷をそれほど長い間持ち続けることは出来ません。
私の心の傷はもう癒されています。何しろ、五百億年以上前のことですもの」
「え?」
朱雀の台詞にシリスは言葉を失った。
「・・・・五百・・・・億年?」
「ええ、そうですけど・・・・それがなにか?」
訝しげなシリスに朱雀は首を傾げる。
「・・・・二十億年・・・・では無いのですか?」
シリスがそう問いかけると、今度は朱雀が凍り付く。
「・・・・いいえ、五百億年ですけど・・・・」
「・・・・」
絶句するシリス。彼女の頬には一筋の汗が流れていた・・・・。
・・・・シリスを封じていた封印。
それは時間の流れさえ歪ませる特殊な結界だった。それにより、万が一結界が破れても時間の流れの違いによりシリスの毒が外の世界に漏れる時間を遅らせることが出来るように作られていたのである。
そのためにシリスが感じていた数十倍の時間が外の世界では流れていたのである・・・・。
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / < 9 > / 10 / 11 / 12 / 13 / 14