[ 三妖神物語 第四話 女神帰還 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第二章 旧友参上! 大宴会!!
1
「さて、これからどうしたものか・・・・」
竜一は自分にあてがわれた部屋の窓から外を眺めて呟いた。
三妖神はこの祭りの期間はあちらこちらに顔を見せなければならない、かなり忙しい身の上となる。
いつもなら竜一の側に控えている彼女達だが、今回はそうも言っていられない。
三人はそれぞれ、祭りの準備に忙しい。
時間がくれば彼女達はそれぞれの”人の世”の御座所へ向かうことになる。
三妖神には二種類の
一つは神として、人とは関わらずに暮らす場所、すなわち、今竜一が居るような”聖域”と呼ばれる場所である。
ここは余程の事情がない限り、人間が訪れることは許されない。たとえ許されたとしても、ここに来ることが出来るのはそれぞれの宗派の大神官とトリニティを束ねる大神官長だけだ。
そして、もう一つは人の世の、あるいは”常世の御座所”と呼ばれる、神と人との接点たる場所。
一般的に神殿と呼ばれる人と神との交わりの場所である。
そのあいだ、竜一は何をしているかというと・・・・あきれたことになーーんにもしないのである。これが。
この祭りは三妖神を祭るものであり、竜一にはなんの関係もない。
この世界に彼の知り合いは居ない。
子孫、あるいは血縁関係くらいならいるかも知れないが、三千年もの時が過ぎている上に、それは前世の話である。
今生の竜一にとっては真っ赤な他人だ。顔を見せる義理もない。
一人でうろついて祭りを眺めるという手もあるのだが、自分を罪人だと思っている竜一には、そんな気は起きない。
つまり、十日間この社の中で怠惰に時を過ごすことになるだろう。
「テレビも漫画もパソコンもゲームもない十日間・・・・た・・・・退屈だ・・・・退屈すぎる!」
「そんなに退屈なら、町に出て遊べばいいのに。ほら、お金だって有るし」
そう言ってミューズは大きな革袋を一つ投げてよこした。
口の紐をゆるめて中を見る。
新品の銀貨がぎっしりと詰まっている。袋の大きさからして、数百枚程度は入っているだろう。
「こっちの世界の通貨よ。
金貨もあるけど、銀貨の方が使いやすいし、これだけ有れば一年は余裕で遊んで暮らせるから、祭りを楽しむ資金としては十分でしょ?」
ミューズが笑いながらそう言うと、竜一はため息をついた。
「別にいらねえよ。ここから出る気はないし。
十日間、ここでごろごろしているから、食い物さえ有ればいい」
「せっかくの祭りだ。少しくらい楽しんでも・・・・」
メイルがそう言いかけたが、竜一は頭を振った。
「・・・・御主人様・・・・」
何かを言いかけたシリスだが、その続きは言葉にならなかった。すると、やたらと明るくミューズが二人に声をかける。
「さて、そろそろ出かけましょう。
マスター、食料は倉庫に入っているから好きなように食べててね。
あと、退屈なら二階の書斎と地下の蔵書庫にこの世界のあらゆる書物があるから、退屈ならそれを読めばいいわ」
「書物?」
「そうよ。歴史や学術書から娯楽小説。それから、漫画もあるわ」
「漫画があるう!?」
ミューズの台詞に竜一は心底驚いた声を出した。
「所詮、人間の考える事なんてどんな世界でも似たようなものよ」
頷いてミューズは答えた。
ミューズの社にはこの世界に存在する全ての書物がある。有史以来の人間の知恵の集大成が彼女の手元に保存されているのだ。
学術書や技術書。神話や伝説を書き記した粘土板。大衆娯楽の小説から新聞にいたる有りとあらゆる書物が彼女の社に存在する。
現界で人間が作った書物は全て彼女の手元にあると言っても過言ではない。それどころか、人間社会では既に失われた書物さえ山の様に積み上げられている。
それは、彼女が知識神として崇拝されているためである。
魔術と学問の女神、雷神ミューズに人々は感謝のしるしとして、新しく作られた書物を神殿に備える。神殿に備えられた書物はその瞬間にミューズの元へと届けられる。すなわち、雷神ミューズにとって書物こそが供物なのだ。
そのおかげで、かつてヤフェイが世界を支配しようとしたときに焚書にされた数多くの貴重な書物や知識が彼女の元で守られた。
その後、現界で失われた知識を人間達に与えてやるために、ミューズは自分の手元にある書物の複製を現界に送り続けている。
ただ、その量があまりにも膨大なため、まだ、かなりのものが社の中に眠っていた。
部屋から出ていく時、ミューズはふと思いだしたように足を止めて竜一に振り返る。
「ああ、そうそう。
町へ出たくなったら、地下の”扉の間”に行けば、この世界のどこにでも行けるわ。
好きなように遊んでね」
「扉の間?」
「そう、この世界の主要な場所に直通の門が有るの。
現界は勿論、神界・魔界・精霊界、それに竜界にも通じているから、退屈はしないんじゃない?」
そして、門の使用方法を簡単に教えてくれた。
「別に使わないと思うが・・・・」
そう言いながらも、結局聞いてしまった竜一である。
「はーーー、退屈だ・・・・」
青い空を流れ行く雲を見上げ、欠伸をしながらため息を付く。
この世界の小説や漫画にも興味はあったのだが、部屋を覗いてみてあっさり挫折した。
空間を圧縮した、やたらと広い部屋の中に足の踏み場もないほどに書物が積み上げられていたのだ。
一応、学術や芸術、娯楽作品や通俗的な書物など分類別に分けられてはいるが、その量を見たとたん目眩を感じ、何も持ち出さずに部屋から退散してしまったのである。
「まあ、本当に退屈になったら読めばいいか」と自分でも良く分からない言い訳を呟きながら、結局、窓辺でぼーーとする竜一だった。
「でも、何もしないで、ぼーーっとするのも、悪くないなあ・・・・」
向こうの世界では、ミューズ達の作った世界でもない限り、四六時中騒音が聞こえ神経を痛めつけてくれた。
普通の状態でも、車の騒音が良く聞こえる場所に彼のアパートはあった。
だからこそ、値段の割に広い部屋が確保できたわけだが、その騒音のために、心底のんびり出来た試しはない。
時折、訳の分からない集団が宣伝カーで走り回り、スピーカーでがなり立てたりしてくれる時など、ミューズに抹殺命令を出そうとして、喉元まで出かかったそれを必死に飲み込んだことも、一度や二度ではない。
それがここにはない。
人里から遥かに離れた社。
自然の精霊と魔族、獣と鳥、虫と植物達がいるだけだ。
耳に届くのは鳥のさえずりと、虫の声。木々のささやきと水のせせらぎ。
それらは、心地よいハーモニーとなって、竜一に安らぎを与えてくれる。
「・・・・こういうのも・・・・たまには良いかも・・・・しんない・・・・」
すでに、瞼が落ちかかっている。半分夢心地である。
今、竜一は極めて無防備な状態だった。
三妖神は彼の側には居らず、彼自身、思いっきり無防備である。
だが、それで何の心配もなかった。
なぜなら、幸いなことにこの世界では彼を狙う者は存在しないのだ。
いや、正確に言えば、彼を狙う者は存在はする。すなわちヤフェイである。
しかし、この現界に干渉する権利をヤフェイは失っているのだ。
有る程度自由に動ける天使ならば彼を脅かす事もできるだろうが、それをすれば、さらに自分の立場が悪くなることくらい、いくら無謀で無能なヤフェイでも十分に承知しているだろう。
なにより、無理に竜一に手を出そうとしても、精霊や妖魔や魔族が黙ってそれを見ているはずがない。
彼に近づこうとしただけで、天使は八つ裂きにされる事になる。いや、それ以前に聖霊にして、三妖神とマスタードラゴンの親友たる”虹の乙女達――レインボーシスターズ――”が黙ってそれを見過ごすことはない。
そして、この社にはミューズの強力な結界が十重二十重にかけられている。
たとえ、ヤフェイ自身が仕掛けてきても、びくともしない頑強な守りに守られているのだ。
結局ヤフェイとその天使には何もできないのである。
ヤフェイにしてみれば、本来の世界では手出しできず、異世界でしか行動できないと言うのは何とも皮肉な話に違いない。
ぼーーとしていると、時折、小さな風が彼の髪の毛に触れ、まるで名残を惜しむように小さなつむじ風となり去っていく。
それは精霊達の静かな挨拶。しかし、竜一がそれに気づくことはなかった。
2
三妖神はミューズの社から神界と現界の接点、黎明界の入り口へとたどり着いた。
そこで、ミューズは自分の配下の者達を呼び出した。
ミューズに仕える者達の中で最強の力を持つ雷神四天王。精霊・朱雀、妖魔・迅雷、そして、双子の精霊・爛華と麗華が最後に現れて、ぞれぞれが挨拶をする。
ミューズが四人に声をかけた。
「私達はこれから神界に挨拶に行くわ。
この祭りが終わるまで、あなた達は自由にしなさい。
勿論、あなた達の部下にもね」
にっこりと笑うミューズ。彼女の元には彼女の力に魅せられた精霊や妖魔が数千も集っている。そのうち、ミューズ自身が認めた二千の精霊や妖魔達はそれぞれ、四天王の管轄にされていた。
ミューズが認めていない、いわばもぐりの使い魔の数はミューズ自身把握しきっていないが、一説には五千とも一万とも言われていた。
朱雀は、シリスを見つめる。
彼女の瞳には静かな光が宿っている。彼女はどうやらシリスに対して特別な思いが有るらしいが、詳しいことは他の者達は知らなかった。
ただ、彼女が元々シリスに従うことを望んでいたのは事実である。結局シリスはそれを断ったのだが、ミューズが彼女の力を惜しんで自分の部下になるよう誘い、彼女もそれを受け入れたのである。
シリスを見つめていた朱雀は直ぐにミューズに顔を向けて挨拶をする。
「それでは、私は精霊界に戻ろうと思います」
迅雷もミューズに挨拶した。
「私は魔界へ戻り、魔王様に今までのことをご報告いたします」
爛華と麗華も精霊界へ戻るとミューズに言うと、ミューズは何かを思いついたかのように声をかけた。
「ああ、そうそう。
爛華と麗華は明日、私の元に戻ってきて。大切な用があるから」
その言葉に二人は頷き、そして四人の姿はかき消えた。
それを見送って、三人は黎明界へ向かった。
「ただいま帰参致しました。メセルリュース様」
三人を代表して、黒い髪を背中の中程までのばした黄金と淡く青みがかった銀の瞳の女性が、深々と頭を下げ、他の二人もそれに倣う。
「お帰りなさい。どうやら、無事に彼と再会できたようですね」
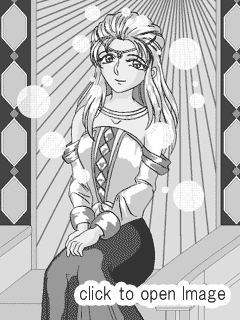
優しい声で答えたのは、正面の玉座に座る女性。
淡い光をまとった銀の髪。深い優しさを秘めた紺碧の瞳を持つ、人間の年齢で言えば、二十代前半といった慈愛と包容力を感じさせる美女。
全ての命を育む大母神、創造神の娘にして女神の長。
大聖母神、メセルリュース。
「はい」
メセルリュースの問いに、穏やかな笑顔で答えるミューズ。
しかし、直ぐにその表情を改め、再び礼をする。
「今回、こちらにご挨拶にうかがったのは、私達の祭りに出席するためです。
こちらの世界で活動する許可をいただけないでしょうか」
「・・・・くすくす、ミューズ、らしくない挨拶はよろしいですわ。
そのような形式的な挨拶は私達には不要のもの」
メセルリュースが笑いをこらえてそう言うと、彼女の左右に控えている男女が大笑いする。
「まったくだ、堅苦しい挨拶など我らには不要だろうが! さっさと、いつも通りのお前に戻れ!」
「聞いてると、背中がむずかゆくなるわい」
「そうそう、シリス殿ならともかく、ミューズ殿には似合わぬよ」
口々に勝手なことを言う。
「酷いわねえ・・・・せっかく神が格好つけているのに」
思わず苦笑するミューズ。
「何が格好つけているのに・・・・よ、笑いをこらえるこっちの身にもなってよね」
「いや、まったく」
その場に居合わせた男女――神や魔王達――は笑いながらそう言う。
「ただいま戻りました。みなさまもお変わり無く」
「シリス殿、変わりようなど有るはずが無かろう?
そなた等が向こうに行ってまだ半年ほどだ」
「久しぶりと言うほど時はたっておらんよ」
「それもそうだな」
メイルが答え。シリスも頷いた。
「それもそうですね」
「ところで、ディル・フェライン殿は・・・・失礼、今は”神崎竜一”さんとおっしゃるのでしたね。
彼はおかわりありませんか?」
メセルリュースがそう尋ねると、ミューズが答える。
「特にこれと言って変わったことはありません。
封印も機能しており一般の人間として問題なく暮らしていたようです。
ただ、”奴”の息のかかった者達や力を欲する者達に目を付けられ始めていますが・・・・
それにしても、今のマスターの名をよくご存じで」
ミューズの疑問にメセルリュースは曖昧な笑いで答えた。
「それにしても、三千四百年ぶりにマスタードラゴンが帰還されたか・・・・」
「我らにとっては瞬きするほどの時にすぎぬはずだったが・・・・彼が居なくなってから妙な喪失感がつきまとっておった・・・・」
「まったく、たかだか三千年程度の時間をこれほど長く感じるとは思いもしませんでしたな」
たくましい肉体を誇る大男と、細身だが鋭い強さを秘めた男が頷き合う。
このガルフェスール世界を守護する神界最強の守護者、闘神バラスレフィスと魔界を守る最強の戦士、魔王将軍レグラフィス。
双璧と讃えられる二人の闘神を見て、興味深そうに白髪をした賢者、知識の最高神ファベリアスルが呟く。
「私にとっては別にそれほど長くは感じなかったが・・・・感情というものは時間の長ささえ変えてしまうものなのか・・・・なかなか興味深い」
神族や魔族は元々感情を持ってはいない。だが、人間が誕生した時、感情を持つ彼等を見ている内にそれに興味を持った神や魔族が現れた。
そして、今では暇つぶしに感情を持った者とそれを拒否した者。そして、純粋にそれを研究対象とした者に別れたのである。
知識の至高神ファベリアスルは数少ない感情の研究者だった。
「ねえねえ、それで、今の彼の様子はどお?
久しぶりに古巣に帰ってきて喜んでいたでしょう?」
ミューズに魔王帝ヴェスリエルが子供っぽいしぐさで笑いかけた。
外見を見る限り幼い少女にしか見えない彼女だが、その愛らしい姿とは裏腹に魔族最強の魔力を誇る大魔王である。
「それが、相変わらずの石頭でねえ・・・・」
苦笑を張り付けて答えるミューズ。
「・・・・自分の罪はまだ清算されていないと言い張って・・・・な」
処置無し、といわんばかりにメイルが頭を振りながら嘆息する。
「そう・・・・」
寂しそうにヴェスリエルが答える。
「・・・・あの・・・・本当に申し訳有りません・・・・
わたくしが至らぬばかりに皆様にご迷惑を・・・・あの・・・・わたくし・・・・なんとお詫びして良いのか・・・・」
ほとんど泣きそうな顔で小柄な女性が三人に頭を下げた。
「あなたの責任ではありません。そんなにご自分を責められることは・・・・」
シリスが気遣って声をかけるが女性は頭を強く振って否定した。
「わたくしがもっとしっかりしていれば・・・・
わたくしの半身があの方をおとしめるような真似をしたのは、わたくしのミスです・・・・。
もっとしっかり彼を監視していれば・・・・このようなことには・・・・」
「過去のことを悔やむのは止しましょう、大切なのはこれからどうするかですわ」
シリスが励ますと、ミューズが後を継ぐ。
「そう、そのためにあなたに協力してもらっているのだから。
今度こそ、あの馬鹿を地獄の底にたたき落としてやるわ!」
「あらあら、神界きっての策謀家が何やら悪巧みをしているようね。
お手柔らかにお願いね」
美と愛の女神、ファレルシーダがその美貌に笑顔を浮かべる。
「ミューズ、お前、何を企んでいる・・・・」
メイルが不信感(と、言うほど大げさな物ではないが・・・・)を込めた瞳で睨み付ける。
「企むとは失礼ね。マスターを守るための当然の布石をしているだけよ。
まあ、一種の保険ね」
不快感を全身で表現しているメイルにミューズはからかうように笑いかける。
「相変わらずの秘密主義だな・・・・少しはあたい達にも相談しろよ」
溜息をつくメイルにミューズはすました顔で答えた。
「乙女のひ・み・つ」
「・・・・あのなあ・・・・」
額に片手を当てて唸るメイル。
「わたくしも、そのお話をお聞かせ願いたいのですが?」
シリスにまで追求されるが、ミューズは答えようとはしなかった。
「だーめ、何しろ、ヤフェイ撃退作戦の切り札なんだから、迂闊には話せないわ」
「切り札・・・・ですか?」
「そう」
シリスの問いかけにミューズは力強く頷く。
「仲間内でも秘密かあ・・・・じゃあ、私達には絶対に漏らせ無いって事だな」
「そうよ。申し訳ないけどね」
ヴェスリエルにミューズが頷く。
「どこから情報が漏れるかわからないからね・・・・そう言うことだから宜しくお願いするわね。聖魔王殿」
ミューズが視線を向けると、先ほど三人に泣き顔で謝った、少女と見間違うほどの小柄な女性は静かに頭を振った。
「その件に関しては既に覚悟は出来ておりますが・・・・わたくしには、”聖魔王”などとたいそうな名で呼ばれるような資格はありません・・・・」
伏し目がちにそう呟く彼女にミューズは苦笑した。
「まったく、変なところで意固地なんだから・・・・マスターはルシフェリラ殿の性格を受け継いだのね。きっと」
「ああ、間違いないな。変なところで良く似ている」
「そうですわね」
ミューズの誉めているのかけなしているのか良く分からない言葉に、メイルとシリスが交互に頷ずき、人の世の闇を見守る魔王、ルシフェリラは顔を赤らめて縮こまってしまった・・・・
そして、しばらくの間、三人は色々な神々や魔王達と会話を楽しみ、情報を交換しあった。とはいえ、わずか半年の留守であるからそれほど変わったことがあるわけではない。ただ、ミューズはヤフェイとその一党の動きを特に注意深く聞いていた。
「ところで、メセルリュース様。ラフェリメール殿のお姿が見えぬようですが?」
ミューズがそう尋ねると、メセルリュースが笑って頷いた。
「彼女には大切な仕事を頼んでいるので・・・・しばらくは私の元には戻りません」
「メセルリュース様が片腕のラフェリメール様を手放されるなんて・・・・よほど大切な御用のようですわね・・・・」
シリスがそう言うと、メセルリュースは頷いた。
ラフェリメールはメセルリュースの片腕と言われるほどの存在である。女神達の伝令役であり、メセルリュースの親友でもあった。
その彼女がメセルリュースの元を離れるというのは、よほどの事である。
しかし、そのことは三妖神は勿論、他の神々や魔族にも内密のことらしい。ミューズがその理由を聞きたがったが、メセルリュースは曖昧に笑ってごまかすだけだった。
「ミューズ。あなたが自分の策を他の二人に言わないのと同じ事ですわ」
こう言われては、さしものミューズも引き下がるほか無かったのである。
神々と魔王達に一通り挨拶を終え、三人は黎明界を離れることにした。今日はとにかく忙しいのだ、次は竜族への挨拶、そして、現界で人間達と祭りを楽しまなければならない。
「私達はそろそろ竜王様方に挨拶をしなければなりませんので、これにて失礼いたします」
ミューズがそう言って御辞儀をすると、メセルリュースが口を開いた。
「そんなに急ぐこともないでしょう? ゆっくりなさったら?
それに、今行っても竜宮殿には四竜王陛下も十二神将の方々もいらっしゃらないわよ」
「それはどういうことでしょう?」
シリスが尋ねると、ファレルシーダが答える。
「竜王陛下は用事があるとか言われて、出かけておられます。
十二神将の方々も、それぞれの竜王についている様です・・・・詳しいことは私達にもわかりませんが」
「そうですか・・・・」
シリスが呟くと、レグラフィスが意地の悪い笑顔を浮かべて補足する。
「・・・・一部の神将は、彼の所に押しかけると言っていたな。
彼が、倒れるまで酒盛りしてやると息巻いていたようだぞ」
「ははは・・・・」
「なるほどねえ・・・・」
それを聞いて、メイルが苦笑しミューズも笑いながら頷く。
”彼”とは言うまでもなく竜一のことである。
昔は彼の元に、ちょくちょく竜族が訪れては馬鹿騒ぎをしたものだ。どうやら、今回も竜一と酒盛りしたがっている者がいるらしい。
「余り面白がってばかりもいられませんわ。
二人とも忘れたのですか? 今の御主人様は・・・・」
シリスがそこまで言うと流石にメイルも気がついた。あっと声を上げる。
「・・・・まずい!」
「今のマスターは下戸だったわ!!」
メイルの声にミューズの悲鳴が重なった。
竜一はあらゆる薬物を中和する特異体質である、そのためにいくら飲んでも酔うことはない。しかし、飲める飲めないは、酔う酔わないとは別問題だ。
飲める飲めないは純粋に好みの問題になる。酒の味が好きか嫌いかで、飲めるかどうかが決まる。
そして、今の彼はアルコールが苦手なのだ。
何しろ、匂いを嗅ぐだけで気分が悪くなると言うのだから、彼の酒嫌いもそうとうのものである。
彼女達の悲鳴と苦悩を見た神と魔王はその様子に不思議そうな顔をした。
「一体どうした?」
バラスレフィスが疑問を口にすると、ミューズが、苦笑しているのか、苦悩しているのか、何とも表現しがたい表情で答える。
「今のマスターは”下戸”なのよ・・・・」
「げこ?」
訝しげな表情でミューズを見つめるバラスレフィス。
「向こうの世界で言う酒を飲めない人間、”ディヴ・フェール”の事よ」
『嘘お!?』
ミューズの答えに、その場に居合わせた者達の驚愕の悲鳴が見事にハモッた。
感情を持たないはずのファベリアスルの声までも。
「あ・・・・あの、最強の”ラウ・フェール”だった、マスタードラゴンが?」
「飲み勝負で、あの紅竜王陛下をも打ち破った絶対無敵の”ラウ・フェール”が?」
「・・・・悪い冗談やめてよね。いくら転生したからって、そんな馬鹿なこと有るわけ無いじゃない!」
「・・・・とても、信じられません・・・・本当なのですか?」
それぞれ、口々に好きなことを言うが、そのどれもが、”信じられない、あり得ない”である。
その気持ちは彼女達にもよおーーく分かる。
初めて竜一が下戸であることを知ったとき、彼女達も恐慌状態に陥った位なのだ。
ちなみに、”フェール”とは、この世界の酒の神の名前であるが、神と言うよりは精霊に近い存在だ。
”ラウ・フェール”とはフェール神に愛された者、あるいは、フェール神を愛する者。すなわち、酒豪の意味を表す言葉である。それも並みの酒豪ではなく、酒豪の中の酒豪のことを示す敬称である。
逆に”ディヴ・フェール”とはフェール神を恐れる者、あるいは避ける者と言う意味で下戸を意味する。
上記の二つは一般的に”ラウール”と”ディフール”と略されることが多い。
”ラウ・フェール”、”ディヴ・フェール”と正式に呼ばれるのは特別なことなのである。
最強のラウ・フェールと言われたほどの男だった彼が、ディヴ・フェールになったというのは神々や魔王達にとっても驚愕の事態であった。
転生する事によって、性格も趣向も変わる事自体はそれほど珍しいことではない、それどころか、極当たり前のことに過ぎない。
その意味では別に驚くことではないはずなのだ。
現実に、”神崎竜一”の前世”ディル・フェライン”は比類無き酒豪、絶対無敵の”ラウ・フェール”だったが、さらにその前世は、酒を多少たしなむという程度で酒豪と言うほどではなかった。
それを考えれば、それほどおかしなことでもないはずなのだが、”ディル・フェライン”の酒豪ぶりはとんでもない代物であり、そのとんでもない酒豪が下戸になったと言うのは神々や魔王を恐慌状態に追い込むほどに強烈な事実であったのだ。
だが、それはまだかわいい方だとメイルは思っている。
もう一つの”恐怖症”など、初めて聞いたとき、メイルは思わず失望のあまり卒倒しそうになった位なのだから。
それを今言ったところでなんの意味もないことだが・・・・。
暗い思いに沈んでいたメイルはミューズの呟きに我に返った。
「まずいわね・・・・今のマスターに酒は禁物なのに・・・・」
「しかし、十二神将の方々の楽しみに水を差すのも・・・・」
ミューズの苦い呟きに苦悩に満ちたメイルの声が重なる。
(・・・・ひょっとして、マスターがこの世界に来たくなかったのは、このことが最大の原因なんじゃ・・・・)
一瞬、本気でそう思ったミューズである。
「どうします? 御主人様の元に戻りますか?」
「そうしたいのは山々だけれど・・・・もうすぐ祭りが始まってしまうし・・・・」
「まずいな・・・・」
苦い顔で唸る三人。
祭りの初日。午前八時にそれぞれを崇める大神殿に顔を出し、自分達がこの祭りの間、現界にとどまっていることを全ての信者、人間達に宣言するのが彼女達の日課である。今から竜一の元に戻ってはとうてい時間に間に合わない。
時間を操作するというのも余り得策ではない。この世界は向こうの世界よりも遥かに強い力に満ちている。不用意に世界のあり方に干渉するのは余り利口な手ではない。何より、今自分の手の内をここでさらすのは得策ではない。
特にヤフェイにはミューズが得た新しい力を知られるわけには行かなかったのだ。
「とはいえ、影を使うのは・・・・あまり得策ではないし・・・・」
さしもの策士ミューズにも良い策が思いつかない。
竜王十二神将が竜一の元にいるのならば、影をその元に遣わすのは非礼に当たる。あまり好ましいことではない。
それに、十二神将が竜一の都合にお構いなしに強制的に酒宴に突入しているとしたら、影では対処できない。
所詮、影に本体ほどの力はないのだ。十二神将は、ミューズやメイルが本気にならなければならないほどの強者ぞろいである。
乱暴な酒宴を止めるために、実力行使をしなければならないとしたら、本人が行かなければお話にならないのだ。
「いっそのこと、挨拶の方に影を送るというのはどうだ?」
「そうね・・・・そうしようか」
この世界の人間など、竜一の爪の垢ほどの価値もない、彼等との約束などミューズ達にとっては紙切れよりも軽いのだ。今は、竜一のほうが大事である。
しかし、そう結論つけようとしたミューズにシリスが苦い口調で忠告する。
「そのようなことをして、この世界の人間の信頼を裏切ってよいのですか?」
「別に良いじゃない? ほっといても」
さらりと言いのけるミューズにシリスは渋い顔をした。
「・・・・策士ミューズの言葉とも思えませんわね・・・・
例えあなたがどう思っていようと、人間達はわたくし達を信仰し、その見返りを期待しているものです。
人間という生き物はそういう存在。そして、その証を欲っしもします。
この祭りはいわばその証をたてる物です。その信頼関係が失われれば、人間達が再び見返りを期待してヤフェイへの信仰に走ることもあり得ます」
「人間に私の影を見抜ける訳、無いと思うけど・・・・。
・・・・ヤフェイがつけ込む可能性はあるか・・・・」
自分の術を見抜くような人間がいるとは思えないが、万が一という事もある。
それに、ヤフェイが何らかの手を打ってくるかも知れない。奴は力こそ小さいが姑息な手段は得意なのだ。
そして、その万が一があったとき、人間達はどう動くだろうか?
ここぞとばかり、ヤフェイの信徒達が煽るかも知れない。
ヤフェイの勢力が再興するのはミューズの望むことではない。だが、再興したならその時には改めて叩き潰すと言うのも悪くない選択だ。
どうすべきか悩んだが、メイルの言葉で意を決する。
「盟主なら大丈夫だろう。
十二神将の方々が盟主に危害を加える事は無いはずだ。
酒を飲み過ぎても他の人間のように身体に悪影響が有るわけが無い。
それに・・・・」
全ての化学物質を中和する特異体質を持つ竜一にとって酒が飲めないと言うのは、気分の問題にすぎないのだ。
そして、さらにメイルは続けた。
「それに、この機会に酒に強くなってもらうのもいいだろう?
あたいだって、たまには盟主と飲み明かしたいからなあ・・・・」
竜一に忠誠心厚いメイルだが、主人に危険がない以上それほど心配はしていなかった。
そして、そのメイルの言葉が決定打になった。ミューズ自身竜一と酒を飲み交わしたいと思っていたのである。
「命や健康面に不安はないしね・・・・荒治療をすると思えば問題はないか・・・・」
メイルの願望にミューズもあっさりと同意した。
とても主人に仕える使い魔の台詞とは思えない。能力のみならず、こういったところも彼女達が使い魔としては規格はずれであることの証明であった。
「大丈夫ですか? 十二神将の方々は底なしの所がありますから・・・・
逆効果にならなければよいのですが・・・・」
シリスが不安げな口調でそう言うと、ミューズも渋い顔になる。
「・・・・どちらにしても、マスターの元に帰る時間はないから、心配しても仕方がないわよ。
うまく行くことを祈りましょう」
ミューズの言葉にメイルも頷く。
最強の戦闘力を持つ闘神と、最大の魔力を誇る雷神といえど、こればかりはどうしようもなかった。ただ、誰に祈るのかと聞かれたら、彼女達自身答えることは出来なかったに違いない。
かくして、竜一はあっさりと彼女に見捨てられてしまったのである。
情けないことおびただしい。が、メイルとミューズのこの目論見が、後々、とんでもない事態を招くことになろうとは彼女達には想像もできなかったのである。
3
「それでは、私達はこれで・・・・」
ミューズがそう挨拶をすると、メセルリュースは少し厳しい目をミューズに向け口を開いた。
「ミューズ・・・・まさかと思いますが・・・・この世界の人間達を抹殺する気ではないでしょうね?」
「まさか・・・・」
小さく笑うミューズ。しかし、その笑いは少々堅かった。
「その気は、今の所はありません。今の所は、ですけれどね・・・・」
自分の主人を最優先に考えるミューズに釘を差すことをメセルリュースは忘れなかった。彼女は危険過ぎる策謀をその胸に秘めていることがあるのだ。
メセルリュースは”謀略の魔女”ミューズの性格を良く知っていた。
既に、マスタードラゴンが異世界に転生した以上、この世界の”人間”に遠慮をする必要はミューズには無いのだから・・・・
そして三人は神々と魔王達に挨拶を終え、黎明界を後にした。
さて、竜一の守護女神達が神々や魔王達に挨拶をしていた頃・・・・
暇を持て余しまくってぽーっとしていた竜一の元に客人がやってきた。
「おおおい! いるんだろう? 顔を見せろ!」
「私達に挨拶しないとは、つれないんじゃないのよお!」
「こらーーー! 開けろーーー! 酒盛りしようぜえ!!」
いくつもの声が社の玄関で上がった。
その声を聞いて、竜一は一瞬のうちに己の気配を完璧に消し去った。
格闘術を学んだおかげでその手の事にはなれていたが、今回は竜一自身会心の出来と思える程のものだった。その気配を感知することは何者にも至難の業であろう。
その声が誰を呼んでいるか竜一はよおぉぉく分かってはいる。
声の主もものすごく良く知ってはいる。かつては極めて親しい、気心の知れた連中だった。しかし、今の自分にとっては最強最悪の相手であろう。
何しろ自分は罪人なのだ。彼等に会うことなど許されるはずはないのだ。
いや、この場合罪がどうのこうのと言う問題ではない。
そんなことは関係なく、とにかく、何がなんでも言語道断に、絶対に会いたくない存在であった。
・・・・少なくとも今は。
息を殺して潜んでいると、しびれを切らしたのか怒鳴り声が聞こえる。
「えええい! 居留守をつかってんじゃない!」
「いるのは分かっているのよ! 顔を見せなさい!!」
「こらーー! あたい等とは酒飲めねーてのかああ!! ふざけてんじゃねえぞ!!
出てこおぉい!!」
しかし、今顔を会わせることは竜一にとって身の破滅を意味する。
死んだ振りを決め込んだ。
「・・・・そーか、そおかあ、そお言う態度をとるのか。
それならこっちにも考えが有るぞ!」
その声が聞こえると同時に、玄関前にあった彼等の気配が消えた。そして、次の瞬間には・・・・
「鬼さん見ーーっけ」
完璧なまでに気配を消し、死んだふりをしていた竜一の目の前に彼等は居たのである・・・・
竜一の前に現れたのは、青竜十二神将、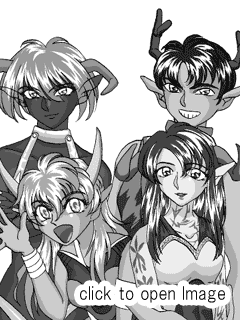
竜一の前に現れたのは、昔からなじみの者達である。機会がある事に彼等は顔を見せ、竜一と宴会をしていたものだ。
この面子に黒竜十二神将、
「久しぶりですね」
「カイ・サラム、元気だった?」
「そりゃ、ずっと前の名前だろ、確か今は、ディル・フェラインだよな」
「馬鹿! それも前世の名前!!」
「あーーも、面倒くさい!! マスタードラゴンで良いでしょう!!」
竜一の前で、人型になった竜族達は勝手に結論づけようとしている。あわてて、それに制止をかけた。
「待って下さい、私の名前は”神崎竜一”です。
マスタードラゴンではありません」
竜一の抗弁に竜達は苦笑を漏らした。
「何とも・・・・意味深げな名前だなあ・・・・」
「ほんとね・・・・名はその本質を表すと言うけれど・・・・」
「そうですね・・・・あなたのご両親は自分の息子の行く末を知っているのでしょうか?」
「・・・・そう思います?」
竜一の苦笑に彼等は大きく頷いた。
「私の世界の言葉の意味を良くご存じですね」
苦い表情で竜一が問いかけると彼等は胸を張って答えた。
「我らを甘く見ないでほしいな」
「そうよ。私達は”邪神”共と戦って、あらゆる次元を旅しているのだから、その程度のことは承知しているわ」
「”かみさきりゅういち”と言う音がどんな意味を含んでいるのか、私達も承知しています」
「かないませんね・・・・皆様には・・・・」
竜一は彼に似つかわしくない丁寧な口調で彼等に対した。
竜一の元を訪れた竜族。
彼等は最高種族竜族を束ねる長”四大竜王”の直属の部下”竜王十二神将”の面々であり、総称”四十八貴竜”と呼ばれる者達であった。
四十八貴竜とは、竜王に仕える十二神将の総数、四十八名によって構成されている竜族の最高位の存在である。
この場合、四十八貴竜に四名の竜王は含まれない。竜王はさらに特別な存在であるからだ。
竜王を別格としても、四十八貴竜も十分にとんでもない存在である。その力は竜王に及ばぬとはいえ、最高神でさえ彼等の前では無力に等しいのだ。
人間など言うに及ばず、神々や魔王達でさえ四十八貴竜に会える者など限られている。邪神から世界を守るために戦う時などは顔を会わせる事もあるが、私的な事情で彼等と付き合える者など殆ど居ない。
祭り好きの竜族であるから、正体を隠して人間達と馬鹿騒ぎをすることくらいなら有るが、正体を自ら明かすなど、人間に対してはまずあり得ない事だ。
まして、正体を知られた相手と酒を酌み交わして馬鹿騒ぎするなど、奇跡に等しい。
それほどの存在であるから、自然と竜一の口調も丁重になり、態度もやや堅苦しいものとなるのだが、竜族はそれをよしとはしない。
彼等は竜一のことを対等の存在と認めているのだ。
認め、受け入れた相手に他人行儀にされるのは竜族にとっては、あまり心楽しいことではないのである。礼儀正しさは、時として互いの間を仕切る壁となることもあるのだ。
竜族にとって竜一の態度は未だに自分達に打ち解けない者の自己防衛、よそよそしい態度にしか見えないのである。
たとえ竜一が心底、彼等に対する敬意を表現しているつもりでも。
「何時までも堅苦しいこと言ってないで、楽しみましょ!」
そう言った炎那の手には酒の瓶が握られていた。
「いや、しかし・・・・」
竜一がそう言うと、竜一を誘った女性がすねたように、彼にすりよる。
「なによ! このあたしの酌を断るって言うの!!
紅竜十二神将第四位、炎那様のお酌じゃ飲め無いって言うの!!」
恐ろしい剣幕で迫ってくる彼女の迫力に押されながらも、竜一は何とか声を絞り出して答える。
「違いますよ! 俺、下戸なんです!!」
「なに? 下戸?
えーーと、下戸って、確か向こうの世界ではデヴ・フェールのことだったわよね・・・・
なにいいい! デヴ・フェールだとおおお! 嘘をつくなああ!!」
「わああ! 本当なんですう!! お願いですぅ勘弁して下さいいぃ!!」
炎那の剣幕に、竜一はとうとう泣いて謝りだしたのだった・・・・
4
さて、神々への挨拶周りを終えて、現界に三妖神が戻って来た頃、その僅かな時間の間にミューズの社の中庭には、中身を飲み干された酒瓶が林立し、空になった酒樽が巨大な山を形作っていた。
既に宴会はたけなわのようである。
「えーーーん、勘弁して下さいよおぉ・・・・」
半泣き状態で悲鳴を上げているのは、ビキニ程度の面積しかない薄手の衣装を着た小麦色の肌の美女に抱きしめられた竜一だった。
美女は右手に、直径4
並の人間なら、数十分で急性アルコール中毒と化し、あの世への超特急に乗り込むこと疑いない状況で、竜一は半べそ状態だった。
何とか逃げ出そうともがいてはいるのだが、マスタードラゴンとしての力を誇っていたかつての彼ならばともかく、今の、ただの人間の竜一に、紅竜十二神将第四位の実力を誇る炎那の腕力から逃れる術など有ろうはずがない。
今の竜一の力は人間としてはほとんど限界に近い力を持っている。だが、それは所詮人間のレベル、それも向こうの世界のレベルに過ぎない。創造神さえ越える力を持つ十二神将の力の前では、完全無欠に無力である。
じたばたもがくが、炎那に押さえられた顔はぴくりとも動かない。
彼女に押さえられて自力で逃げられるのは、十二神将や竜王を除けば、神族・魔族数あれど最強の闘神と讃えられるメイルくらいであろう。
いくら暴れようがもがこうが、当然のごとく状況はいっこうに改善されないのであった。
「やめて下さいいい!!」
「却下!
我らが王、紅竜王陛下に飲み比べで勝ったあんたが、この程度飲めないなんて、あたしは絶対に認めないからね!!」
「だーかーらー、それは前世のことでしょう! もう、三千年以上も前の事で、今の俺とは無関係・・・・」
「聞こえなーーい!!」
竜一の涙ながらの抗議をまさしく一蹴してのけて、炎那はさらに酒樽を傾ける。
「何もそこまでしなくとも・・・・そろそろ、勘弁してあげてはどうですか?」
「・・・・泣いてるみたいだぞ・・・・おい・・・・」
他の者達は、炎那の剣幕に気圧され、遠巻きに見守るだけである。
「なーーにいってんのよ、宴会はこれからなのよ!!
この程度で音を上げるんじゃ無いわよ」
怒ったような口調でそう言う。その彼女を見て、おそるおそる白竜王十二神将第七位、春嵐はぽつりと問いかける。
「ひょっとして・・・・あなた酔ってるのではなくて?」
「なーーに言ってんろよ。
たかがぁ、葡萄酒2200
「酔ってる、酔ってる・・・・」
炎那の酒気を帯びた反撃に、苦笑しつつ冷静に突っ込みを入れる面々。
「あらしはぁ、酔ってなんかぁ、いらいぞお!!」
つっこまれた彼女はさらに反撃を試みるが、その呂律はやや怪しく、形勢は圧倒的に不利なようである。
酒飲みの”酔ってない”の台詞が信憑性に欠けるのは、竜族と言えど変わらないらしい。
ただ、他の者達も突っ込みこそすれ止めようとする者はいなかった。
皆、酒を飲むのが楽しいのだ。竜一もいずれ酒の楽しみを思い出すだろう。そんな軽い気持ちだったのも確かだ。
だが、何よりも炎那が集まったメンバーの中で最強の実力を持っていた為に逆らい難かったのが最大の理由だろう。
かくて、拷問のごとき狂乱の酒宴が永遠と続くのだった・・・・
1 / 2 / < 3 > / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14