[ 三妖神物語 第四話 女神帰還 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第四章 出会い。
1
神殿の中庭にある大木の脇に静かに降り立つ。
この辺り一帯でもっとも長い年月を生きてきた古老、カラの大木の精霊に挨拶を交わす。この大木がこの近辺の精霊を束ねる長老であり、シリスをこの神殿に呼び寄せた張本人であった。
「噂に違わずお美しいですな・・・・シリス殿」
古木が言葉を話す。普通の人間には聞こえぬ音、理解できぬ声で。
そして、シリスも頭を下げて挨拶する。
「初めまして、薬神の役目を与えられた魔神シリスと申します。
今後とも宜しくお願いいたします」
シリスの挨拶にカラの木霊は苦笑した。
「全く、噂通りですな。
まだ、”薬神”と名乗るには抵抗がありますかな?」
「わたくしは魔神。それ以外のものにはなり得ぬ定めなのです」
寂しげなほほえみを浮かべるシリスに木霊は嘆息した。
「まだ、そのこだわりを捨てられないようですな・・・・」
その言葉にシリスは答えず、用件を切り出した。
「所で、この神殿にわたくしの力を必要とする病人が居ると聞いて参りました」
他の精霊達から聞いても良いのだが、自分を呼びだした存在に話を聞くのは当然のことである。
木霊は、話をはぐらかされたのを残念に思ったが、不快ではなかった。
彼女なら全て許してしまえる。そんな不思議な力をシリスは持っているのかも知れない。
「そうでしたな。どうも、直ぐに世間話をしてしまうのが私の悪い癖でして。
実は、半月ほど前にこの神殿に”ドヴァ熱症”に感染した親子が来たのです。
発病していたのは母親の方ですが、これが、処置不能の末期症状だと言うことです」
「ドヴァ熱症?
あれはそれほど治療の難しい病ではないはずですが・・・・」
それを聞いてシリスは訝しげな表情を作ったが、直ぐに納得した。
「その親子はヤフェイの信者だったのですね?」
ドヴァ熱は安静にして薬を飲んでいればそれほど危険な病ではない。
例え薬が無くとも、症状の軽いうちに十分な栄養と休養を与えれば、時間はかかるが治すことが出来るような病気なのだ。
正しい知識さえあれば簡単に直せる病気を末期状態にまで拗らせるには、それこそ、ヤフェイの信者のように医学無知の上に狂信的な者にしかできない。
「そうです、それで女神の降臨を願ったわけです」
何故、木霊が女神の降臨を望んだのか? その理由は極めて簡単なことだ。少年と仲のいい精霊が特別に頼んだのである。
「そうですか・・・・分かりました。ここへ来たのはその患者を癒すためですものね。
会ってみましょう」
そして、女神は神殿へと歩き出した。
2
シリスは目立つことを好まない。
己の気配と姿を消して、神殿へと入り込んだ彼女に誰一人として気づかなかった。
神殿には腕利きの神官達がいろいろな結界や術をかけてある。
泥棒などの不信人物の排除の為の防御呪文や捕縛結界。子供や素人が劇薬などに触れぬようにするための予防呪文。この神殿に悪意を持った者を阻むための結界等である。
特に、泥棒や神殿に対して敵意を持つ者は姿を隠してくる者もいる、そう言った者達の術を破る結界も当然しかれているし、彼女に陶酔している精霊や妖魔達も進んで各地の神殿の守護に力を貸している。
しかし、それらの術もシリスには通じない。
何しろ、女神の術である。人や精霊が使う物とはレベルが根本から違いすぎる。
それに、なんと言ってもシリスはこの神殿が崇める女神本人なのだ。この神殿を守るために紡がれた術や守護精霊達が、彼女の術を邪魔する訳が無い。
女神は人や精霊に気づかれることなく、静かに歩みを進める。
やがて、問題の人物の眠る病室に到着した。
神官達が適切な処置を施しているのは彼女の目には明らかだった。にもかかわらずその患者の容態は芳しくない。
一目見て、それはかなり危険な様態だった。まさしく、薬の力でかろうじて命をとどめているような極めて危うい状況。
”ドヴァ熱症”でこれほど症状を悪化させた患者を診るのはシリス自身、何百年、いや、何千年ぶりだろう? 驚くより先に感心してしまうほどのものだ。
だが、感心してばかりもいられない。
このまま放っておくのは余りにも哀れだ。周りを見ると、彼女の看護人の神官とおぼしき青年が看病疲れからか、こっくりこっくりと居眠りしていた。それを確認し、他に人間がいないのを確認すると、周囲の力と自分の力を練り上げて”生気”を作り、それを静かに彼女の心臓の上に集める。
十分に溜まった”生気”をそのまま静かに彼女の心臓にそそぎ込む。
膨大な魔力と生命力を持つ女神だからこそ出来る術だ。
人間の魔力では生命力を作り出すことは出来ない。
”魔力”を一度”精霊力”に変換して”精気”として人に与えることは出来ても、”生気”すなわち”命”そのものにすることは不可能なのである。
”精気”は”活力”とも呼ばれる力である。ある程度体力が残っている時には人間の肉体を活性化させることが出来るが、彼女のように極限まで衰弱した者に”精気”を無理に与えると、その力に弱った肉体が耐えられずに逆効果になることが多い。
”命の力”を与える術。それはまさしく、女神だからこそ可能な高度な術なのである。
もしも、この場にミューズがいたら、人間ごときにそこまですることはないと怒ったかも知れない。
そこまでする義理はないし、なにより、人間がつけあがる! と怒鳴ったかも知れない。だが、シリス自身はもともと、彼女を癒すためにここに立ち寄ったのだ。例えミューズが文句を言っても彼女を癒しただろう。
シリスの力で作られた”生気”は柔らかな光の帯となって彼女の心臓の辺りに吸い込まれるように消えていく。
力のある神官なら、その力の流れを見ることが出来ただろう。もしも誰かがいたら、シリスの存在に気が付いたかも知れない。
幸い、シリスが力を注ぎ終わるまで、誰一人としてこの病室には尋ねてこなかった。看病役の青年神官も目覚める気配はない。
部屋は充分に日の光が入り、暖かく明るいが、そのままにしておくのも気の毒なので、患者にかけられている毛布を直すと、部屋の中にあった予備の毛布を眠っている神官にかけてやり、シリスはその部屋を出ていった。
しばらくして、目を覚ました神官は自分にかけられた毛布に気づいて首を傾げ、自分が寝入っていたことに気が付くと飛び起きて患者の様子を確認し・・・・慌てて、他の神官を呼びに部屋から飛び出した。
彼女の顔色が良くなったことに驚いて上司に報告に向かったのだ。
一目見てそうと分かるほどに、彼女の顔色は健康的な輝きを取り戻していたのである。
3
シリスは彼女を癒し、そのまま神殿から出た。
一応、この神殿の責任者に挨拶くらいはしていこうかと思ったのだが、この神殿に来た理由が病人を癒すためと言う事は秘密にしておくべきだとシリスは思っていた。
彼女自身、余り目立ちたくはなかったし、このことがミューズに知られたら後々やっかいなことになるかも知れなかった。
さらには、この事で人間が自分に甘え過ぎるようになっては困るという懸念もあった。
だが、その理由を隠すと、この平凡な神殿に来た理由が無くなってしまう。
気まぐれと言ったところでだれも信じないだろうし、何より、死ぬ寸前の重病人の様態が持ち直していることは明らかであり、すぐにばれてしまうだろう。
従って、この神殿には始めから自分が来ていないことにした方が好ましい。
早々に他の神殿に出向いて、そこに顔見せすることで自分の勤めを果たそうと考えていた。
その足で他の神殿に向かおうとして・・・・ふと足を止め、神殿の裏庭に向かう。
子供達の声が聞こえたので、好奇心を刺激された彼女は少し子供達の様子を覗いて行こうと思ったのだ。
シリスは人間の子供にやたらと甘い性格をしていた。もっとも、ミューズがそのことを聞いたら、シリスは人間に甘すぎるほど甘い性格であり、子供に対してはより甘くなるだけだと辛辣に言うだろうが・・・・
始めは様子を見てすぐに去るつもりだったのだが、様子が少しおかしい。よくよく見てみれば一人の子供を数人の子供が虐めているようだ。
彼女達三妖神はこういう虐めを特に嫌っていた。
赤の他人。それも子供同士の事に、女神が口を挟むのはどうかとも一瞬思わないではないが、一対一の正々堂々とした喧嘩ならいざ知らず、一対多数の一方的な虐めでは見ぬふりも出来ない。
人目の付かないところで術を解くと、静かに争っている子供達に近づいた。
この時、シリスは目立たないように瞳の色を碧に変えていた。
髪の毛の銀色はそれほど物珍しいものではないが、銀の瞳というのは人間は勿論、精霊でさえ、まれにしか見られない極めて珍しい色なのだ。
瞳の色を変えないで人前に出ることは、それだけで自分の正体を大声で公言しているようなものである。
さらに、服装も神官の礼服に変える。
彼女の女神としての正装も見る者が見れば、一発で正体を見抜かれるほど特徴的な物なのだ。だからこそ衣装を変えた訳なのだが、この時シリスは、一寸したミスをしてしまっていた。
そして、困ったことに、彼女自身はその事に最後まで気が付かなかったのである。
「あなた達、どのような理由かは知りませんが、一人を大勢で虐めるのは感心出来ることではありませんよ。いい加減におやめなさい」
子供達に近づいてシリスがそう言うと、子供達は一瞬、シリスの美貌に見とれてぽかんとしていたが、リーダーと思われる少し年長の少年が文句を言った。
「そんなの、姉ちゃんには関係ないだろう? 引っ込んでろよ!」
「そうだ、そうだ! これは僕達の問題だ! 大人は引っ込んでてよ!」
「子どもの喧嘩に大人が口を出すのはいけないことなんだぞ!」
なかなか口の達者な子供達の言葉に、シリスは半分感心しながらも少しきつい口調で言葉を続ける。
「正々堂々、一対一の男の喧嘩ならわたくしも口を挟むつもりはありません。
しかし、数を頼んでの弱い者虐めならば、それを見過ごす事は出来ません。
自分の年齢をどうこう言う前に、たった一人を多数で虐めるという卑怯な行動をすること自体、人として恥ずべき事だと知りなさい!!」
一括して、小生意気ないじめっ子達を諌める。
人に甘いと言われるシリスであるが、弱い者いじめなど、理不尽な行為に対しては断固として厳しい態度をとるのである。
相手が子供であろうと、いや、子供であればこそ、人としての分別をたたき込むべきだと思っているのだろう。その言葉は極めて厳しく、重いものだった。
厳しい言葉に生意気な子供達も毒気を抜かれてしゅんとなる。
「・・・・だけど・・・・こいつは、ヤフェイの信者なんだぜ・・・・そんな奴がシリス様の信者になるなんて・・・・シリス様だって迷惑だよ・・・・」
ぶつぶつと年長の少年が文句を呟いた。
「そうなのですか?」
優しい光を秘めたその瞳を向けて、虐められていた少年に尋ねるシリス。
少年はその服装から美貌の女性神官らしい彼女の笑顔に頬を赤く染めてながら、きっぱりと言いきった。
「ヤフェイの信者だったのは確かだけど、俺はもうヤフェイを捨てたんだ。
俺は、これからはシリス神に仕えることを心に決めた。
俺はもう、シリス神の信者だ!」
強い決意を込めてそう言い切った少年。その言葉にシリスは優しく微笑む。
その微笑みにますます少年は顔を赤くしてうつむいた。
シリスはいじめっ子達に視線を移して言葉を続けた。
「過去はどうあれ、この子は自分の生きる道を自分で決めました。
これほど真剣にシリス・・・・様に仕えることを望んでいるのなら、かの女神も喜んで彼を迎えるでしょう」
自分自身の名前に”様”と敬称を付けるのにとてつもない抵抗を感じて一瞬口ごもる、が、神官の姿をしている自分が仕える女神を呼び捨てにするのは不自然だったので、無理矢理、シリスは言葉を続けた。
「むしろ、かの女神ならば、これほど真剣に自分に仕えようと努力している彼に理不尽な暴力を働くあなた達をこそ嫌われるでしょう」
シリス神に嫌われる! この一言はシリス神に仕える者にとって死刑宣告にも等しい。
「・・・・分かったよ。
シリス様に嫌われるのはイヤだからな・・・・悪かった」
年長の少年がそう頭を下げると、他の子供達も少年に謝り、そのまま、宿舎の方へ走っていった。
「・・・・有り難う・・・・
でも・・・・本当にシリス神は俺みたいなヤフェイの信者だった人間でも、受け入れてくれるのかな?」
力のない疲れた口調で、少年は目の前の美しい女性神官に尋ねた。
ああ、この子はずっと不安だったのだ。
シリスは少年がずっと心の中に抱いていた物を悟った。
いくら自分自身に言い聞かせても、本当に女神に認められるだろうか自信がなかった。いや、不安だったのだろう。
そして、自分が他に行く場所がないと言うことも少年を追いつめていたに違いない。
ヤフェイの信者が、その信仰を捨てると言うことがどれほど勇気のいることか、シリスは良く知っていた。
ヤフェイへの信仰を捨てても、他の神を信仰することは彼等にとって容易なことではない。
他の神を異常なほどに排斥している宗教である、他の神々の信者達も彼等によい感情を持っている訳が無い。
新しく他の神を信仰しようとしても、その神の信者がそれをなかなか受け入れようとはしないのだ。そのために、ヤフェイの信者は他の神をなかなか信仰できない。
それが、ヤフェイにとって好都合だということは、他の神々の信徒達も理解してはいる。だが、どうしても感情が納得してくれないのだ。
そのため、結果としてヤフェイの信者は他の宗教に移籍しにくく、その数が一定以上減らない原因にもなっていた。
シリスはふと、この少年が他人に思えなくなった。
この神殿の中で浮いた、異質な存在の彼。それは、かつての彼女の主人の姿と同じものだった。
かつてあまりに巨大な力を持つが故に恐れられ、人の世界から排斥された自分の主人に・・・・
そしてそれは、彼女自身の姿でもあった。
「少し、お話しをしませんか?」
シリスは少年を連れて、木陰に向かって歩き出した。
4
少年を木陰に案内したシリスは、草の生えた大地に直接腰を下ろした。
「あの・・・・その礼服汚れますよ・・・・」
少年の目にはシリスの礼服が美しく見えた。
すさまじい美貌を持つ女性が着ると服までもが必要以上に美しく見える物らしい。その服が汚れることをついつい心配してしまったのだ。
「大丈夫ですよ。ここの草に腰を下ろしても、それほど汚れることはありませんわ。
それに、わたくしは、こういうふうに座った方が落ちつくんです」
美しい笑顔を向けられた少年は顔を赤くしてシリスの横に勢いを付けて座った。
「余り乱暴に座ってはいけません。
草が驚いていますよ」
「あ・・・・ご、ご免なさい」
謝る少年の頭を優しくなでて、彼女は話を続けた。
「あなたは、自分がヤフェイの信者であった事を恥じているのですか?」
「うん・・・・今まで、あんな神を信仰していたなんて・・・・情けないよ・・・・
あいつは、俺のかあさんを殺しかけたんだ・・・・」
自分がヤフェイを疑い始めたのは精霊の存在を知り、彼等に手助けされたことがきっかけだったと少年は話した。
ヤフェイの教義では神とそれに従う天使以外、全てが忌むべき存在であると書かれていた。そして、村の人々も他の村の人間が精霊や聖獣と呼んでいるモノが邪悪な生物であると口をそろえて言っていた。
だが、精霊達は彼に色々な事を教えてくれた、そして、彼は神が精霊を排斥しているのは自分の教典が過ちだと言うことを知られないようにするためだったのではないか? と疑いを持ち始めていたのだ。
人の批判的能力こそがヤフェイにとって最大の敵である。
自分の教義を疑う存在。そして、その原因となりうる精霊や他の神々の知識は、全てヤフェイにとって”悪魔の”知識なのだ。
「本当にシリス神は、俺みたいな人間でも受け入れてくれるのかな?」
よほど心配なのだろうか、同じ言葉を繰り返す。
目の前にいる美しい神官に何度も確認しないと、自分自身でも納得出来ないのだろう。
不安な瞳で自分を見上げる少年にシリスは優しく頷いた。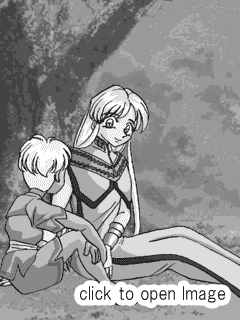
「ええ、大丈夫ですよ」
「でも・・・・」
なおも不安げな少年をシリスは何とか励ましてやりたかった。
自分がその女神本人だと言いたいのは山々だが、それではあまりにも安易すぎる。
少し悩んだが、シリスはある物語。とても古い物語を聞かせることにした。
「わたくしの知っているお話が有るのですが、聞いてみませんか?
とても古い物語ですから、つまらないかも知れませんが、それで良ければ・・・・」
「古い物語?」
「ええ、とても、とても古い物語です」
シリスの顔を見上げた少年は静かに頷いた。
どんな物語なのか興味もあったし、こんなきれいな女性ともう少し一緒にいたいと思ったのだ。
「うん、聞きたい。どんな物語ですか?」
少年の言葉にシリスは物語を語りだした。
美しい調べの様なその言葉が、静かに流れ始めた。
「昔々、あるところに一匹の魔獣が居りました・・・・」
1 / 2 / 3 / 4 / < 5 > / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14