[ 三妖神物語 第四話 女神帰還 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第九章 策謀
1
その日の勤めを終えてミューズは神界へと赴いた。
「ミューズです。メセルリュース様にお目通りを願いたい」
メセルリュースの聖域への入り口である門の前でそう言うと、その声に門が反応する。
メセルリュースの聖域を守るこの門そのものが門番であり案内役なのだ。
「ミューズ殿、今回はいかなるご用件でしょうか?」
門が柔らかい七色の光を放ちながら、性別不明の声で尋ねる。
「私の部下、二人の処遇についてご相談したい事があります」
すると、門の声とは違う優しげな声が流れ出した。
「おはいり下さい。メセルリュース様は本邸に居られます。
直接お送りいたしますので」
その声に呼応し扉が開き始める。
開いた扉の中からあふれでてくる光を気にもとめずにそのまま門の中へと歩を進める。
七色の光を放つ光球、メセルリュースに仕える光の精霊がミューズの前まで緩やかに漂ってくる。
ミューズが足を止めると光球は弾けて光の粒となり、彼女の身体を覆い尽くした。
空間を埋め尽くした光は、やがて薄れて消えて行く。
光が消えた後、その場にミューズの姿はなかった。
「何を企んでいるのかしら? ミューズ」
椅子に座り、テーブルを前にして笑顔でメセルリュースはミューズを迎えた。
淡い光沢を持つ光の具現体”ゼプロウェズ”で作られた椅子とテーブル。
テーブルの上には既に自分とミューズの分のお茶が用意されていた。
「企んでいるとは人聞きが悪いですね」
苦笑を返すが、メセルリュースは表情を変えなかった。
「あら? そうですか?」
白々とそう言うとミューズに茶を勧めた。
「それはそうと、つもる話もあるしお茶でもどうです?」
「ええ、いただくわ」
砕けた口調でそう言うと、メセルリュースの正面に座りカップを手に取る。
紅茶に近い香りを放つ液体。精気の一種で、液体のような状態で固定されているそれを飲むミューズを見つめながらメセルリュースはぼやく。
「竜一さんは、いえ、マスタードラゴン様は、この世界に戻ってくる気はあるのかしら・・・・」
メセルリュースはそれが気がかりだった。
既に彼がこの世界から去ってから三千年以上が過ぎているが、その間に彼はまだ一度しか転生していない。
したがって、罪の清算が終わっていないと竜一が考えていても仕方がないのだが、彼の言動を見ると、彼はこの世界に戻って来る気が無いのではないのか?
そう思わずにはいられなかった。
「まだ、マスターのことを諦めてなかったの?」
人の悪い笑みを浮かべるミューズ。
「諦めるなんて・・・・私は・・・・」
うつむいて顔を赤らめる。
「まあ・・・・分からないでもないけどね・・・・
でも実際、マスターはこの世界に対して罪の意識を持ちすぎているから・・・・」
ミューズの言葉にメセルリュースは悲しそうに呟く。
「彼に罪がないとは言えません。しかし、アレは不幸な事故でした。
本当に罪を償うなら、この世界を守ることこそが真の償いになると思うのですが・・・・」
「それも一つの考え方だけどね」
メセルリュースの呟きに相づちを打って、ミューズはカップを傾けた。
「とにかく、あの馬鹿を始末しないことにはどうしようもないわね」
冷たい憎悪を込めてはき捨てる。
ミューズが怒りをぶつけている相手は勿論ヤフェイである。一応は神であるヤフェイに対して、”あの馬鹿”だの”始末”だの、なかなか物騒な台詞を吐くがメセルリュースはそれを咎めなかった。
「ヤフェイは未だに自分の罪を認める気は無いようです。
そのうち、何とかしようとは思っているのですが・・・・」
そう言いつつミューズの表情をうかがう。
この”謀略の魔女”はきっと恐ろしい計画を立てているのに違いない。メセルリュースはそう確信していた。
相手が自分の表情をうかがっていることをミューズは承知していた。そして、力強く頷く。
「あの馬鹿には死んでもらうしかないんじゃない?
あのゲスに反省だの自重だのを期待する事自体間違いよ。
何しろ、人間の創造神なのだから」
突き放すようにはき捨てるミューズ。
人間は極めて正確にヤフェイの性癖を写している。その意味では人間はなかなか良くできた神の模造品だった。
人間は過ちを犯しても、直ぐにそれを忘れて同じ過ちを繰り返す。反省も後悔も一瞬のうちに消え去り長続きしない。
人間はそう作られていたのだ。永遠に過ちを続ける存在として。
いちいち反省していては現界を食い尽くし、支配することなど到底不可能なのだから。
そしてそれは、ヤフェイ自身の性格でもあった。
「それで、そろそろ本題に入っても良いかしら?」
空になったグラスの中に液体精気を継ぎ足しながらミューズは話を続ける。
「私が今回ここに来たのは、私の部下になっている
「ああ、あの双子の精霊ですね。
あの娘達がどうかしたのですか?」
小首を傾げたメセルリュースにミューズはにっこりと人の悪い笑みを浮かべて、答える。
「ま、百聞は一見に・・・・、あ、違ったわね、”己の瞳に写りし姿を見よ”よ。
爛華! 麗華!」
ミューズの声に答えて二人の人影、いや精影が現れる。
純白の髪と薄紫色の瞳を持ち、目鼻立ちから気配までもが全く同じ二人の美女。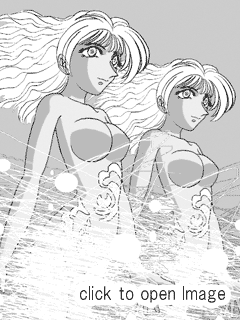
精霊には希有な存在。双子の精霊、
だが、今メセルリュースの前にいる彼女達は、精霊と言う言葉には当てはまらない存在となっていた。
「・・・・驚きましたね・・・・もう”聖霊”のレベルにまで達していたとは・・・・
いえ、これは、この力は聖霊以上・・・・」
「元々、筋は良かったけどね」
驚くメセルリュースにミューズが頷く。
「もう神のレベルにまで達していたのですか・・・・」
感心しきったメセルリュースの声。
精霊と聖霊は本質的に同じ存在である。
精霊の力が臨界点を超えてなお安定した時、その存在は聖霊と呼ばれるようになるのだ。
臨界点とは、精霊の器を越える力のことを指す。
基本的に精霊は臨界点を越えることは出来ない。
臨界点を越えたとき、精霊は己の力を制御しきれなくなり、力の暴走と秩序の破壊を招くことになる。それは精霊の存在自体の危機となる。
それ故に、力が不必要に強くなってしまった場合、力を分割し、分体を作ることにより力のレベルを落として安定を図るのだ。そのために海の水全てが一体のウェンディーヌや巨大な台風が丸ごと一体のシルフになることはない。
ところが、極希にその臨界点を越える力を持ちながら安定する存在が居る。
それが聖霊と呼ばれる存在だった。
精霊を遥かに凌ぐ力を持ち、その力は神に近い。
実際に聖霊の中からさらなる力を蓄え、新たなる神となったものも居た。
聖霊とは”限りなく神に近い”精霊の事なのだ。
ただし、聖霊の中でも神となれるものは双子だけである。
神とは光の属性を持つ存在である。だが、光があれば闇がある。それは鉄則。
それは真理。
新たなる神が生まれれば新たなる魔王が目覚める。
光と闇の新しい誕生、そのバランスを取るために、神となる聖霊は必ず双子でなくてはならない。
片方が神に片方が魔王に。そうして、世界のバランスは保たれる。
目の前にいる元精霊。麗華と爛華は既に神や魔王と言っても良いほどの力を持っていた。
二人の巨大な力を見てメセルリュースはミューズの考えを察した。流石にこの辺りは女神達の主である。
「・・・・この娘達を新たに神の座につけるつもりですか?」
「察しが早くて助かるわ」
ミューズの人の悪い笑みを見て、メセルリュースは彼女の辛辣な策謀の一部をかいま見た様な気がする。
雷神ミューズは彼女達を新しい”人間の”神にするつもりなのかも知れない。
ヤフェイの跡目を彼女達に継がせるつもりなのか?
雷神ミューズの策謀は奸智の極み。女神の長であるメセルリュースでさえ、彼女の真意の全てを探ることは至難の業だ。
だが、これだけは言える。
ミューズは、誰がなんと言おうとヤフェイを抹殺するつもりだと言うこと。
その決意の証。ミューズの心の中ではヤフェイ抹殺は既に決定した事項。いや、既成事実なのだろう。
こうなっては何を言っても無駄だ。彼女はすでに、ヤフェイを亡き者として新しい世界を構築することを計画しているに違いない。
そして、彼女の行動を阻止できるほどの力を持つものは神界にも魔界にも居ないのだ。恐ろしい事に。
彼女の絶対的な力には、もはや神々や魔族がどうあがいても対抗できるものではない。
彼女を力尽くで止められるのは四竜王と四十八貴竜の極一部、そして、闘神メイルだけなのだ。そして、竜族もメイルも彼女を止めることはないだろう。
メイルについて言えば説明するまでもない。ヤフェイの存在を苦々しく思っているのは彼女もミューズと同様だ。
竜族は神族や魔族のごたごたには基本的に不干渉なのだ。さらに言えばヤフェイは竜族にも心底嫌われている。
嫌いな相手と好きな相手。どちらに味方するかは自明の理である。
その竜族の行動を非難する者は殆どいないだろう。なにしろ、神族や魔族もヤフェイの味方をする者は絶無なのだから。
それ程までに、ヤフェイは徹底的に嫌われているのだ。
そうなれば、ミューズのその策謀を、既成事実を覆せるものはマスタードラゴンだけしかいない。
ヤフェイの被害者であり、彼女達の主であるマスタードラゴンだけがミューズを止められるのだ。だが、ミューズは自分の計画を決して彼に話すことはないだろう。
彼に止められることをミューズは最も恐れているのだから。
メセルリュースも、竜一――マスタードラゴン――にこの事を言う気はなかった。
今となってはメセルリュースも流石にヤフェイをかばう気にはなれないのだ。
可能な限り中立を保とうとする彼女ではあるが、ヤフェイは既に神々からも魔族からも人望(神望?)を失って久しい。彼を見捨てたところでそれを非難する神魔は誰一人居ないだろう。
ただ、一つだけ問題があった。
「ルシフェリラはどうするつもりなのです?」
ミューズの考えを確かめるために、メセルリュースは、あえて彼女の名を出した。
聖魔王ルシフェリラ。
人間の神ヤフェイの双子にして人の闇を司る魔王。
彼女が司る人の闇。それは安らぎの夜の闇。
人間の全ての悪徳の象徴とも言うべきヤフェイに相反するかのように、彼女は人間の数少ない美徳を象徴するかのような存在だった。
神であるヤフェイが
謙譲、慈愛、理性、良心、献身、誠意。愛情。
人の心の微かな善。それらの象徴とも言うべき存在。
皮肉な見方をする者は、「魔王が理性を司るが故、人の理性は光の中では儚く、闇の中では頼りない」と笑い飛ばす。
人間の間では魔王を邪悪と見る風潮が残っていた。それも、ヤフェイの残した悪しき習慣であった。
だが、彼女が人の微かな善の象徴であることは事実であり、それを疑う者はない。
彼女の善良さは神族や魔族の間でも評判である。彼女の”聖魔王”の称号に反対しているのは本人だけなのだ。その称号を認められるほどの彼女の善良さと誠実さは創造神ガルディエルをして、「何かの間違いでヤフェイの双子になったとしか思えない」と言わしめるほどである。
また、彼女のおかげでマスタードラゴンが何とかヤフェイの魔の手から逃れられていたと言うこともあった。
いかに絶大な力を持つマスタードラゴンと三妖神といえども、人の魂を扱う力を持つ人間の創造神たるヤフェイから完全に自由ではいられなかった。
マスタードラゴンと三妖神だけでは完全にヤフェイからの干渉をはねのけるのは難しい。人間の肉体を持っている間はとにかく、肉体を失い、魂だけの無防備な状態ではヤフェイの干渉から逃げきるのはかなりの難問だった。
人間の魔王たるルシフェリラの助力があったからこそ、マスタードラゴンはヤフェイからの魂の自立を勝ち取ることが出来たのだ。
それに対しては三妖神も深く感謝している。だからこそ、ヤフェイに対しては徹底的に冷徹なミューズもルシフェリラには敬意を払う。
そして、神と魔王は対の存在。神たるヤフェイが滅びれば魔王たるルシフェリラもまた消滅することになる。
三妖神が、その絶対的な力を持ちながらもヤフェイを今まで消さなかった、いや、消せなかった最大の理由がそこにある。
他にも理由は色々あるが、ルシフェリラに対しての思いが決定的な理由であった。
ルシフェリラの存在を守るために、暴挙を繰り返すヤフェイを無念を飲み込んで見逃すしかなかった。半殺しで我慢するしかなかったのだ。
だが、ミューズはにやりと笑う。
「心配無用。ルシフェリラ殿を守る手は既に考えているわ。
マスターを失って三千年、その間、この私が無駄に時間を浪費していたとでも思うの?」
絶対の自信を持ったその微笑みにメセルリュースは彼女の謀略を止める術がないことを認識した。
(・・・・ヤフェイ・・・・自業自得とはいえ・・・・哀れね・・・・)
最強最悪。”謀略の魔女”あるいは”恐怖せしめる残虐神”の異名を持ち、その雷名を聞けば邪神さえ恐怖に震えると言われる雷神ミューズの怒りを誘ったものが、どれほど惨めに残忍に殺されるか彼女は熟知している。
恐らく、ヤフェイは今までのどんな存在よりも惨めな最期を遂げることになるだろう。
自業自得とはいえ、ヤフェイの不運と悲劇にメセルリュースは同情せずにはいられなかった・・・
「もしかしたら・・・・彼女を見殺しにするかも知れないから、覚悟をしておいてね」
意地の悪い笑みを浮かべたミューズにメセルリュースは眉をしかめる。
「何の事ですか?」
「あの小娘のことよ。
あの娘にあなたの欠片が入っているのに気づかないと思っていたの?」
「・・・・」
ミューズの言葉にメセルリュースはしばし沈黙していたが、深いため息を付いた後、諦めたように呟く。
「気付いていたのですか・・・・」
「当たり前よ。そうでもなければ・・・・」
それ以上は言わなかった。メセルリュースが今にも泣き出しそうな顔になっているのだ。
「私は・・・・彼の元にいたかった・・・・でも・・・・」
「全く、随分と危険なまねをしたものね。
あの馬鹿がこのことに気付いたらあなたの力を悪用されかねないのよ」
ミューズは、彼女が何をしたのか知っていた。そのためにあの不幸にして皮肉な結末があったのだ。だが、それはまだ終わっていない。ヤフェイの存在がある限り、そして、その手の中に”あの小娘”の魂が有る限り、それは、危険な火種となりうる。
「過去のことをどうこう言っても仕方がないわね。
これからの事を考えましょう」
ふっきるようにミューズは言葉を続けた。
冷たい言葉であった。だがそれが正論だ。
メセルリュースは気弱な恋に憶病な娘から、完璧な女神の顔に瞬時に立ち戻る。
「分かりました。彼女の処置はあなたに任せます。
あなたが最善と思う方法をお取りなさい」
女神の主人としての威厳のある言葉。自分の言葉、その行動の全てに責任をとる覚悟を決めた、その証。
「有り難う、そう言ってもらえると助かるわ」
ミューズは頷いた。もしも、ヤフェイが彼女の秘密に気が付いた時は、最後の手段も辞さない。ミューズは固い決意を心に持っていた。
そして、この瞬間、ミューズの計画は完成したも同然だった。ヤフェイ抹殺計画が。
後は、何時あの愚かな神が自分達に無謀な挑戦をしてくるか。それを待つだけだった。
彼女の主人はこちらから手を出すことをよしとはしない。あくまでも向こうが手を出した時に初めて反撃できるのだ。
ヤフェイが野心に駆られて戦いを挑んだ時。その時こそ、あの愚かな神の最後の時なのだ。
2
自分の考えていた以上に長い年月を生きていたことは、彼女にとってかなり大きな衝撃だった。しかし、朱雀と分かりあえたことはそれに勝る喜びだった。
「これからどちらへ?」
朱雀の問いにシリスは何かを決意したような厳しい顔で答えた。
「竜王様方の元へ・・・・」
朱雀とシリスはそこで分かれた。精霊の朱雀には竜族の聖域、竜界へ行くことは出来ないのだ。
朱雀は一足先に現界へと戻り、シリスはそのまま、何かを思い詰めたように深刻な表情で竜界へと赴いた。
竜界。
神をも越えた最強種族、竜族の聖域。
竜界は現界から完全に隔離された場所にあり、そこにすむのは竜族でも最高位の力を持つ者達だけである。
四竜王と四十八貴竜。そして、四十八貴竜の直属の部下で百九十二体居る天竜。
彼等は神竜族とも呼ばれる竜族最強の存在である。彼等はあまりに強大すぎる力を持っているために滅多なことでは現界に降りることはない。四十八貴竜は創造神を越える力を持ち、天竜達も上級神以上の力を持っている。よほど注意しなければ、そこに存在するだけで世界のバランスを狂わせてしまう。
そのために彼等は滅多に現界に降りることは出来なかった。ましてや竜王ともなれば竜界にある竜宮から動くことは殆どないと言っても良い。別の世界に行くことを除けば、だが。
・・・・ただ、その割にはマスタードラゴンの元に顔を出しまくっている様な気がするのだが・・・・まあ、気のせいだろう・・・・
竜界に赴いたシリスは殆ど手続きをすることもなく、あっさりと黒竜王の元へと通された。
マスタードラゴンの使い魔、薬神シリスは竜王に直接会見できる数少ない存在なのである。
「黒竜王陛下、お久しぶりです」
女神としての正式な礼服を着て礼儀正しく挨拶をするシリスに優しく微笑む黒竜王。
その外見は人の感覚で言えば十二才程度の童女の姿だ。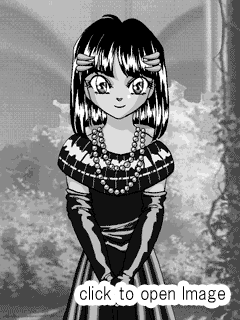
髪型は肩口に合わせて切りそろえられたおかっぱ頭であり、顔立ちも美しいと言うより愛らしい感じの幼さの残る顔である。
髪と瞳は黒曜石のごとき漆黒。その艶やかさは何とも言えず美しい。
黒竜王は何故かこの姿を気に入っているらしく、マスタードラゴンや三妖神と会うときはこの姿をとる。
外見からはとても竜族とは思えない。唯一点、左右の耳元から生えている、髪飾りのように見える三本、計六本の美しい角を除いては。
黒を基調として所々金糸と銀糸で飾られた、決して華美ではないが優美な礼服を着てシリスを迎えるその瞳には、外見の幼さを補って余りある知性の輝きを秘めていた。
もっとも、竜王たる彼女は数百億年以上の時を生きている。外見で彼女を判断するのは愚かの極みだ。
無限とも言える魔力と不死身の肉体を有し、あらゆる世界の知識を所有する最強の存在。
全次元世界の守護者、四竜王。
その席の一つに座る彼女は全ての大地と闇を統べる力を持つのだから・・・・
「この度は、是非とも黒竜王陛下にお尋ねしたい事がありまして、お伺いしたのですが・・・・」
「あなたの力の事と彼との出会い・・・・そうですね」
優しい言葉をかける。
シリスは頷き、彼女は自分の予想が正しかったことを改めて確信した。
「・・・・わたくしの力を完全に封じる力を黒竜王陛下はお持ちでした。
それにも関わらず、何故わたくしの力を封じず、結界に封じるにとどめたのでしょうか?」
そう、シリスはその疑問をずっと持ち続けていた。彼女の力を封じる結界を紡げた黒竜王と白竜王ならば、彼女の力そのものを封じることが出来たのではないか?
現実に彼女の毒の力は二竜王には通じなかったのだから。
「ええ、確かに封じることは出来ました。
しかし、あの当時、あなたは生まれたばかりの幼く弱い存在でした。そのあなたに存在そのものに干渉する術を施すのは危険だったのです。
無理に術を仕掛ければ、その術に耐えきれずに力が暴発することもあり得ました」
淡々と語る黒竜王。その言葉は感情を見せず事務的なものだった。
「ですが、結界の中でわたくしも成長していました」
シリスの反論に黒竜王は深く頷く。
「そう、その通りです。
あなたにとっては極めて迷惑な事だったでしょうが、私達はあなたを利用したのです。
マスタードラゴン殿を、彼をこの世につなぎ止めるための存在として」
やはり。やはりそうであったのだ。
シリスは自分の予想が正しかったことを知った。
シリスの考えを知ってか知らずか――おそらくは承知の上であろう――黒竜王は言葉を続ける。
「私達は彼の、マスタードラゴンの存在を必要としていました。
彼がこの世界に生まれ落ちることを私達は知っていました。
そして、彼が自分の力の重さに耐えきれず、自滅寸前となることも私達は知りました。
彼に生きるための目的を与えるにはどうすればよいのか、私達は悩みました。
彼を生かすために何が最善であるのか・・・・
そして、私達はあなたと言う存在を彼と出会わせることにしていたのです。
彼が生まれる前。遥かな過去に、それは決められていました・・・・」
遠い目をして黒竜王は天井を仰ぎ見る。
竜宮の謁見室。その天井は普段空を映し出していた。
美しく澄み切った青空を映し出す天井。それを見つめる黒竜王の瞳には遥かな過去、マスタードラゴンの当時の姿が見えているのかも知れない。
・・・・まだ、彼がシリスの存在を知らなかった頃、彼は自分の力を何よりも恐れ忌み嫌っていた。
その力は彼を同族から隔離し、人間の創造神の欲望をかき立て、彼を孤独の中に閉じこめ苦しめた。
その孤独と恐怖から逃れるために彼は使い魔を作った。
元々、その使い魔は彼を滅ぼす為に作られた。そう、今でこそ絶対の忠誠を誓う下僕である彼女達は本来、彼自身を滅ぼす天敵として作られていたのだ。そのはずだった。
だが、彼の持てる技術と力を結集して生み出されたはずの使い魔は、残念なことに彼の期待に応えることは出来なかった。
使い魔としては破格の力、上級神さえ越えるほどの力を持つ使い魔。それでもなお、彼の力には遠く及ばず、彼を滅ぼす力を持つことは出来なかった。
万が一自分の力が暴走した時、彼女達に自分の力を抑える役を望んでいた彼の望みは潰えた。彼はしかたなく彼女達と家族として共に暮らすことにした。
彼女達と暮らすことにより孤独はある程度癒されたが、自分の力に対する恐怖は消えなかった。それどころか上級神にも勝る力を持つ使い魔を作り、それでも自分の力に遠く及ばないと知った。それは彼の恐怖を助長するには充分すぎた。
現実に自分にちょっかいをかけてきた人間の創造神が、まるで虫けらのごとくあっさりと使い魔達に叩き潰されたのを目の当たりにした時、自分の力が、存在がこの世界にとって間違いではないのかと思うようになった。
彼はその頃から、自分自身の力から逃れる方法が”死”、完全な消滅しかない。
そう考えて居たのかも知れない。
彼を見守っていたのはシリスだけではなかった。竜王もまたある理由から彼を見守っていた。彼が生まれる遥か前から。そして、彼が自らの存在を抹殺することは彼女達にとって好ましいことではなかったのだ。
そして、彼女達は考えた。彼に生きる希望を、生きるための目的を与えることを。
その目的は彼でなくては、”彼の力無くしては”不可能なことが望ましい。
白羽の矢は、遥かな古の時、黒竜王と白竜王が封じた魔獣の末裔に突き立ったのである。
結果としてその目論見は最大の効果を上げた。
魔獣の末裔の存在を知った彼は、魔獣を封じその力を良い方向に使う機会を与えた。それにより、彼自身、自分の力の使い道を見つけた。魔獣の末裔を守るという生き甲斐を。
その魔獣が薬神としての地位を与えられ、邪神に対抗する新しい力となったのは、竜王達も予想していなかった嬉しい誤算だった。
そして、今、その薬神がここにいた。薬神シリスが。
「あなたを利用したこと、幾重にもお詫びいたします。
けれど、我々にはあなたに犠牲になってもらうしか方法がなかった。
彼が自らの存在を否定することだけは、どうしても避けたかったのです。
私達の都合であなたに長き孤独と苦痛を与えたこと、許されることではありません。
謝って済むことではありませんが、お詫びいたします。
本当に、申し訳ありません」
シリスに対して、黒竜王は深々と頭を下げた。その謝罪にシリスは目を丸くする。
よりにもよって、絶対無敵、万物の頂点に立つ四竜王の一人に頭を下げられているのだ。驚くなと言う方が無理である。
だが、黒竜王にとってはそれは正当な理由があった。謝ったところで到底許されることではないのだが。
四竜王ならば、黒竜王ならば、マスタードラゴンの力を封じることは出来た。
だが、どうしてもそれを行えなかった。
黒竜王自身は彼の力を封じるつもりだった。人が持つにはあまりにも危険な力。
その力を封じるつもりでいた彼女を止めた者がいた。
強大な力。そしてその力を御しえる能力を持つ者を白竜王が欲していたのだ。
だから、その力を封じることを禁じた。そして、そのかわりとして、シリスの存在を必要としたのである。
今、彼は力を失っている。しかし、いずれ、彼は再び力を得るだろう。そのための今は休息の時。
より強大な力を得て大いなる存在となるための。真なる”マスタードラゴン”となるための。
全ての運命は白竜王の掌の上にあった。
「顔を上げて下さい。
わたくしは黒竜王様を責めるために参ったのではありません。ただ、真実を知りたかっただけなのです。
怨んでなど居ません。むしろ、感謝さえしているのです。
御主人様と巡り会う機会を与えて下さったのですから」
シリスにしても、彼が夢の中で自ら命を絶てば、さぞ、後味の悪い思いをしただろう。自分の影とも言うべき存在が死によってしか救われないなら、自分も何時かは・・・・そう絶望したかも知れない。
自分の存在がマスタードラゴンを救ったという事は彼女にとって喜ぶべき事なのだ。
竜王達を何故怨むことが出来るだろう。感謝することはあっても怨むことなど、彼女には出来ない事だった。
「身勝手な私達を許してくれると?」
「許すも何も、わたくしは何もされていないのですから」
シリスの笑顔に黒竜王は再び頭を下げた。
シリスが黒竜王の前から退出しようとしたとき、思い出したように彼女はシリスを呼び止めた。
「一つだけ、あなたにお尋ねしたいことがあります」
シリスはそれを聞いて軽く眉をしかめた。
「森羅万象、全界に知らぬ事の無き竜王陛下に、わたくしがお教えできるようなことが有りましょうか?」
「あの方は・・・・私の罪をお許し下さるでしょうか?」
うつむき、尋ねるその気弱な声音に、シリスは彼女の言葉の意味を把握した。
「・・・・わたくしの知る限り、御主人様は四竜王陛下を愛して居られます。
決して、あなた様方に恨みを抱くようなことはないでしょう。
どうか、ご安心下さい」
それを聞いて、黒竜王は力無く頷いた。
3
メイルは困っていた。
他の二人は未だに帰ってこず、竜一は虹の乙女達の玩具と化している。
話に入ろうにも話題に付いてゆけず、口を開いても言葉が出ない。
「・・・・話題が・・・・無い」
心底困ったように呟き、途方に暮れた顔でレインボーシスターズと竜一のやりとりを無言で見守るしかなかった。
しばらくして、やっと満足した聖霊達が引き上げてからも他の二人はなかなか戻らない。
二人は唯、何も言わずに見つめるだけだった。
この場合、二人が無言だったのにはそれぞれ訳がある。
メイルの場合は二人っきりで何を言えばいいのか分からなかったためだが、竜一の場合は精神の疲労がピークに達し、口をきく事も物を考えるのもおっくうになっていたのだ。
何しろ、昨日は十二神将の宴会拷問、今日はレインボーシスターズの世間話攻撃。
両方とも竜一が出来るだけ会いたくない相手だった。神経はすり減り、胃はギリギリ痛み続ける。
その地獄の時間からやっと解放されたのだ、放心状態になっていても仕方がないだろう。
ぼーーと、焦点の合わない目で見ていた先がメイルだったわけである。
しかし、精神のやすらぎの代わりに、肉体はやすらぎを失っていた。
ぐううぅぅ・・・・
盛大な腹の虫がなる。朝から殆ど何も食わずに彼女達の相手をしていたのだから、健康的な肉体が文句を言うのも当然だった。
この場合レインボーシスターズが彼の食事のことを失念していたのには訳がある。
かつての彼は竜王に近い力を持つ程の存在であったため、その気になれば何も食べなくても平気だったのだ。その点で彼は竜族や神々に類する存在であった。
虹の乙女達はかつての彼と同じ感覚でつきあっていたため、普通の人間になった彼が食事を必要とすることに気が付かなかったのである。
ただ、たとえ休憩を与えられたとしても、罪の意識を引きずりまくった竜一が、その原因である彼女達の前でまともに食事が出来たかどうかは疑問の残るところである。
「飯の用意でも・・・・」
竜一が立ち上がろうとした時、メイルがそれを止めた。
「あたいが作る」
そう言って、そのまま厨房に引っ込んでしまう。
「・・・・書庫から適当に本でも持ってくるか・・・・」
他にすることが無い竜一は、立ち上がると、二階にある巨大図書室へと向かった。
あたいは盟主と二人っきりになっても、何もできない・・・・
厨房で料理を作りながら、嘆息する。
なさけなさに涙がにじむ。
こういう時位しか二人っきりになれる事はないのに、二人っきりになると何も言葉が出ないのだ。ミューズ達が側にいる方が何かと口が回る。
自分から話題を作ることが、自分にとってこれほど難しいとは思ってもいなかったメイルだった。
考えてみれば自分は何時も力で戦ってきた。
それだけが自分の出来ることであり、自分が主人たるマスタードラゴンに対する役割だと思っていた。
今まではそれで良いと思っていた。策謀はミューズに任せ、自分は何の気兼ねもなく力任せに敵を打ち砕くだけで良かった。
だが、こういう状況では何の役にも立たない。
マスタードラゴンを、自分の主人を異性として意識しだしたとき、力だけで生きてきた自分には、己の心を表現することさえ出来なかった。
おまけに、マスタードラゴンは超が付くほど女心に鈍感だった。転生してもその性格は一向に矯正されない。自分から言わなければ彼は未来永劫、気づくことはないだろう。
だが、それは口に出来ない言葉。
それを口にすれば今の三人の関係が、三妖神の結束が壊れてしまう恐れがあった。
性格も能力も考え方さえ全く違う三人。一見バラバラにしか見えない三人が完璧な調和と結束を保っているのは、マスタードラゴンへの絶対的な忠誠によるものだ。
最も忠実と言われるのはメイルだが、他の二人もマスタードラゴンへの忠誠は生半可なものではない。
唯、他の二人は別の役割を持つために、忠誠心がメイルより薄いように思われるのは仕方がないのだ。
メイルは全て忠誠心が基準となっている存在だった。
主人であるマスタードラゴンに対して絶対にして完全な忠誠を持つこと。それは彼女の主人の心に強固な信頼感を与える。
彼女だけは絶対に自分を裏切らない。世界中の全てが敵になったとしても。
その強固な信頼感がマスタードラゴンを精神的に支えている。
だが、メイルの心に”異性としての”愛情が生まれたとき、彼女は自分の忠誠心が愛情に変わりはじめるのを感じた。
それではダメだ。それでは、忠誠を保てない。
愛情とはいわば独占欲の別名でもある。そして、愛情はささいなきっかけで最強の憎悪に変化する不安定な物だ。三妖神の一人としてではなく、女として、マスタードラゴンの全てを独占したい。そう考える様になるだろう。そうなったら、三妖神の結束は簡単に崩れてしまう。
だから、自分の心の奥にそれを封じた。自分自身のために、主人のために。
それでも、彼と二人っきりになると、どうしようもなく心に思いが募る。
このままではいけないと思っているのに、抑えが効かなくなりそうになる。
だから、それを紛らわすために別のことを考えようとする、他の話題で気をそらそうとする。そうしたいのに、話題が出てこない。何も考えられない。
「・・・・どうすればいいのか・・・・」
何かいい手はないものか。必死に考えるのだが、何しろこういう事に関しては全く免疫のないメイルである。妙案など思い浮かぶはずもない。
同じように主人に恋心を抱いていても、他の二人は上手くやっている。他の二人のようにそつなくこなすことがメイルには出来なかった。
自分の不器用さが恨めしい。
無視するという手は使えない。使い魔としてもそんな事が出来るはずがないし、第一自分自身、主人の側にいるのは不快ではないのだ、ただ、辛いだけ。それでも、側にいたい。
最強の闘神、無敵の戦士メイル。
邪神に恐れられ、竜王にさえ一目置かれる彼女にとって、愛こそが最大の強敵であった・・・・。
4
「・・・・見ておれ・・・・今に・・・・今に見ておれよ・・・・」
地の底から這い出てくるような怨念。
あたりに重く立ちこめる障気。
一見、凶悪な鬼神か暴虐な魔王の城かと勘違いしたくなるような、密度の高い怨念がとりまく、ここは神の城。
その憎しみと怒りは激しく燃え盛り、彼の心と体を焼き続けている。
「・・・・獣共めが・・・・造物めが・・・・
下等生物の分際で、創造神の我に逆らいおって・・・・・」
その目には狂気が宿り、口からは重い呪詛が漏れ出ていた。
「見ているが良い。我こそが唯一絶対の神にふさわしい・・・・
我こそが全能の神なのだ・・・・貴様等の血と命でそれを証明してみせる・・・・」
呪詛の声はますます強く、深い憎しみと怒りに煮え立つ障気を吐き出す。
「見ているが良い・・・・いずれ・・・・必ず・・・・」
彼の予言には、自分の絶対的な勝利が記されている。天から落とされた邪悪な者共と神の戦い。そして、神の軍勢の勝利が。
「そう、この予言の通りに・・・・全ては・・・・決定しているのだから・・・・。
それが運命なのだ・・・・
我が決めたのだからな・・・・、全能の神となるこの我が・・・・」
自ら作った予言の一文を思い出し、ぐっぐっぐ。と悦に入った笑いを漏らす。
彼は、自分が作った予言に自分自身が惑わされているのだ。だが、その事実は彼には見えていない。
彼にとって必要なのは、自分の夢想の世界であって現実ではなかった。
「ヤフェイ様・・・・いかにしてそれをなすおつもりですか?」
彼の傍らにいつのまにか天使が立っていた。彼女は、メイル達との戦いの時唯一生き残った天使。
彼女の役目は戦いの趨勢を見守る事。神の目となり耳となり情報を集める。そのために、彼女はいかなる戦いにも助力しない。ただ、見守るだけ。
ヤフェイがそう彼女に命じた。
「彼女達は恐ろしいほどに強い力を持っています。
このままでは・・・・」
勝ち目など無い。その言葉を彼女は飲み込む。
「案ずるな・・・・我には切り札がある。
いかに奴等が下等動物と言えど、あの者の顔くらいは覚えておろう・・・・
そう、あの者が我が手中にある限り、奴等に勝ち目など無いのだから・・・・」
くっくっく。喉を振るわせて悦に入る。それは、とうてい神の姿とは思えず、天使は僅かに顔をしかめた。
「見ておれ・・・・今に・・・・今に!」
そして、咆哮が城を揺るがせる。
「我に対する不敬の数々! 貴様等の血と命であがなってもらう!!」
ひとしきり不満をぶちまけ、城の中に漂う怨念の障気をより濃くして、神は思案に耽る。
いかにして、奴等に自分への贖罪をさせるか。
その思考に没頭した神は、もはや身じろぎもしなかった。
かくて、様々な存在から思慮と謀略は生まれでる。
それが新しい歴史を紡ぐ糸となるのか、編みあがった歴史を引き裂く破壊の刃となるのかは時の女神の裁量しだい。
人はそれを運命と呼ぶ。
・・・・様々な思いと出来事を飲み込んで時は流れる。
そして、祭りの終わりがやってくる・・・・
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / < 10 > / 11 / 12 / 13 / 14