[ 三妖神物語 外伝2 海辺にて・・・・ ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第2章 深淵より来るモノ
「いーやーだー! 死にたくないいぃ」
「往生際が悪い、あきらめろ」
夜、あたりには民家もなく、街灯もない。明かりと言えば遠くにある観光客用のホテルの窓の明かりと、星明かりくらいしかない、漆黒の闇の中で、何やら言い争う声が聞こえる。
一方は声変わりを済ませた男の濁声。もう片方は性別不明の声だった。
抑揚もなく、性別どころか感情さえその声からはかることは難しい。
「冗談じゃない! 行くならお前だけで行けえ!! 人を巻き込むなあ!!」
すでに半泣きと言っても良い男の声に、性別不明の声はきっぱり言いきる。
「そうはいかぬから、お前を連れてきたのだ。
私一人で済むなら、足手まといのお前などわざわざつれていくものか。
いい加減、男なら覚悟を決めろ、一樹」
愛想もくそもない口調で断言する。
だが、そう言われた当人は、覚悟など全く決めていなかった。
「馬鹿ぬかせ! お前と違って俺は普通の高校生なんだぞ!!
いくら竜神の
行くなら一人だけで行け! 唯!!」
どうやら、彼等はいとこ同士であるらしかった。
話を聞けば、従兄弟という理由だけで、魔物退治に無理矢理つきあわされようとしているらしい。
この状況を見る限り、一樹と言われた少年の方の言い分が正しいように思える。
ただの高校生に化け物退治などつとまるとは思えない。まあ、多少、従姉妹に対して薄情な気もしないではないが・・・・
ただ、唯と呼ばれた美女にも何やら彼を連れていかなければならない理由があるらしい。泣こうがわめこうが、彼女は全くそれには取り合わず、何やらぶつぶつと呟くと、突然、叫んだ。
「九羅座火!!」
否、それは呼びかけであった。やがて、彼女の呼びかけに何かが答える。
「
夏のそれも亜熱帯の沖縄である。例え夜といえどもそれほど気温は下がらず、その暑さは、じっとしていても汗ばんでしまうほどだ、しかし、声が聞こえた瞬間に、唯と一樹の周りの気温が急激に下がった。過ごしやすい涼しげな空気が彼女達の周りをとりまいている。
「九羅座火、私達を運んで海の上を飛んでもらいたい」
「承知」
唯に風が答える。次の瞬間には唯と一樹は見えない何者かに乗って、夜の空に舞い上がっていた。
「やめてくれーー! 降ろしてくれえぇぇ・・・・」
後には一樹の悲壮な声だけが残された・・・・
「・・・・・・・・」
そんな二人を、少し離れた場所から見送る影があった。
十分に鍛えられた、そして極限まで無駄な筋肉をそぎ落とされた理想的な肉体を持つ者が、二人に気取られぬようその気配を完璧に消して、一部始終を見届けていた。
と、その影の後ろから声がかかった。
「このような所で何をなさっているのです? 康夫さん」
「わあ!」
その声に、おそるおそる後ろを振り向いて・・・・康夫は彼女がすぐ後ろにいることに今更ながら驚いていた。
「こ・・・・これはシリスさん・・・・脅かさないで下さいよ」
大げさに息を付いて、康夫は自分より頭一つ分は小さい彼女を見おろした。
「そう言うシリスさんこそ・・・・一人で女性が出歩くのは・・・・物騒ですよ」
「わたくしが普通の人間でないことは十分ご承知のはずでしょう?
そのような心配は無用ですわ」
「普通、そんな事を堂々という言うものかなあ・・・・
たいていは秘密にしたがるものでしょう?」
苦笑しつつ康夫は話をはぐらかそうと、少しずれた話題を出した。
「御主人様はあなたのことを心から信頼していらっしゃいますから・・・・あなたの”正体”を知らなくとも・・・・」
話題を逸らすつもりが、やぶ蛇であったことに気づき、自分の浅はかさを康夫は後悔した。
そんな康夫の様子を無視して、一呼吸おいてシリスは真っ直ぐに康夫を見つめる。
「それよりも、わたくしの質問に答えていただけません?」
「・・・・いや、・・・・その・・・・ちょっと、散歩してみたいなーっとか思いまして・・・・」
しどろもどろに答える康夫に厳しい視線を向けるシリス。その瞳に見つめられて康夫は内心焦っていた。
「・・・・これは、わたくしの個人的な感想ですが、彼女達はおそらく竜神の力を継いでいる一族だと思います・・・・」
康夫のあせりを知ってか知らずか、シリスは話し出した。
「わたくしの見立てでは、確かに彼女達の力は人間としてはかなり強い方でしょう。
竜族の力を与えられている以上、余程の事でも無い限りは、問題はないと思いますが・・・・」
そこで言葉を区切り、強い眼力で康夫を射抜く。
「今回の相手は、この世界の黄金律を無視した力を使う存在・・・・おそらくは、彼等の影響を受けた存在なのでしょう・・・・
彼女にはいささか荷が重すぎるのではありませんか?」
「あの・・・・おっしゃっている意味がよく分かりませんが・・・・俺に何を期待していらっしゃるのでしょう?」
いつのまにか、康夫の言葉遣いが丁重になっている。
どうやら、シリスにつられたらしい。シリスはさらに言い募る。
「とぼけられるのですか?
では、はっきり申し上げます。手助けしなくてよろしいのですか?
あの子達は竜の力に連なる者達なのでしょう? 例え種が違うといえども・・・・」
「・・・・そりゃ、俺はけっこう強い方だと思いますよ。」
溜息混じりに呟く康夫。”結構”などといってはいるが、彼の腕力は人間の常識、いや、非常識さえ越えたところに位置している。
「けど、それはあくまでも腕力だけです。
妖怪だの魔物退治だのそんな非常識な相手にどうしろというんです」
康夫の言い訳じみた台詞に、シリスは嘆息した。
「そうですか・・・・まあ、よろしいでしょう。
結論を急ぐつもりはありませんし、”あなた方”が御主人様に危害を加えないことは承知しておりますから・・・・」
そう言うと、唯と一樹が消えたあたりを見つめ・・・・
ばさり!
その音と同時に、彼女の背中には美しい白銀の翼が一対、現れる。
僅かな星明かりでさえ微妙な光彩と虹の色彩を描く夢幻的な美しさを描く翼。
微細な鱗が描く至高の芸術品と湛えられる女神の羽衣。それを広げて、優雅に空中に舞う。
「どうするつもりですか?」
「あの子達が心配ですから・・・・様子を見に参ります」
その一言だけを残し、再び翼をはためかせる彼女。
そして、次の瞬間には彼女の姿はもはや彼の視界の届く範囲には無かった。
「・・・・やはり、彼女はごまかせないか・・・・」
康夫は苦笑した。その呟きを聞いたのは、風と海、そして、大地の精霊達だけだった。
自分達の部屋に戻ったミューズはシリスが居ないことに真っ先に気が付いた。
「シリスは? 買い物にでも行ったの?」
「いいや」
メイルがつまらなそうに返答する。
「・・・・まさか・・・・」
ミューズの絶句にメイルは仏頂面で頷く。
「・・・・全く! 前の自殺未遂事件といい、どーして、よけいなことに首を突っ込むのよ!」
「仕方がない。お節介で誰にでも情をかけるのがあいつの癖だ」
そのあたりのことは、ミューズもメイルも十分に承知している。彼女の異常なまでのお節介、人への同情心の理由は。
だが、ついつい、口に出して怒りたくなるミューズだった。
なにしろ、相手はその道のプロである。
シリスのことから自分達のことをかぎつけるかも知れない。
シリスのことだから、相手にこちらのことを知られるようなドジを踏むとは思えないが、万が一という事もあり得る。そうなれば事態はややこしい事になるかも知れない。
勿論、どんな相手だろうと実際には大した問題ではない。この世界の神や魔王であろうと自分達に危害を加えることは出来ない、まして、そこらに転がっている人間の魔術士や霊能者など自分達にとっては敵にはなり得ない。
だが、わずらわしいことは事実であるし、康夫や竜一のように規格はずれの人間がいないとも限らないのだ。油断は禁物であり、危険は最小に押さえておくべきである。
「メイル、マスターをお願いね」
「行くのか?」
おもしろくなさそうにメイルが問うと、ミューズは頷いた。
「つまらない事件に巻き込まれる前にシリスを連れ戻すわ!」
そう言うと、メイルの返事も聞かずに部屋を飛び出していった。
ミューズの剣幕に呆気にとられていたメイルは、ぼそりと呟いた。
「・・・・既に手遅れだと思うが・・・・」
メイルの呟きは殆ど、完全な事実であった。しかし、その言葉をミューズは聞いていなかった。
それは、鳥のように見える。少なくとも、外見上の特徴は人間が知り得る生き物の中では鳥と呼ばれる部類に入るはずである。
柔らかな羽毛に包まれた翼を時折はためかせ、風に乗って優雅に舞う姿は人間にとってもお馴染みの光景だ。ただ、問題なのはそのサイズである。
その背中には小さな影が二つ乗っていた。その鳥のサイズに比較すれば、ノミのように小さい、だが、そのノミのような影は先ほどからののしり有っていた。正確に言うなら片方が一方的にまくしたて、もう片方はそれを聞き流している様子だ。
そう、その影は人間だった。
人間がノミほどのサイズに見えるのだから、その鳥の大きさがどれほどのものか想像に難くない。
力強く広げられた翼は、片方だけでも8mはあるだろう、両翼の幅は20mをくだらない。その巨大な存在を現在の科学は理論的に説明することはできない。
そしてそれは例え目撃されても人間には認知されない。人の常識に反するものを人は決して認めはしないのだ。それが、自らの目で見たモノであろうとも・・・・
そして、先ほどから聞こえる絶叫は今だ耐えることなく続いている。
「俺は帰る! 早く降ろせ!! 戻せーー!」
その濁声はあの浜辺でわめいた者と同じだった。彼の名は一樹、いとこに無理矢理魔物退治につきあわされている哀れな青少年だった。
「いい加減にあきらめろ、往生際の悪い・・・・・」
さすがにこれだけ怒鳴られると、無視し続けることもできないらしい。
唯は顔をしかめて、わめき続ける従兄弟を見やった。
「・・・・そんなに戻りたいか?」
「当たり前だ! 戻せ!! 降ろせーー!!!」
「分かった」
あっさりと頷く唯に一樹は素直に喜べなかった。絶対に何か裏がある。そして、不幸にも一樹の予感は的中した。
「そんなに帰りたければ、帰っても良い。
ここから自力でホテルのある海岸まで泳げ」
きっぱり言いきった唯の顔を、一樹はしばらく呆然と見ていた、が、すぐに我に返って、確かめる。
「ここから、自力で帰れ・・・・と?」
「そうだ。帰りたければ勝手に帰れ」
愛想もくそもなく、一樹を一瞥すると、もう用はないといわんばかりに海に視線を戻した。
漆黒の色に塗り固められた海は、ときどき夜光虫や発光機能を持つ生物達の光が見えることもあるが、殆ど真っ暗闇と言ってもいい。
「・・・・」
一樹は自分達が来た方角を仰ぎ見た。
微かに、小さな明かりが見える。しかし、それ以上のモノは見ることが出来ない。
そもそも、その明かりが何の光なのかさえ分からなかった。
この暗闇の中で、小さな明かりを頼りに距離を測るなど、一樹には不可能だ。
いったいどれほど沖に来たのか一樹にはまるで分からない、だが、少なくとも数キロ程度の距離はあるだろう。
「あ・・・・あのさ・・・・唯・・・・」
「このあたりなら鮫くらいはいるだろう」
ぼそりと呟く唯。その言葉に絶句する一樹。
何しろ、世界でも有数の美しいサンゴの有る海である。
殆ど汚染されていないこの亜熱帯の海では、鮫もそれほど珍しい生き物ではない。
他にも猛毒を持つタコやクラゲなども多数生息しているだろう。
「・・・・・・」
視線を海に向ける。
いま、自分達がどれほどの高さを飛んでいるのか見当も付かない。
それほど高いようには思えない、だが、低いとも思えない。
この深淵は、人間から全ての感覚を奪い去る。ここから飛び降りて自力で泳ぎ帰るなど、まともな人間には絶対に不可能である。それは、常識以前の問題だ。
「・・・・つきあえば良いんだろう・・・・」
絶望の溜息を一樹はもらした。
「分かればよろしい」
そう言うと、唯は再び呪を唱え、名を呼びかける。
「荒御禍! 闇楓!!」
「
「
不意に空中から声が聞こえる、今まで何も居なかったはずの空間に二つの影がたたずんでいた。
外見は人間と殆ど変わらない。
淡い燐光をまとって空中に浮かぶそれは、一体はがっしりした髭面の男の姿を、もう一体は細身の女性のような姿をしていた。
「そろそろ始める。力を貸してくれ」
「御意」
「全ては巫女姫様のお心のままに」
唯の言葉に、二人はそう答えて軽く頭を下げた。
「お・・・・おい! いきなり、そいつ等を使うのか?」
呼び出された彼等を見て一樹は仰天した。何しろ、
「・・・・あ・・・・あのさ・・・・やっぱり、俺、帰りたいんだけど・・・・」
「なら、早く降りてくれ。これから私達は海の中へ入る。逃げるなら今の内だ」
唯のその言葉に、一樹は深いため息を付いた。
ぱっしゃあん
一樹の溜息を合図に、白波を立てて二人を乗せた九羅座が海中へとおどり込む。
周りは漆黒の闇。それは人間の心に恐ろしいまでの重圧をかけてくる。
九羅座火の結界の力によって、水圧はもとより呼吸の心配さえないはずなのに、
一樹は奇妙な息苦しさを感じ、胸元に右手を添えて深呼吸を何度となく繰り返す。
呼吸は間違いなく出来ている。肺には新鮮な空気が確かに補給されているというのに、胸を締め付ける息苦しさは全く変わらない。
違う・・・・
一樹の心の奥底にある冷静な何かがささやいてくる。
これは、海の、この暗闇の重圧ではない。
この息苦しさは海のせいではない。例え深淵の闇に有ろうと、海からこのような圧力を感じるはずがない。
一樹の中に流れる唯と同じ血。竜の力を預かる一族の血が、そうささやく。
普通の人間ならこの闇の海に恐怖を感じるかも知れない、しかし、竜とは即ち大自然の化身。その力の加護を受ける俺が、母なる海に恐怖を感じるなどあり得ない。
そう、これは海のせいなどではないのだ、それ以外の、とてつもない何か。
この海に潜み、我々の敵となる存在。その力の重圧なのだ。
その囁きを自覚したとき、一樹は眉をしかめ、口をへの時にゆがめた。
自分は何の取り柄もない一般人だと信じているのに、唯に付き合わされるたびに自分の中に流れる”竜族の血”を思い知らされる。
唯のように超常的な力を持っているわけでもないのに、彼の中に流れる血が嫌と言うほど自己主張してくれるのだ。
「どうかしたか?」
一樹の仏頂面をみて、笑いを含んで唯が尋ねる。だが、一樹は「別に」と答えるだけだった。
何も言わずに唯は視線を正面に戻したが、あの口振りと表情を見ると彼女が自分が何を考えているか分かっていたに違いない。
「何が
一樹は唸りながら自分の従姉妹の背中をにらみつけた。
力を感じる。
自分に対して敵となる存在が近づいてくるのをそれは感じていた。
大きな力だ。人の身には余るほどの巨大な力だった。
”食らってやる”
それは思った。
確かにその敵は強い。
もしも、自分が今までの存在であったなら、勝てたとしても、かなりの痛手を受けただろう。あるいは、負けていたかも知れない。
だが、今の自分はこの世界の黄金律を越えた存在。この世界の神の”法則”をさえ越えた存在だ。負けはしない。
”邪魔だてする者は・・・・倒すのみ・・・・そして・・・・全てを滅ぼしてやる”
何もかもを滅ぼす。そのために自分はここにいる。
あれと出会ってから自分は生まれ変わったのだ。
人間を今まで見守ってきた。だが、人間共は、己の欲望のために自分の聖域を破壊し尽くした。
聖域を破壊され信仰を失ったそれには何の力もなかった。ただ、時の流れの中で滅びるしかなかった。その運命を受け入れかけたとき、あれが現れた。
あれは自分に強大な力を与えた。この世界の全てを破壊し尽くせる力を。
今こそ復讐の時だ。長い時間、自分という存在に守られながら感謝も親愛もわすれ、己の欲望のために自分の聖域を破壊した人間共にその罪を償わせるとき。
人間共は自分と言う存在を抹殺したのだ。そんな奴等にかける情けなど、もはや無い。
そう考えると、もはやじっとしてなどいられなかった。
”全てを滅ぼす!!”
絶叫し、それは敵の前へと躍り出た!!
「なっ!!」
その突然の出現に、さしもの唯も思わず驚愕の叫びを上げた。
目の前に現れた巨体。暗く深い海の中で、それはあまりにもよく見えすぎる。
唯達に現れたその影の大きさは尋常ではない。
全体像は、岩の固まり。そうとしか形容できない不格好な代物だった。
ごつごつとした、まるで、ついさっき砕けた岩の固まり。そうとしか見えない。
その岩の固まりのほぼ中央にとかげ、あるいは蛇であろうか、は虫類とおぼしきモノの頭が浮き出ていた。たまたま、岩が似た形をしていると言うだけかもしれないが・・・・
そして、大きさが尋常ではない。その大きさは、横幅だけでも唯達が乗っている九羅座火の三十倍はある。縦方向の長さにいたっては百倍近い。
とんでもなく巨大な岩の固まりだった。
だが、唯が驚いたのはその巨体にではない。これだけ巨大で、大きな力を持つモノの存在を直前になるまで気が付かなかったという事だ。
普通なら、これほど大きな力を持っているなら気配くらい悟れるはずなのに・・・・
だが、すぐに驚愕から立ち直り、自分の部下の名を叫ぶ。
「九羅座火!!」
唯の意図を察知して、九羅座火が、闇楓と荒御禍が瞬時に空間を跳ぶ!!
「まずいな・・・・思ったよりやっかいな相手だ・・・・」
舌打ちした唯に一樹がおびえたを含んだ声で尋ねる。
「や、やっかいな相手って・・・・勝てるのか?」
「わからん・・・・」
一樹の不安な声に、これ又自信のなさそうな答えを唯が返す。
「ま・・・・マジかよお・・・・」
半泣きで一樹は情けない声を出した。
剛胆で大胆不敵の唯がこんな弱気な事を言うのは、一樹にとっても初めてのことだ。
それ程までに奴は手強い存在らしい。
「奴の力は異質だ。この世界の黄金律に定められたモノではない。
質が違いすぎて、力の大きさも能力も見抜けない・・・・」
「来ますぞ!」
荒御禍の声に答えるように、その巨体が海を割って飛び出した。
「荒御禍! 奴の眉間に
闇楓! 私と同調しろ!!
九羅座火! 結界を強化!!」
ドウオオォォン!!
爆音にも似た轟音があたりに響きわたる。
荒御禍が放った強大な力を持つ雷撃は正確に岩の中央にある蛇の眉間に命中した。
激しい火花を散らしながら術によって生み出された雷は常識ではあり得ないほどのエネルギーと持続力で相手の体を引き裂こうとしている。
「
唯の声に答えて、荒御禍が放ったより数十倍、数百倍のエネルギーを持った強力な雷が幾筋も天空から、導かれるように荒御禍が打ち込んでいるポイントに命中する。それは一寸の狂いもない精密射撃であった。
集中した巨大なエネルギーはあたりの空間を青白く染め上げ、怪物の巨体をプラズマの炎で覆い尽くす。
ピシッ
異様な音がした。
「なんだ?」
一樹が眉をひそめたとき、どう見ても岩にしか見えないその化け物の体に、深い亀裂が幾筋も走った。
それは見る見るうちに怪物の体中に広がり、中から赤い光が漏れ始める。
「やった! 案外簡単じゃねえか!!」
やがて、亀裂同士がつながり、ぱらぱらと岩肌がはがれ落ちてくる。
それを見て勝利を確信した一樹だが、そうは甘くなかった。
はがれ落ちた岩肌、細かいモノでも数m、大きいモノでは数十mもあるそれが、ものすごい勢いでこちらにつっこんでくる!
「な!!」
驚愕の叫びを上げた一樹だが、その岩は九羅座火の結界に阻まれて彼等には届かない。
「ふう・・・・焦らせやがって・・・・」
額の汗を拭いため息を付く。
化け物の方を見ると、落ちる岩の固まりが雨のようだ。しかし、それらは有る一定の位置まで落ちると、落下をやめて急激に襲ってくる。
今の所は結界で防げているが、それは十分な負担となっている。ただの岩なら、いくらぶつかっても九羅座火の結界はびくともしない。しかし、相手は唯が恐れるほどの怪物である。その岩には強力な念と力が込められているのだ。その力に少しずつ九羅座火の結界の力がそぎ落とされて行く。
「こりゃ、唯に化け物が倒されるのが先か、結界が壊れるのが先か、競争だな」
こういう事態になると一樹には何の手助けもできない。ただ、唯に張り付いて成りゆきを見守るだけである。
ピシ・・・・ピキピキ・・・・
新しい亀裂がどんどん増え、既にあった亀裂はどんどん長く、より深いモノへと変化する。
それと同時に崩れ落ちる岩もより大きなものとなり、それがそのまま九羅座火の結界を脅かす。
「鼬ごっこだな・・・・どちらが先に音を上げるか・・・・」
見物人になるしかない一樹は、素直に観戦モードに突入していた。
ビュヴヴヴ・・・・
ついに九羅座火の結界までも悲鳴を上げ始める。こうなると、一樹としてものんびりと高みの見物とは行かなくなる。
唯に声をかけたい所だが、下手をしたら唯の集中力を削ぐことにもなりかねない。
今、唯は闇楓と同調しており、普通の状態ではない。万が一術の集中が解けたら、最悪の場合精神崩壊しかねないのだ。
「早く終わってくれ・・・」
一樹の祈りが通じたのか、ついに、岩中に広がった亀裂がその体を引き裂き始めた。
亀裂の間から漏れる光は強くなり、まるで昼間のようにあたりを照らす。ただ、その色が血に染まったかのように真っ赤な光なのが太陽の光とは違っていたが。
カッ!
岩肌が完全に崩れさり、その奥にあるモノが放った光は、一樹の視力を一時的に奪った。
やっと終わったと一樹が一息ついた時、唯は虚空を睨みつけていた。
その視線の先には、巨大な蛇。いや、頭が7つ有る巨大な生物が空中でとぐろを巻いていた。
「八叉の大蛇!」
ひきつった顔で叫んだ一樹に唯は頭を振った。
「違う・・・・あれは
一つの頭の大きさだけでも九羅座火をかるく越えるだろう。首(?)の太さも頭の半分以上はある。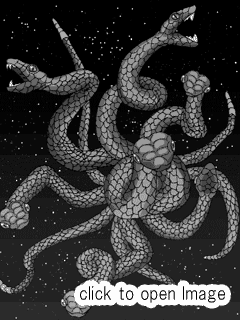
それが腹の部分から7つに別れて別々の方向に睨みを利かせている。
尻尾も七つに別れており、7匹の蛇が腹の部分でくっついたような、いびつな形をしている。
確かに見た目は恐ろしい姿をしている。しかし、本来、
「そなたは・・・・もしや”
唯の呼びかけに、”
「我が名を知っておるとは、お主等何者だ」
腹の底に響く声が誰何する。
「我らは白竜様にお仕えする者。
我は
共に竜命に従う者なり!」
「ほう・・・・すると、そなた等があのツインドラゴンと呼ばれている・・・・」
先ほどの敵意と殺意は薄れ、代わりに好奇が瞳に宿る。
「いかにも、その通りです」
南深螺の問いに答えて、言葉を続ける。
「何故にこの地を侵されるのか?
あなた様には、この地と海を治めるべき責務があられるはず」
唯が尋ねると、南深螺は激しい怒りを吐き出した。
「黙れ! 我に滅びを命じたのは貴様等、人間の方であろうが!!」
その怒りを受けて唯は眉をひそめた。
「貴様等人間が我が力の源たる聖域を破壊したのだ!!
我を滅ぼすというなら、それも良かろう!! なれど、その償いはしてもらう。
我に守られながら、ただの一度も感謝することなく、その恩を徒で返した礼儀知らずな者共に滅びを与えん!!」
「聖域を破壊した?」
唯は、その能力で聖域の在処を探した。
微弱な力を感じる。
弱々しい、今にも消えてしまいそうなモノ。確かにその力の波動は竜族の物のようだ。しかし、何という弱さ、何という頼りなさであろう。とても、大自然を律する竜族の聖域とは思えない。
そして、そこには巨大な建築物――海上空港――が存在していた。
”沖縄国際空港”
未来の発展のため、リゾート開発を促進するため。いろいろな理由がこじつけられて、建設にこぎ着けた4年越しの巨大プロジェクトであったが、そのために貴重なサンゴの多くが工事のさいに破壊された。
そして、空港が建設された場所が、南深螺の聖域だった。
人間がそこを空港建設のポイントにしたのは決して偶然ではなく、必然であった。
竜族の力の源はいろいろな種類がある。
高位の竜族は自らの力で世界を動かすことさえ出来るが、いくら竜族とはいえ下位の存在ではそうは行かない。
自分が仕えている上位の竜族から力を借りていろいろな神事を行う。
人間達がそういった場所を見逃すはずもない。
ただ、この空港の作られた場所は海産物の宝庫でもあるため、漁師達は必死になって反対したのだが、結局、金の力にモノを言わせた建設会社と利権ぼけの政治屋共に、ごり押しされてしまったのだ。
だが、最近、今までになかったような災害や小さな地震が頻発し、関係者達を悩ませている。
それが、聖域の力を失った自然の”反動”であるという事実に気づいている人間は殆ど居ない。
「我を忘れるのは人間共の勝手だ、それを責める気はない。
だが、我の存在を抹殺するというのなら容赦はせぬ。
滅ぼされる前に、滅ぼすのみ!」
そして、燃える怒りを唯にぶつける。
「いかに白竜王の慈愛を受けた汝等といえども、我の復讐を邪魔するので有れば容赦はせぬぞ!!」
「その力、どのような手段で手に入れられたのですか?
正当の竜族の力とはあまりにもかけ離れた物のように思えます。
さらには、この世界のいかなる存在にも属さぬ力のようですが?」
唯のその問いは、南深螺の怒りにかき消された。
「我の邪魔をするモノは容赦せぬ!! 失せろ!!」
大きく開かれた口から紅蓮の炎が九羅座火に迫る!
九羅座火はすばやく身を捻り、その炎から逃げ出すが、残る六つの首も鎌首をもたげて九羅座火を狙い攻撃してくる。
炎が闇を引き裂き、巨大な大気の渦が竜巻となる。毒の息をまき散らし、水を操って九羅座火を打ち落とそうとするが、九羅座火は器用にそれらの攻撃をかわし続けた。
「・・・・やはり、戦う以外にないか・・・・」
彼女にとっては同じ竜族に連なる者が相手だ。それが、蛟か人型かの違いがあるだけで親戚と言っても良い。
できれば戦いたくはない相手である。
それに、元々人間の方が悪いのだから、彼の怒りを向けられても天罰といえるかも知れない。
しかし・・・・
唯は心の中で呟いた。
彼は既に常軌を逸している。このままでは人間だけでなく、無関係な動物達までもが巻き込まれかねない。
唯にとって、怒りに全てを見失った同胞の姿を見るのは耐え難いものだった。
現に彼が吐き出す毒の息はあたりを汚染し、海の上に魚の死骸が浮き始めている。
そしてなにより、この世界の黄金律に従わない力を使い続ければ、この世界そのものが崩壊しかねない。世界は極めてデリケートなのだから・・・・
「やむおえぬか・・・・」
決心した唯は、すばやく九羅座火に命じた。
「九羅座火、すぐに一樹を連れて安全なところまで離れろ!」
「なりませぬ! 巫女姫」
「そのようなことをなされば、どのような結果となるか、巫女姫もよく御承知のはず!
お考え直し下さい!」
荒御禍と闇楓が必死になって唯を止めようとするが、唯は首を縦に振らなかった。
「彼の力は未知数だ。強さも性質もまるで分からぬ。
だが、蛟である以上、相応の力を持っていたはず。
その許容量を越えていないとしても、そうたやすく勝てる相手ではない。ましてや、力が分からぬとなれば、こちらとしては全力で当たるしかないのだ」
正論である。
強さの分からない相手であるならば、逃げるか、さもなくば、持てる力の全てを使って戦うのが戦いの正道だ。唯はそれをよく知っていた。
「しかし・・・・」
なおも何かいいたげな闇楓だったが、彼女の言葉を一樹が遮る。
「それなら、俺をここにつれてくるなよ・・・・」
無理矢理つれてこられ、見たくもない化け物と対面させられたあげく、「やはり邪魔だからどっかに行け」では余りの扱いである。
唯の気持ちもわからんではないが、あまりに勝手すぎる。と愚痴の一つも言いたくなる一樹である。
「それはすまないな。だが、運命と思ってあきらめろ」
同情の欠片もない台詞を吐いて、そのまま、九羅座火から中空へと舞い降りる。
足場のないはずの空中に危なげなくたたずむ唯。
彼女の周りにほのかな燐光が蛍のように舞っていた。
唯は本気だった。それも今までに無いような力を蓄えている。それを知って、もはや彼女を止めることが出来ないことを荒御禍も闇楓も知ったのだ。
「ええい! やむ終えぬ!! やるぞ、闇楓」
「・・・・承知」
ほとんど、やけくそ気味にまくしたてて、荒御禍は南深螺に雷禍を打ち込む。
諦めた口調で闇楓もそれに続いた。それを合図に、九羅座火はきびすを返すと一目散にその場から逃げ出した。
「まったく・・・・無茶なことを・・・・」
一樹は唯達の居た方向へと視線を向ける。そこでは、まばゆい閃光が走り、轟音が響きわたる人外魔境の戦場と化していた。
人間の自分には付いていけない世界が、常識の通じぬ異世界がそこに出現していた。
南深螺の力が彼女の理解を超えた物であったのは事実だ。それと同時に、南深螺も彼女の力が自らの想像以上の物であることを思い知らされていた。
特に片割れである一樹が離れたとたん、けた違いの力を発揮し始めたのである。
強大な力と力がぶつかりあう。その余剰エネルギーは海を引き裂き天空をこがさんばかりに暴れ回る。
(なるほど・・・・流石は噂に名高いツインドラゴンの
感心して、目の前の相手を睨む南深螺。
ツインドラゴン――双頭竜――。
人間の血を受け入れ、その力を弱めながらも人の社会にとけ込んだ竜族達の中に時折見られる奇形種。
本来一人の肉体に竜族の力とその力を制御する能力が備わっているのだが、この”双頭竜”は、別個体に力と制御能力が宿る物で、いわば二人で一人前という存在である。
ただし、二人で一人だが、力が劣ると言うわけではない。その逆なのだ。
力を受け持つ個体は、力の制御能力を持たない分、人間のキャパシティの限界ぎりぎりの力を持つことが出来る。場合によっては人間の限界を越える力を持つことさえ有るのだ。
しかし、その力を制御する能力がないため、単体でその力を使うと暴走を引き起こしてしまう諸刃の剣である。特に力が大きいため、その危険性は生半可な物ではない。
そのために、もう一方の制御を司る者のサポートが絶対に必要だった。
竜喘一樹はそれを望まなかった。
彼は自分は普通だと、何の力もない”まともな”人間だと信じて生きてきた。
しかし、いとこの竜峰唯の力が発現すると同時に、彼の中に”双頭竜”としてのもう一つの特性が目覚めたのだ。
双頭竜は互いに相手を呼び合う。
それがいやで、竜族としての修行もいっさいせず、唯の存在を無視し続けていたが、唯の力が巨大になるにつれ一族の誰の手にも負えない状況となった。
唯は一族の歴史上、稀にみる力を有した最強の双頭竜の片割れだったのだ。
こうなると、唯の力を制御できるのは彼女の半身たる一樹のみである。
いやがる一樹の意志を無視し、一族の長老達は、彼と唯を双頭竜として認めてしまった。
さらに悪いことに、彼の制御能力は体質に有り、特別な修行が無くても唯の側にいるだけで彼女の力を制限することが出来た。
それ以来、一樹は、事ある毎に唯に引きずられ、事件に巻き込まれ続けていたのである。
そして今、唯は生まれて初めて、実戦で単独行動を行った。一樹という”押さえ”のない自分がどれほどの力を持っているのか、いつまで自分の力に耐えられるのか彼女は知らない。
それは危険な賭であった。