[ 三妖神物語 外伝2 海辺にて・・・・ ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第1章 海辺にて
熱く燃える太陽。
どこまでも広がる紺碧の海。
焼け付く砂浜に美しい肢体があちこちに見える。
季節は夏!
夏と言えば海!
海と言えば!!
そう! 水着なのである!!
今、竜一と三人娘は康夫と共に沖縄の海で夏を満喫していた。
「しかし・・・・よく沖縄旅行なんて当てたもんだ」
感心しきって竜一は康夫を見た。
「俺のくじ運は宇宙一だからな!」
胸を張って豪語する康夫。そう、この旅行は康夫が町内の福引で当てた物だった。
”特賞−沖縄旅行二泊三日、4名様ご招待”
商品を買ってそのくじをもらったとき、竜一はためらうことなく買い物につきあってくれた康夫にそれをゆずった。
この世に生を受けて19年、参加賞以外の景品をもらったことのない竜一にとって、くじなど”会場に行くだけ無駄な物”以外の何物でもない。
そんな物の抽選に並んで貴重な時間を潰すくらいなら、家で本でも読んでいる方が遥かにましだった。
そのくじを渡して、その日家に帰ると、わずか2時間後に康夫から電話が入った。
『沖縄旅行当たったぞ』
「へ?」
あまりにも当たり前にそう言いのけた康夫に竜一は絶句した。康夫曰く今までくじで狙った物を外したことはないそうである。
ただ、惜しいことに彼のくじ運は物品に対しての物で、現金のくじには全く役に立たないらしい。
物が景品のくじならば、それがダイヤモンドの指輪でも確実に手に入れられるのだが、現金が絡むと、残念賞以外とれないのだそうだ。
それでも、物をもらえるだけいいと、竜一などは思うのだが・・・・
そして、せっかく当たったのだからと暇を持て余していた竜一を誘ったわけである。
恋人でも誘えという竜一に、康夫は「俺の心の恋人はメイル師匠だけだ!」と断言した。
はじめはメイルに声をかけたのだが、康夫の誘いをメイルはあっさり断った。
「あたいは盟主の使い魔だ。盟主の影の差さぬ所にあたいの存在すべき理由など無い」と。
竜一の行く所ならそれが地獄の底であろうと付いて行く、だが、彼の居ない所など天国だろうと御免だ。それが、メイルの気持ちなのだ。
というわけで、竜一を誘うことになったのである。
しかし、今ここにいるのは竜一と康夫とメイル・ミューズ・シリスの5人である。
一人分をどうしたのか?
言うまでもないことだ。ミューズは自腹を切ったのである。
何しろ、宝石だろうが金塊だろうが自由に作り出せる錬金術士である。竜一の懐を痛めないようにするくらい造作もない。
ただ、こういうのけ者になるケースを除いては竜一はそれを禁止している。
人間は一度楽なことを覚えてしまうと、奈落の底まで落ちていくことを竜一は良く知っていた。
ダメ人間にならないために、彼は、錬金術に頼ることは極力避けているのだ。
今回は、本当に例外的な措置なのである。
はじめは、シリスが家に残ると言った。
留守番が一人くらい居た方がいいだろうと。しかしそれを竜一は許さなかった。
「ところであの美女達はどうしてるんだ?」
姿が見えない三人を探しながら康夫が言うと竜一はサングラスに手を添えながら答えた。
ちなみに竜一がしているサングラスは、バーゲンで買った890円の安物である。
サングラスに大金をつぎ込むようなもったいないことなど、彼はしない。
「着替えに行ってる、じきに戻るだろう」
そう答えてまもなく、ビーチから男達の溜息と歓声が聞こえてきた。
まるで磁石に吸い付けられた砂鉄のごとく男達が群がり、人間の団子のような固まりがこちらへと近付いてくる。
近づくにつれ群がる男共が何を言っているのか聞こえてくるようになった。
「ねえねえ、彼女、俺とデートしない?」
「なにいってんだ!!
お嬢さん、俺とホテルのレストランで朝日を眺めながら乾杯しましょう!」
「ねえ、彼女! 彼氏いる? 俺が立候補しようか?」
「ぜひ、私とおつきあいして下さい!」
言いたいことを言っているが、言われている当人達は全く無視しているようである。
男達の声は聞こえるが、その主役の声はまるで聞こえてこないことからも、それは容易に想像できた。
しかし、男達は全く懲りずに、何とか口説こうと必死であった。
「ちょっと! 何してるのよ、秋一!!」
時折、女性が割り込んできて、人混みの中から男を引きずり出して文句を言う事まで起きている。
どうやら、彼女を放ったらかして口説こうとしている馬鹿もいるようだ。
「うるせなあ、あっち行ってろよ、麻由美」
「なによ、ちょっとかわいいからって、最低!」
「何を言う、”ちょっと”じゃなくって”ものすんごく”かわいいだ!」
「浮気者ー!!」
バチーン
盛大な音を立てて男の頬に赤い痣ができあがる。しかし、男は凝りもせず、頬に元恋人の絶縁状をつけたまま再び人混みの中に潜り込む。
男に盛大なびんたをくれた女性は、怒りに肩を振るわせて、さっさと、その場を立ち去った。
「・・・・罪な奴等だなぁ・・・・」
あまりにもすさまじいこの様子に竜一は頭を抱えた。
「もしかしたら・・・・、あいつ等をつれてきたのはとんでもない間違いだったかも知れない・・・・」
頭痛さえ感じながらそうぼやくが、もともと、メイルが目当ての康夫に招待されたのであるから、これはもう仕方がない。と、その元凶である康夫が笑う。
「これで、いくつのカップルを壊したのやら・・・・」
楽しげに笑う康夫を恨めしげに竜一が睨む。
「・・・・笑い事じゃねえぞ・・・・このままじゃ・・・・」
恋仲破壊魔──カップルバスターズ──なんて名前まで付けられかねない・・・・
冗談のようなことを考えて、本気で頭を抱えてしまった竜一である。
ただでさえ人だかりが出来ているところに、そんな騒ぎが起きるのだから目立たない方がおかしい。何が起こったのかと野次馬共が群がり、人間の団子はさらに巨大化する。
だが、その原因となっている人物全員を見ることが出来るのは中心付近にいる者達だけだった。
ほかの外側にいる男達は誰が中にいるのかよく分からない。ただ、一人だけ飛び抜けて身長の高い女性が見えているだけだ。
その女性の美しさだけでも、男達を引きつけるには十分すぎる物だったが・・・・
「なあ、何がいるんだ」
「すっげえ美人がいるんだってよ」
「そんなに美人なのか?」
あちこちから聞こえる声。そして、さらに集まってくる男達。
「こりゃ、関係者としられたらとんでもないことになるな・・・・」
思わず他人のふりを決め込む竜一だが、そうは問屋がおろさない。
人の塊はどんどん自分達の方へと近づいてくるのだ。
勿論、原因となる者達が竜一の所に来ようとしているのだから、当たり前の話ではある、しかし、この人集りは尋常ではない。
もしも、これで彼女たちとの関係がばれでもしたら彼等に袋叩きにあうこともあり得る。
嫉妬に狂った人間に理屈など通用しないのだ。
「シリスやメイルはともかく・・・・ミューズの奴、絶対に遊んでやがるな・・・・」
苦々しく竜一は呟く。
ミューズがその気になれば、そこら辺の男共など近づくことさえ出来ぬ程の威厳と威圧感を出すことが可能だ。
彼女達は、女神なのである。その力と威厳によって、鈍感な人間達でさえ畏怖せしめるほどの力を持っているのだから。
勿論、シリスやメイルもその気になれば、人間達を近づけさせない存在になることは出来るが、それをしないのは別に彼女達が遊んでいるからではない。
それはあくまでも、女神としての顔なのだ。
それは、異界の女神としての彼女達の一面。この世界の正式な女神でない彼女達にそれをする事は許されない。
今の彼女達が見せることの出来る顔は、竜一の”使い魔”としての顔であり、竜一を守る”戦士”の顔と、竜一の家族として、”女”としての顔だけだ。
そして、今、男達をもてあそんでいるミューズは、女としての顔を見せているに違いない。
「俺・・・・知らねえーっと」
そう言って逃げようとした竜一を、後ろから捕まえた者がいた。
抱きしめられた竜一の後頭部が、豊満な柔らかい物に挟まれる。
「どこへ行くのぉ、竜一ぃ?」
甘い声でじゃれつく様は、まさに、でかい猫そのもの。
もっとも、猫などと言ったらへそを曲げてしまうだろう。
美しい漆黒の髪を背中の中程までのばした女性。白い線が胸から腰に向かって斜めに描かれている真っ赤な水着を着込んだ美女が竜一を抱きしめる。
「ミ・ミューズ! よせ!」
あわてて怒鳴る竜一だが、ミューズは笑ってそれを無視した。
「やだ、今更照れること無いでしょ、竜一」
「おいおい、ミューズ。そろそろ離してやったらどうだ?
竜一の顔が赤くなってるぞ」
二人のじゃれあいに、あきれたように声を掛けてきたのはスカイブルーの鮮やかな水着を着た、褐色の肌にショートカットの金髪の大柄な美女、メイル。
その長身はこの浜辺にいる誰よりも高い。2mは優に越えている彼女は、その長身と美貌で異常なまでに目立ちまくっていた。
引き締まった無駄のないその肉体は、美しさと同時にすさまじいまでの戦闘力を秘めた代物で、普段着の彼女に言い寄る無謀な男など、一人しか存在しない。
どんなに鈍い男でも、潜在的なその力を、恐ろしさを本能的に感じるのであろう。
しかし、夏の海という舞台のせいか、はたまた水着を着たためにメイル自身が開放的になっているのか、今日の彼女からは、いつもほどの威圧感は感じられず、それどころか、肉体美の色気まで感じられる。
そのために、珍しく彼女も男達の興味の対象となっていたのだ。
さて、ミューズとメイルが竜一を名前で呼んでいるのは、竜一の命令だった。
いくらなんでも、人前で”マスター”だの”御主人様”だのといわれてはあまりにも恥ずかしすぎる。
想像力過剰な人間なら、とんでもない方向に想像が膨らんでしまうことだろう。
そのために出かける前に口を酸っぱくするくらい名前で呼ぶようにと彼女達に言っていたのだ。
そのかいあって、ミューズとメイルは竜一を抵抗無く名前で呼べるようになったのだが・・・・どこにでも例外というものは有るのである。
「ミューズ、それくらいにしておいたほうがよろしいのでは?
竜一様も困っていらっしゃいますし・・・・」
他の二人が名前を呼び捨てに出来るのに対し、シリスにはやはり遠慮がある。
なんとか名前で呼ぶことは出来たのだが(これも、相当苦労してのことらしい)名前に”様”付けではやはり恥ずかしい。
しかし、既に竜一もあきらめていたのでもう何も言わない。
これが彼女の精いっぱいなのだから・・・・
ちなみに、他の二人が水着に包んだ自分の体を惜しげもなくさらしているのに対し、シリスは未だにタオルケットで体を隠している。相当に恥ずかしいらしい。
メイルの苦笑とシリスの非難の声にもミューズは動じず、それどころか見せびらかすかのようにさらにきつく竜一を抱きしめた。
当然周りで見物している男達はおもしろくない、たちまちブーイングの嵐である。
「お嬢さん! そんな男のどこがいいんだ? 俺の方がかっこいいのに」
「うおおお! うらやましいい!! 俺もあの胸の谷間に挟まれてみたいい!!」
「お姉さん! 俺と夜明けのコーヒーをベッドの中で飲みましょう!!」
口々に勝手にわめく男達、いい加減、竜一がうんざりしてきた頃、メイルが男達を眺める。
「・・・・ちぇ、しょーがねーな・・・・」
「お嬢さん、もしもおれとデートしたくなったら呼んでね、すぐに駆けつけるから。
あそこのホテルの911号室に泊まってるから」
「俺のTEL−Noはねえ・・・・」
メイルに軽くにらまれた男達は、不思議と素直に彼女たちから離れていった。口々に好き勝手なことを言いながら。
うるさい野次馬達が過ぎ去った後、やっとの事でミューズの悩殺攻撃から脱出を果たした竜一は、改めて、海をバックに浜辺にたつ彼女たちを見つめた。
・・・・美しい光景だった。
周りにいる他の女性達が、ただの背景にしか見えないほどに彼女たちは魅惑的だった。
ミューズの水着は多少胸のカットが深い程度の極普通の物だった。特にハイレグと言うほどの物ではない。むしろ腰のカットは最近の物にしては控えめなほどの物だ。
だが、彼女が着ると、普通の女性がスーパーハイレグを着た以上に足のラインが美しい。
元々、ずば抜けてスタイルがいい彼女達である。普通の水着を着てもハイレグ以上に魅力的な姿を演出できるのだ。
むしろ、ハイレグを着ると足が異常に長くなりすぎるため、かえってバランスが悪くなるほどだ。そのために、ミューズは絶対にハイレグ水着を着ない。
また、俗に言う超ビキニと呼ばれるタイプの水着も彼女は着ない。彼女に言わせるとあれは露出狂のたわごとで、水着とは認めないとのことである。
その隣りに立つメイルもなかなかの物だった。水着のデザインそのものはミューズよりさらに控えめで、スクール水着ではないかと思わせるほどに色気も露出も無視された物である。
しかし、メイルのずば抜けた長身とそのプロポーションのためか、水着のデザインを完全に無視した魅力があった。その小麦色の肌と黄金に輝く髪の毛がスカイブルーの水着と絶妙のコントラストを演出している。
ただ、その体格と引き締まった肉体は色気というより、健康的な魅力を感じさせるようだが。
しかし、そんな二人に対しシリスは未だにタオルケットをかぶっていた。
そう、着ているのでも、上に羽織っているのでもなく、頭からかぶっているという表現がぴったりの有り様だった。
体のサイズより二周り以上は大きいタオルケットをかぶり、それは完全に足下まで隠している。
夏の海に来て、そんな格好で海辺を歩き回るような人間など彼女以外にいるはずもなく、これ又、他の二人とは別の意味で思いっきり目立ちまくっていた。もっとも、この場合は、ただ単に周りから浮いているとも言えるのだが・・・・
「シリス・・・・この暑いさなか、しかも海に来てまでそんな暑苦しいかっこしてどーする?」
あきれ果てたような竜一の言葉にシリスは少し困った顔でうつむいた。
「ですが・・・・」
「せっかく着替えたんだろう? 見せてくれよ」
「はい、でも・・・・」
竜一の言葉に、なおもシリスはためらった。
「何もったいぶってんのよ!」
何時の間にシリスの後ろに回ったのか、そう言うのと同時にミューズがシリスのタオルケットをずりおろす。まさしく電光石火の早業である。
「きゃああ!」
いったい何が起きたのか、一瞬シリスは状況を把握できなかったが、自分の姿を見て両手で体を隠すようにして、恥ずかしそうにしゃがみ込んでしまった。
「・・・・・・・・」
「・・・・・・・・」
どんな水着が出るのか期待に胸を躍らせていた竜一と康夫は・・・・その場に凍り付いていた。
こんな、”恥ずかしい、見ないで!”と言うポーズをするのだから、どんな水着を
着ているのかと男なら誰もが期待せずにはおかないだろう。しかし・・・・
どれほど時間がたったことだろう。ようやく我に返った康夫がぽつりと呟いた。
「・・・・ダイバー・・・・スーツだな・・・・」
「あ・・・・ああ」
康夫の言葉に竜一も力無く答える。
そう!
タオルケットの下から現れたシリスの姿は、ダイバースーツそのものだった。
首から足首までぴっちりと覆い隠す黒い布地。腕も手首まで完全に覆い尽くし、露出されているのは手と足と顔だけ。
頭の部分が無いことと布地が少し違うことがダイバースーツとの僅かな相違点だった。
「シリス・・・・このくそ暑いのに・・・・そんな暑苦しい格好をして・・・・どーする・・・・」
先ほどと同じ台詞を疲れた口調で竜一は呟いた。あまりのことに虚脱感に襲われる。
「・・・・俺は師匠と泳いでくる・・・・」
疲れたようにそう言うと、康夫はメイルに近づき、いきなり両手を握りしめた。
「師匠! お美しゅうございます!! 一緒に泳ぎましょう!!」
いきなり大声でまくしたてられ、メイルはめいっぱい渋い顔をして見せたが、康夫は全く頓着せずに続ける。
「ああ! この私めのために、このようにお美しいお姿をしていただけるとは沢田康夫、人生最大の幸福!! もはや、思い残すことは有りません!!!」
「そおかい・・・・」
額に青筋を立てて懸命に怒りをこらえていたメイルは康夫が台詞を言い終えると同時に吠えた。
「ならば! 星になれ!!」
ドキャアア!
メイルの右アッパーが康夫の顎をとらえ、康夫は空のかなたへと吹き飛んだ・・・・
「まったく、うっとおしい・・・・」
メイルがわずらわしげに髪を掻き上げると、ミューズが楽しげに笑う。
「あらあら、何もそんなに邪険しなくても・・・・怪我でもしたら大変でしょう?」
「あの程度でどうにかなるような柔な男か」
メイルは苦笑して、飛んでいく康夫に視線を送る。メイルのパワーに急上昇を続けていた康夫はやがて重力の法則により弾道軌道に入る。そして・・・・
ぱっしゃあん・・・・
遥か沖で小さく水柱があがった。
もしも、間近で見ていればかなりの大きさの水柱と大きな効果音が聞こえていたことだろう。しかし、かなり遠くで起きたそれは、とても小さく、注意しなければ見落としてしまう程度の物だった。
「成仏せいよ」
その一部始終を見ていた竜一は哀れな親友に合掌した。
思えば、康夫がメイルをいきなり師匠呼ばわりし出したのはゴールデンウイークの事だった。
有る組織が、懲りもせず竜一達にちょっかいを出したとき、たまたま(極めて必然的に)居合わせた康夫もそれに巻き込まれ(進んで首を突っ込み)、うやむやの内に彼女達三人と出会う事になった。
その時、メイルの飛び抜けた力を直感で知った康夫は、それ以来、彼女を師匠と呼んでまとわりついていた。
口ではいろいろと文句を言っているメイルだが、それなりに楽しんでいるようである。
現に、先ほどのアッパーも十分に手加減していたのだ。
ただし、その”加減”はあくまでも康夫や三人娘のレベルの事で、普通の人間があんな強力な一発を食らったら、頭蓋骨が粉砕され、100%即死間違いナシというとんでもないしろものである。
康夫はメイルが(手加減をするとはいえ)人間形態で殆ど互角につきあえる(ドツキ合える)、とんでもない実力の持ち主だった。
はっきり言ってそのレベルは人間どころか神や魔王のレベルの代物であるが、康夫自身は全く自覚がなく、竜一達も説明はしなかった。
ただ、康夫は自分と互角以上の存在が居ることに感動し、メイルを”師匠”と勝手に呼んでなついてしまっていた。
メイルやミューズも彼の異常な力を不思議に思ったが、それほどこだわらなかった。
実際に”マスタードラゴン”という規格はずれの人間の前例を見たことがある彼女達にとっては、この世界にマスタードラゴン級の超人、いや”超神”が一人や二人居てもおかしくないと考えていたのである。
ただ一人シリスだけが、彼の力の巨大さに違和感を感じていたが・・・・
「まあ、哀れな康夫のことはいいとして・・・・」
再び視線をシリスに戻し深いため息を付く。シリスは既に、タオルケットを”かぶり”なおしていた。
「シリス・・・・せっかく海に来たんだ、もっと楽しめよ」
竜一の嘆息にシリスは寂しげなほほえみを浮かべた。
「わたくしは十分楽しんでおりますわ。・・・・それにわたくしには肌を露出することは許されませんもの・・・・」
その物憂げな表情、寂しい溜息。
シリスと竜一の周りだけ、急に日が陰ったかのように暗く重苦しい雰囲気になる。
「・・・・シリス、”私”の封印が信用できないのかな?」
静かな口調。しかしそれを聞いてシリスは硬直した。
「い・・・・いえ、そのようなことは決して・・・・ですが、万が一という事もあり得ますし・・・・何よりわたくし自身、こう言うことは苦手なものですから。」
しどろもどろにシリスは答える。
今、目の前にいるのは普通の人間”竜一”ではない。彼女達にとって絶対の主人”マスタードラゴン”だった。
「そんなに信用がないのかな・・・・私の力は・・・・」
再びため息を付く竜一、いや、マスタードラゴンにシリスは少し悲しそうな表情でうつむいた。
「・・・・酷いですわ・・・・御主人様・・・・そんな言い方・・・・それでは反論できませんわ・・・・」
「シリス、お前が自分の力を警戒するのは分かる。
しかし、術をかけたとはいえ、布きれ一枚でどうにかなるような力ではないだろう? お前の力は。
それほど、神経質にならなくても言いと思うがな、私は」
シリスはためらいがちに呟いた。
「・・・・それは・・・・そうかも知れませんが・・・・」
すると、いきなり”竜一”は笑って言い返す。
「なら、楽しもう。何か有ったら”俺”が責任を持つから。
お前は心配しなくてもいいんだよ」
何か言おうとしたシリスだったが、彼の笑顔を見てあきらめた。又嫌だと言ったところで彼が納得するわけがない、ここは素直に従おう。そう思い直したのだった。
「はい、それでは着替えてきますね」
本当は着替えなど持ってきてはいない、彼女達は自分達の力で水着を作ったのだ。
だから、わざわざ更衣室に戻らなくても良いのだが、人前で力を使うのはさすがに問題がある。非常事態でもない限り目立たないようにするのは当然のことである。
そして、再び更衣室から出てきたシリスはやはり、タオルケットをかぶって体を隠していた。
「あの・・・・やはりこれは・・・・」
竜一の顔を見ながら言うと竜一は力強く頷く。
「うん、脱ぐの」
「はあ・・・・」
力のない溜息。
そして、自分からおずおずと脱ぎ出す。さすがに先ほどのミューズの行動が効いていたのだろう。
覚悟が出来ていない内に他人に脱がされるよりは覚悟を決めて自分で脱いだ方がずっとましだ。
タオルケットを脱いだシリス。それを見て竜一はほうっとため息を付いた。
「ほおぉ・・・・これは・・・・また・・・・」
シリスの水着姿、それはとてつもなく貴重なものだ。
何しろ、真夏の暑い盛りでさえ長袖にロングスカートでぴっちりと体を覆い隠し、顔と手しか露出しないと言うほどの露出恐怖症(!)なのである。
とにかく見ている方が死にたくなるほど暑苦しい格好を平気でする彼女が、これほど肌をさらすのは極めて貴重なことだった。
「あの・・・・何かおかしな所がありますか?」
竜一の視線に恥ずかしそうにシリスが尋ねる。
「いや、そんなことはない。
ただ、お前がそんな姿をするのが珍しかったから、つい・・・」
その言葉にシリスは顔を真っ赤にした。
シリスの水着、それは先ほどのダイバースーツもどきから腕と足の部分を取り去っただけの極めてシンプルな物だった。
胸のカットなど無いに等しく、首の根本が見えている程度、腰もカットなど全く入っていない。
はっきり言って中学生のスクール水着より色気のない代物である。
しかし、水着自体には何の色気もないが、シリスがそれを着たとたん、なかなかに男心をくすぐる、ある種の色気を演出するのだ。
シリス自身は地味にするために色を黒のままにしたつもりなのだろう。しかし、その黒一色の飾り気のない布地が、万年雪より白い彼女の肌と月のごとく輝く銀の髪の美しさを引き立てる。
そして、彼女の白い肌と黒い水着のコントラストは下手なトロピカルカラーの水着など足元に及ばないほどの輝きを持っていた。
もしも、これで、胸元と腰のあたりにちょっと大胆なカットが入っていれば完璧に悩殺ものである。
この場に水着デザイナーがいてシリスの姿を見たら、自分の存在意義を見失うことだろう。
女性を美しく演出するのが水着の役目であるはずなのに、その役目を全く果たしていないはずの水着に色気さえ感じさせるさせる程の力があることを知ったら、自分の人生に疑問を感じていたかも知れない。それほどの魅力が彼女の水着姿にはあった。
ただ、シリス本人は自分がどれほど男を刺激しているのか、全く気が付いていないようだった。
当然、男どもが再び集まってくる。
先ほどはシリスがどんな女性なのか彼等は殆ど知らなかった。小柄な体をタオルケットで完全に隠していたため、女性かどうかさえ分からなかった有り様なのだ。
しかし、美しいその姿を見たとたん男の本能が彼等を駆り立てる。
ちなみに他の二人にも思い思いに男達が群がってくる。
真っ先に堪忍袋の尾が切れたのはメイルだった。
「いいかげんに・・・・」
そこまで怒声を上げかけた彼女だったが、最後まで言えなかった。
轟音と共に白波が立ち、海を切り裂いて飛び出したモノが、彼女に群がった男どもをあっと言う間に吹き飛ばしてしまったのである。
「ええい! 俺の師匠に近づく奴は容赦しねえぞ!」
「誰が誰の師匠だって?」
「勿論、あなたが俺の師匠です!!」
メイルの白眼視をモノともせず、康夫はきっぱりはっきり言いきった。
「あの二人なかなかお似合いね」
竜一の側にちゃっかり避難していたミューズは康夫とメイルの漫才を眺めてそう呟いた。
「誰がお似合いだ・・・・」
メイルが唸りながら否定すると、康夫がいきなりメイルに抱きつく。
「そんな! 師匠!! 冷たいことを言わないで下さい!!
不肖、沢田康夫。師匠のためなら、例え火の中、水の中・・・・」
「そんなに好きなら、もう一度沈んでこい!」
メイルに投げ飛ばされ、再び明後日の方向に吹っ飛んでいく康夫。
「成仏しろよーーー」
「薄情者おおおぉぉ!!」
竜一のはなむけの言葉に康夫は力一杯、感謝した(笑)
ぱっしゃああぁぁん・・・・
そして、小さな水柱が遥か彼方の沖合いに立つのであった・・・・
それを見て、笑い転げる竜一とミューズ、それから少し離れたところでは、男達に囲まれておろおろしているシリスが居る。
二人の姿を笑っていたミューズだが、災厄(?)は彼女にも襲いかかった。
ひた・・・・
何かかが肩に触れている、それに気づいてふと振り向いた彼女の目に、それが映った。
「きれいなお姉さん、名前と住所と電話番号を教えて」
いきなりそう言ったのは高校生くらいの引き締まった体の青年だった。
顔は整っており、かなりのハンサムである。ただ、その表情が少し軽薄そうなのはマイナスポイントであろう。それでも、ひいきなしにハンサムだ。
十人の女性に声をかければ、七人までが付いてくるだろうという位のいい顔をしているが、あいにくミューズのタイプではない。
もっとも、ミューズにとっては顔などどうでもいいことだったが・・・・
「人に名前を尋ねるならご自分の名前を名乗っていただきたいわね」
皮肉を込めてそう言うと、彼は背筋を伸ばして、答える。
「
本当に名乗るとは思っていなかったミューズは、一樹と名乗った少年に興味を持った。
「お友達になってどうするの?」
「勿論、恋人になってもらって、いずれは結婚まで・・・・いてぇ!!」
一樹は最後まで言葉を続けることは出来なかった、彼の耳を力一杯引っ張った者がいたのである。
「何をへらへらしている、一樹」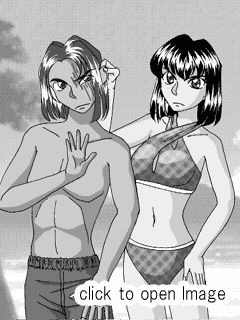
一樹をにらみつけてぶっきらぼうに吐き捨てる。
年齢は一樹と同じくらい。背丈も殆ど同じくらいの黒い髪を肩で切りそろえた、冷淡な面差しの美女がそこにいた。
「ゆ・・・・
先ほどまで軽薄さを絵に描いて額縁に飾っていたような一樹の顔が、恐怖に青ざめひきつっている。
「どこで油を売っているかと思えば・・・・、こんな所でナンパとはねえ・・・・」
それだけ言うと有無を言わさずに引きずっていってしまった。
「いやだあぁ・・・・化け物退治なんか嫌だあぁ・・・・俺はかかわりたくない」
引きずられて行く一樹は必死になって抵抗していたが、見かけに寄らず唯と呼ばれた美女の力は強いらしい。砂浜に跡を残しながら一樹を引きずっていってしまった。
「化け物退治?」
その様子を見ていた竜一だが、一樹が残した断末魔(!)の声が気になっていた。
既に、日は暮れてあたりには夜の帳が降ろされていた。
ホテルの自室でのんびりしている竜一の所にミューズが訪れた時、時計の針はPM8:00を指していた。
「おいおい、夜這いにくるにはまだ早いぞ」
竜一がそう言うと、澄ました顔でミューズが答える。
「心配無用よ。今回は下見だから」
なかなかどうして、ミューズの方がこう言うことにかけては一枚上手である。
彼女の冗談に笑った竜一はすぐに表情を改めた。
「さて、あの話だな」
「ええ」
ミューズは頷いた。
”あの話”、ミューズが訪れたのは昼間のあの奇妙な二人のことだった。
一樹と名乗った少年の言葉”化け物退治”の事が奇妙に心に引っかかっていた竜一はミューズ達に調査を指示していた。
ミューズにしてみればわざわざ調べることでもない。彼女に出会ったときから、そしてこの浜に来てからすぐに気づいていたことだった。
「最近、このあたりに化け物が頻繁に出ているらしいわ。それで、その退治に彼女達が来たのね」
「化け物・・・・ねえ」
化け物が出たなどと常識では考えられない事だ。竜一自身、ミューズ達の存在を知らない頃にそんな噂を聞いていたら、笑い飛ばしていただろう。
しかし、彼は既に非常識の日常にどっぷりと肩まで浸かってしまっていた。
そのため、そんな非日常的な会話にも全く違和感を感じなくなっていたのである。
「しかし、今時そんな話が有るとは・・・・悪質な流言じゃないのか?」
何かを隠すために有りもしない事を並べ立て人々の気をそらしたり遠ざけたりするのは、陰謀騒ぎなどではよくあることだ。竜一もその手の事かと思っていたが、
ミューズに力一杯否定された。
「違うわ、本物の”神魔”がこの沖合いには住んでるのよ。
今までもいたことはいたけど、人間に関わりを持っていなかっただけでね」
神魔とは、神や魔物を示す言葉であり、正体の分からない霊的存在や高次元生命体を呼ぶときにミューズが使う言葉だ。
人間の常識に反した存在をミューズはそう表現する。
普通の人間は”化け物”と言うところだろうが、そういう言葉を竜一は嫌っていた。
肩をすくめて彼女は続ける。
「たぶん、何らかの理由で活性化したんでしょうね。そして、今までの恨みをはらそうとしてるんじゃない?」
実の所、最近のニュースでは妖怪や神魔の話題がひっきりなしにとりだたされていたのだ。
大半の人間たちはそれを本気にしておらず、たいてい幻覚・精神異常ですまされていたが、それが事実であることをミューズ達は知っている。
世界中の妖怪・魔物・精霊の類が最近になって活性化しているのだ、それも急激に。
少しずつ伝説やおとぎ話が現実と化し始め、世界は今や、最先端科学世界から神話世界へと逆行し始めているのである。そして、その原因が他ならないミューズだった。
ミューズは、人間によって破壊され尽くしたこの世界の寿命を、あと30年と診断した。
その寿命がくれば、この世界は人間の欲望を支えきれなくなり、破滅の歌を歌うことになる。しかし、30年という時間は短すぎる、それは彼女の主人たる竜一の寿命よりも短いだろう。
他の人間達のことなど知ったことではないが、主人である竜一が天寿を全うできずに世界の破滅に巻き込まれることは、彼女にとって許しがたい事である。
彼女達の力で別世界に逃れるという手もある、あるいは、今の世界が崩壊した後改めて世界を再生することも、”竜一のための”新しい世界を作ると言うことも可能だった。が、それは、家族や友人を見捨てることにもなりかねない、そして、自分だけ助かるという思考パターンは竜一にはない。
寝覚めの悪くなるようなことを竜一は断じてしないのだ。となれば、彼女に出来ることはこの世界の寿命をせめて100年程度までのばすことくらいである。
そのために、自分の魔力を放出して、この世界の自然界の力を高め、世界を、地球そのものの寿命を延ばしたわけだが、それは結果的に自然界の力の具現体でもある精霊や魔物達を活性化させる事にもなったのだ。
そして、彼等が活性化すれば、当然人間にちょっかいをだしてくる者達も現れる。
特に人間に傷つけられ踏みにじられた存在達にとっては、それは正当な行為なのだから。
そうなることはミューズにも十分に分かっていた。
いわば、これは選択問題だった。
このまま、精霊や魔族の事を忘れて己の欲望の赴くままに30年で滅びるか、彼等の力と驚異を恐れながら、より長い時間を生きるか。
究極の選択であったわけだ。
ただ、それを決めたのが全人類の総意ではなく、一個人の使い魔の決定であるところに多少の問題がないでもないが・・・・
だが、今の所、世界中の魔物や精霊達はそれほど大きな騒ぎを起こしてはいない。
カーニバルのパレードに紛れ込んで騒いでいたとか、何をするでもなく、空中に浮かんでいたとか、せいぜい、人を脅かす程度のモノだ。
それは日本でも同様で、祭りの出店でいつのまにか食べ物が無くなっているとか、神社のお供え物が無くなっているとか言った、悪戯とも言えないほどのささやかな悪ふざけが有ったくらいのものだ。
もっとも、祭りも神社もその地方の神や魔物に対しての感謝と畏怖の現れのようなものだから、有る意味ではそれは精霊や妖怪達にしてみれば正当な行為であり、悪さとは言えないかも知れない。
本来なら、人間達にそれなりの驚異となっても良いはずの魔物達さえ、ずいぶんと大人しい。
だからこそ、それほど大きな騒ぎにならず、集団幻覚程度で収まっているのだ。
魔物達が人間に手を出さないのは、別に人間に遠慮しているわけではなく、れっきとした理由があった。
魔物や妖怪達が大人しいのは第一に、彼等に力を与えた存在に対しての礼節と敬意の表れであった。
精霊や妖怪、魔物達はミューズの存在と彼女が仕える竜一の事を知っていた。彼等に対しての敬意を示して、人間に対して過剰な干渉を控えていたのである。
そして、もう一つの理由は、この世界に干渉しようとしている”外敵”の存在だった。
異世界からの侵略者。
まるでSFのような話だが、それは起こっていた。それも何千年も前に。
それは人間達の知らないところで着々と進んでおり、既に世界の殆どが彼等、異世界の者達の手に落ちていた。それは、精神世界、神話世界の破壊と支配であった。
もしも、物質的な現実世界を彼等が支配しようとしていれば、人間達はそれに気が付いただろう。反対もしただろう。
しかし、彼等が望んだのは物質世界ではなく人間の精神世界の支配権だった。
そして、太古幾多の神々や魔物達の間に起こった事と同じように、人々の心を支配する宗教の一つとして、それは、この世界にやってきた。
”唯一神の支配による完全なる調和のとれた宗教世界”
”他の全ての神とは魔物であり、神とは唯一にして絶対なる”ヤハウェイ”がおわすのみである”
”他の神を信ずる者、即ち魔物の使徒。それらを滅ぼすのは善なる神のよみしたもう事”
それは、人間の悪しき考え”選民思想”に火をつけ、瞬く間に世界を席巻した。
”人間こそが神が作りたもうた存在の中でもっとも優れた選ばれた存在。ゆえにこの世界の支配権は神の子たる人間にゆだねられている・・・・”
この考えは人間にとってはこの上なく好都合だった。
大自然の存在すべてを神とし、それを敬う考えでは、この世界を自分達の思い通りにすることは出来ない。特に、権力者や自然を破壊して富を得る者達は驚喜した。
そして、異世界のそれを自分達の神と崇め、それ以外の存在を邪悪な者と決めつけ、世界を人間の、自分達のものとするために作り替えていったのである。
あまたの神々・精霊の信者達は自分達の神を守ろうとして、彼等の容赦ない迫害をうけ、次々と滅ぼされていった。
そして、現在にいたり、異世界からの侵略者。いや、侵略神はこの世界の殆どをその汚れた手中に収めることに成功していた。
人々との心の交流と信仰心を失った精霊や神々、魔物や妖怪達は人々の記憶からも追い出され、いまや、物語の中にかろうじて面影をとどめているにすぎなかった。
力のある神々や魔物・精霊や妖怪達はそれぞれが存在していた神界や魔界、”隠れ里”と呼ばれる精霊界に去り、
今、再び目覚めた彼等はその力を蓄える必要があった。再び異世界の神が自分達の存在を抹消しにくるその時のために、そして、人間達と自分達の絆を再び作り、この世界に存在をとどめておくためにも・・・・
それ故に、この世界の妖怪や魔物達はまだ、それほど大きな騒ぎを起こすことはなかったのだ。
もっとも、竜一に言わせれば、こんな荒んだ、人間に破壊され尽くした世界に何の未練が有るのかと言うところだ。
もしも、自分が彼等の立場なら人間の絆など作る気にもならないだろう、と。
それが真実であるかどうかは、竜一自身にも分からないことだったが・・・・
だが、どうやらこの沖縄でそんなことはお構いなしに、暴れまくっているものがいたらしい。
さすがにミューズが来ているこの浜辺では悪さはしていないようだが、他の場所ではいろいろと噂が流れ続けている。その存在は今も暴れ続けているのだろう。
それはそれでもかまわないとミューズは思っていた。今までさんざんこの世界を踏みにじってきた人間達にとっては良い薬だとも思っている。ただ、その存在の力に異質なものが混じっているという事にミューズは懸念を感じていた。
本来ならこの世界に存在する神や魔物、精霊や妖魔、妖精や妖怪などには、この世界の黄金律に従った力が備わっている。しかし、先ほどから感じている神魔の力にはこの世界の黄金律を無視したような力が感じられていた。
それが、ミューズには解せない。
「で、その神魔のことはどうするつもりだ、ミューズ?」
竜一は”化け物”という言葉を嫌っていた。それは、あくまでも人間達の側から見た言葉である。自分達人間こそが地上の支配者だと勘違いした驕った考えから生まれた歪んだ言葉だ。
人間など、この世界の借家人、いや寄生虫にすぎず、人間達が”化け物””魔物”と呼び恐れる存在こそが、この世界の真の支配者であることを竜一は熟知している。
竜一の疑問はもっともだ、だが、ミューズは他人の事などいちいち関わるつもりはなかった。全く感心のないそぶりではっきり言いきる。
「私は干渉するつもりはないわね。
退魔士の彼女達が勝つか、神魔が勝つか、それは自然界が、弱肉強食の掟が決めることよ。私が干渉すべき問題でもないし」
「放っておいて良いものだろうか・・・・」
竜一のその言葉を聞こえないふりをしてミューズは無視した。
「じゃ、私は部屋に戻るから」
部屋から出ていきまぎわに、扉を閉めながらミューズは竜一に笑った。
「奴が恐かったら添い寝して上げるから、遠慮無く呼んでね」
「あほ!」
竜一の投げつけた枕はミューズの閉めた扉にぶつかり、虚しく床に落ちた。