[ 三妖神物語 第一話 女神降臨 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第六章 冥神悩む
「で、結局あの女どうなったんだ?」
あれから、無事に自宅に戻った竜一は、傍らにいる可愛い同居人に声をかけた。
ちなみに今の姿は、見慣れた黒猫の姿であるが、その体格は二回りほどおおきくなっていた。
元々変幻自在であるが、猫の姿が、彼女本来の姿に最も近いものであった。
勿論、人間の姿でも彼女自身にとっては何の問題もないのであるが、竜一にとっては大問題である。
といのも、何しろ、ミューズの人間態は、とにかく美しい、ひたすらいい女なのである。
そんないい女と女性にあまり免疫のない竜一が同じ部屋にいたりしようものなら、はっきり言って、何時、理性のかせが弾け飛んで、彼女に襲いかかってしまうかわからなかった。
竜一は、自分の理性と自制心に欠けらほどにも自信が無かったのである。
無論、もしも相手が他の男だったなら、ミューズがおとなしく手込めにされる訳が無い。
雷を落とされて黒焦げにされるか。それとも、蛙や鼠にでもされるか。
とにかく、ろくでもない結末に成ることは間違いない。何しろ彼女は魔道の達人であり、”雷神”の異名を持っているほどなのだから。
ところが、相手が竜一になると、ミューズはやたらと無防備になる。
いや、無防備どころか、わざと隙を作って竜一を誘惑している気配さえある。
(そういえば、あっちの世界でも、ミューズ達は私を誘惑したっけな・・・・)
竜一の頭の中を、遠い、遥な過去の思い出が、微かに浮かび上がった様に思われた。
しかし、それが明確な映像となる前に、彼の夢想は打ち切られた。
「さあ?
あんな蛙の行く末を気にしているほど私は暇じゃありません」
横に寝そべって、尻尾を振りながらミューズは冷たく言い放った。その言葉に竜一は苦笑した。
「ところで、まだ答えを聞いていなかったのだがな」
竜一の真面目な声音にミューズも姿勢を正した。
「実は、向こうの世界を旅立つ時、至高神とメセルリュース様より、決して私たちから正体を明かしてはならない。と言明されていまして」
竜一は眉を潜めた。至高神とメセルリュース様が何故そんなことを?
だが、その疑問はすぐに解消された。
竜一がこの世界に転生したのは罪を清算するためだったのだ。そのために、ミューズが来たからといてすぐに名を明かせるはずがなかったのだ。
だが、そうするとミューズが自分に会いに来た理由が竜一にはわからなかった。
「一体、向こうの世界では何が起こったのだ? ミューズ」
「特に何も無いわ。マスターが気にするようなことはね。
ただ、久しぶりに会いたくなっただけよ。それじゃだめかしら」
いたずらっ子のように半分甘えた声を出して、ミューズは竜一にしなだれかかった。
いつの間にか彼女の姿は、人間の姿になっていた。
それも、黒のドレス姿ではなく、体のラインがはっきり出るスーツ姿でだ。
「まあいい。ところでなミューズ。他の二人はどうした」
竜一がそういうと、ミューズは意外そうに、そして嬉しそうに彼を見つめた。
「記憶が完全に戻ったの?マスター」
「いや、後二人いたような気はするのだが、名前も顔も思い出せない」
竜一は、ミューズが余りにも嬉しそうだったので、少し心苦しくなった。
竜一は、まだ、ほとんど何も思い出してはいないのだ。そう言うと、ミューズは少し寂しそうだったが、気を取り直したのか、直ぐに笑顔を作り、彼にウインク等して見せた。
「いずれわかるわよ」
「そうか」
少し気を取り直して竜一は尋ねた。
「ところで、いつまでこっちにいるつもりだ?」
その問いにミューズはおかしそうに笑いながら答えた。
「飽きるまで」
彼女はこのとき嘘をついたのだ。
これから、彼の側を離れ無いつもりだった。だがそれを今言えば、説教されるに決まっていた。
どうせ説教されるのなら、三人そろっての方がいい。自分だけ、マスターに叱られるのは御免だった。
そして、さらにミューズには、この時腹案があった。
そしてその夜
竜一が熟睡したのを見届けて、ミューズは猫から漆黒のドレスとマントを着た人の姿になると、その美しく整った手を竜一の額にかざし、静かに念を送り込んだ。
ミューズは、今回のことを教訓にして次の手を考えていた。
もし再び今回のようなことがあっても、竜一がすぐに自分達を思い出せるように、伏線を張る必要を感じていたのだ。
そのために、ミューズは一時的に自分の記憶を封印しようとしていた。それも、ただ封印したわけではない。
次に何かが起きたとき、容易に自分達のことを思い出せるように、三人の中の誰か一人の名前を思い出したとき、それをキーワードにして、他の二人の記憶を呼び覚ますようにしたのである。
では、何故わざわざ自分の事を封じるのか?
それは、至高神や女神メセルリュース様との約束のためだった。
”マスタードラゴン自らの力で三妖神の記憶を取り戻し、その名を呼んだときに限り、彼に力を貸すことを許す”という契約。
本来ならば、彼女達三妖神はマスタードラゴンである竜一の忠実な下僕である。
その彼女達が、自分の主に仕えるのにそのような制約を受けるのは、かつて竜一、いやマスタードラゴンが犯した罪のためだった。
とにかくそう言うわけで、何らかの細工をしておく必要があったのだ、三人が全員そろって竜一に仕えるためには。
そして、作業を終えると、もう一つの作業を行うために、ミューズは夜空へと浮かび上がった。
空高く舞い上がったミューズは、そこに結界を張り巡らせた。これから行う作業を何者にも邪魔されないためである。
淡い虹色の輝きがミューズを中心として半径40mほどの球体を形作り、やがて、その輝きが消え去ると、その中心にいたはずのミューズの姿も消えていた。
「さて、こちらの世界の”神”を呼び出すなんて初めてだからね。上手くいくかしら?」
ミューズの視線の先に銀色の魔法陣が浮かび上がると、ミューズは額のアクセサリーに手を添えて静かに外す。
「本来なら、マスターの許可がないと外せないんだけど、事情が事情だもんね。ま、大目に見てもらいましょう」
そう呟くと静かに呪文を詠唱する。
『我は望む。
大いなる力の門よ、我が前に現れ、我が祈りを偉大なる者に告げよ。
我は望む。
命を見守りし大いなる神よ。全ての命の終わりを見届ける者よ。
その御技を成し、死を束ねし冥神プルートゥよ。
我が前にその崇高なる御身を現したまえ。』
ミューズが詠唱する呪文が、音楽的な美しい調べとなり厳かに流れ出す。
今、彼女が呪文を捧げる相手は、この世界の冥府の神であった。
その呪文はミューズが自己流で作った物である。
この世界に来て間もない彼女に、この世界の正確な魔術は使えないが、基本的なことを理解していれば、彼女ほどの使い手にとって不自由は無かった。
そして、その詠唱が終わると同時に、魔法陣の中に美しい女性が現れた。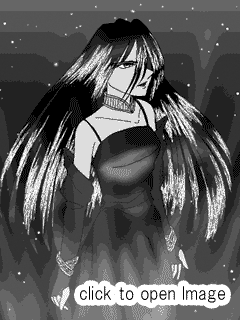
その姿は、ミューズに似ていた。
黒いつややかな髪、漆黒のドレスに身を包み、物静かにたたずむ女性。
ただ、その髪が背中までの長さであること、瞳の色が黒であること、全体的な雰囲気が、近寄りがたい物であるという違いはあった。
「我を呼びだしたのはそなた・・・」
そこまで言って彼女は絶句した。あわてて、ミューズに対して膝を折る。
「失礼しました、”雷神”様とは知らず・・・」
信じがたい光景である。
本来ミューズは、人間であるマスタードラゴンによって作られた使い魔に過ぎない、さらにはこの世界には存在しない異世界の生命なのだ。
この世界の秩序を司っているプルートゥのほうが上位の存在のはずなのである。
それなのに、プルートゥの方がミューズに膝を屈したのだから。
「何もそこまで
どちらが上かは考えるまでも無いと思うけど」
苦笑しつつ答えるミューズに、プルートゥは心苦しそうに反論する。
「いいえ、あなた様のことは良く存じ上げております。
私のような非力な存在が、あなた様と対等の立場になるなど」
(これは封印を解くまでもなかったかな?)
ミューズはあまりにも大げさなプルートゥをみて思った。
先ほど額からはずしたアクセサリー、あれは、ミューズの巨大すぎる魔力を押さえるための封印であった。
勿論、胸の位置にあるペンダントも同じ物である。
これを一つ付けるとミューズの力は百万分の一となり、二つ付けることによって相乗効果により一兆分の一にまでその力を押さえることができた。
ミューズがわざわざ封印をはずしたのは、神を召喚するのには大きな力が必要であり、いくら彼女でも、封印をしたままで神を召喚するのは困難だと判断したからである。
人間の姿から本来の有翼豹に戻れば、彼女の力は人間形態のときの百倍近い力となり、封印をはずすまでもなかったのだが、神を出迎えるのには人の姿の方が礼儀にかなっていたのでそうしなかったのだ。
あまりに腰の低いプルートゥに半分あきれながらミューズは用件を切り出した。
「あなたを呼んだのは他でもないわ、このあいだ魔術結社によって殺された二百名の人間の魂を戻して欲しいの」
これは本来、絶対に受け入れられない願いである。
いくら格が上の相手の願いとはいえ、そんなことを簡単に認めていてはこの世界の秩序そのものを破壊しかねないのだから。
「ミューズ様、それは・・・・」
「これが無茶な願いなのはわかっているわ。でも、マスターによけいな負担を与えたくはないの。
勿論、この世界に不都合が起きないように私が責任を持って処理します。
それに、200人分の魂の代償も払うわ」
そう言うと、ミューズは自らの左手首に傷を付けた。
そこからわき出てくる真紅の液体。それはわき出すと空中に浮き上がり、やがて直径5mmほどの球体になった。
「紅玉・・・・・・」
プルートゥは言葉に詰まってしまった。
その小さな紅玉からは、背筋に寒気が走るほどのすさまじい力を感じる。
「これでは不満?」
ミューズの問いかけに、プルートゥはあわてて首を振った。
「いいえ、とんでもない。
ミューズ様のそれほどの大きさの紅玉ならば、代償としては十分すぎるほどです。
二百人どころか二万人分の命に勝る価値があります」
その言葉に満足げに微笑みながらミューズはだめ押しをする。
「この世界の因果律を変えて、歴史を少し変更しようと思うの。そのためにも二百人分の魂が必要なのよ。お願い協力してくれない?」
因果律への干渉、神でさえおいそれとはできない歴史への干渉。
その難事さえミューズにとっては大した作業ではなかった。あとは、魂の調整さえできれば、この世界の歴史を彼女の思い通り変更することができるのだから。
「わかりました・・・・・・」
ついにプルートゥが折れた。
「ですが、こんな無茶な事は今回限りにしてもらいたいですね」
プルートゥは溜息混じりにそう呟いた。
「心配無用よ。私だってこんな無茶な願いを何度も言うつもりはないし」
しかし、そういうミューズにプルートゥは疑わしげな視線を向ける。
「あら嫌だわ、そんなに私が信用できない?」
「ミューズ様方の噂はかねがねうかがっております。
人の手によって作られた下僕でありながら、神を凌駕するほどの力の持ち主であると。
それゆえに、自らの主人のためには手段を選ばない恐ろしい方々だとも」
言葉の内容はなかなか剣呑な物であるが、その口調と表情は柔らかく、むしろ好意的な物である。
「酷いわね、いったい誰よ、そんな根も葉もない噂をばらまいているのは?」
おどけてみせるミューズだったが、その内容は完全に事実である。
ミューズとしては苦笑するしかないわけだが、すぐに、苦笑ではすまされないことに気が付いた。
なぜ彼女が自分たちのことを知っているのか。それもこれほど正確に。
確かに、ミューズもかつてはただの使い魔であった。雷神という名もあだ名というか、敬称のような物で正式に雷神と認められていたわけではない。
だが、今のミューズは彼女達の世界では、正式に雷神としての地位を与えられ、神として扱われている。
こちらの世界の存在がミューズを見て、”人間に作られた者”と見抜くのは至難の業と言っていい。
それなのに、プルートゥは彼女が人間の使い魔であることを言い当てた。しかも、”ミューズ様方”と複数形を使ったのである。
この世界にまだ来ていない他の二人の存在にまで気づいていることは、いったいなにを意味するのか。
考えてみれば魔道士とはいえ、人間が自分たちの存在を予言しているという事自体妙なことだ。
ミューズは勿論、あの世界を追放された
これはゆゆしき事態かもしれない。
ミューズはそう感じていた。
竜一とともに大学に行っていたときに魔力によって図書室の書物を調べ、あるいは竜一がアルバイトに出かけている間、パソコン通信を利用してこの世界の宗教を調べた。
神と直接対話できるミューズが、わざわざそんな手間をかけたのは、人間が信仰する神と実在する神が必ずしも同じではないためであり、存在しない神を奉っている宗教もあるため、人間の情報で調べた方が確実だからである。
そして、そこにマスタードラゴンが忌み嫌っていたあの”外道馬鹿”の存在を感じた時、ミューズはこの世界が”奴”に浸食され始めていると確信していた。
しかし、どうやらそれ以外にも、第三勢力が存在するらしい。
特に直接自分達に害になる物ではないようだが、正体の分からない存在が、自分達の動きを観察しているという状況は決しておもしろい物ではなかった。
いずれは確かめる必要もあるだろう。だが、今は、こちらの方が重要だった。
プルートゥと契約を結ぶと、ミューズはさっそく因果律へ干渉した。
魔術結社に殺された人間の肉体を再生し、死したはずの者達に新しい命を与える。二百名の人間の肉体を、細胞一つ、原子一個にいたるまで正確に再生し、プルートゥから受け取った魂を、本来の者と同じ肉体に移す。
本来なら死亡したはずの人間を生かす。
それも、時間を戻すのではなく、死んだ後の時間で、である。それは、時間を単純に戻すときとは比較にならないほどの負担をこの世界に強いるものだ。それにより捻れ、歪んだ物理法則を力尽くで修正し、安定させる。
精霊や、ほかの生き物達に影響のないように微妙な修正をし、殺した側の魔術師達の記憶は残しておく。
二度と同じ過ちを犯さないために、彼らの心に楔を打ち込むためにあえて彼らの記憶を残したのだ。
自分達に手を出せば大怪我をするということを、死者すらよみがえらせる力を持ち、最大の魔術結社を滅ぼす力を持つというデモンストレーションであった。
「ありがとうね、プルートゥ、感謝するわ」
「どういたしまして。」
プルートゥはそう言うと、その場から消え去った。
彼女の役目は終わったのだから。
「さて、これで後始末はおしまいね。後は、彼女たちが来るのを待つだけか」
夜空を見上げて、ミューズは呟いた。
”奴”との戦いが近いことを彼女は確信していた。速やかにこちらの戦力を整え、”奴”に対抗できる準備をしておく必要があった。