[ 三妖神物語 第一話 女神降臨 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第四章 魔術結社
竜一が意識を取り戻したのは、見知らぬ一室の中であった。
周りは殺風景な部屋で、簡素なベットとソファー、事務デスクと椅子しかない。
自分がそのベットの上で寝ていることを自覚してから、自分の身に起こった事を思いだした。
そうだ、確か町の中で後頭部に痛みを感じて、それから・・・。
頭に残る鈍い痛みに顔をしかめながら、竜一が自分の置かれた状況を認識していたとき、不意に目の前の殺風景なドアが開いて、一人の女性が入って来た。
彼女は、婉然と微笑んだ。
「ようこそ、竜王の継承者」
・・・ 竜王の継承者? 何の話だ一体?
竜一は呆然と目の前の女性を見つめた。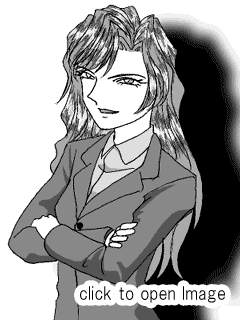
年の頃は25歳前後だろうか。金髪碧眼、万年雪のように白い肌、完璧なアングロサクソンだった。
顔もプロポーションも文句なく一級品であるが、その切れ長の目から放たれる視線といい、全身から発散されている気配といい、受ける印象は冷たいの一言に尽きる。
とにかくお付き合いしたら風邪を引くこと間違いなし、ベットインしようものなら、凍えてしまうような女である。
美人だがあえて近付きたくないタイプの女だろう。ついでに竜一には面識も無いはずであった。
訳がわからずにきょとんとしている竜一を見て、彼女は笑いながら話し掛けてきた。
「なあに、その間の抜けた顔は。
いいのよ、今更しらを切っても無駄なこと。私たちは総てを知っているのだから」
いかにも何もかも知っていますという言い種だが、竜一にはさっぱり理解出来ない。益々面食らう竜一に女は首を傾げた。
「それとも ・・・。貴方本当に何も知らないの?」
素直に頷く竜一。
誘拐されたらしいことは知っていたが、今更じたばたしても始まらない。
ここは大人しく、手に入れられる物は情報だけでももらった方が得である。
竜一はそう結論づけた。逃げるとしても知識がなければ何もできないのだから。
しかし、そんな彼の態度に、彼女は少し意外そうに呟いた。
「変ね。それなら何故、急に貴方の存在を私たちが見失ったのかしら?
てっきり貴方が自分の力に気付いて、気配を隠す手段を講じていたと思っていたのに・・・」
(力?)
どうやら竜一が危惧していた通り、三文小説の世界に踏み込んで、いや、引き込まれてしまったらしい。
口調からして彼女はどうやら、毎度おなじみ悪の軍団その一と言ったところであろう。
竜一は先ほどとは別の意味で頭痛を感じつつ、質問した。
「あのさ、分かるように説明してくれない?
あんた達一体何者なの?
ここどこ?
何の目的で俺を誘拐した訳?」
別に正確な答えを期待した訳ではないが、もしかしたらという気持ちがあったのだ。
それに、こんな得体の知れない相手に捕まって不安な自分の心を、落ち着かせる目的もあった。
竜一は自分を小心者だとおもっていた。もっとも、他人に言わせれば、かなり図太い根性の持ち主だという意見が大半を占めていたが・・・
しかし、予想に反して女はあっさりと竜一の質問に答えた。
「私は魔道士リザン。魔術結社”ミザリー”の幹部の一人よ。よろしく、”継承者”」
「ミザリー?
ミザリーってたしか不幸って意味だよな。なんてネーミングセンスだ」
「我々は人の不幸を食らい、他人の幸運を奪って力を蓄えている。相応しい名前だと思うわ」
リザンは、軽く肩をすくめた。
「多少は世間に迷惑かけてる事を自覚している訳だ。で、その”竜王の継承者”っていうのは。」
「貴方のことよ、決まっているでしょう。」
リザンは意味ありげに笑うと、言葉をつないだ。
「”竜王の継承者”は、魔道士仲間では割と有名な予言にある存在でね。
巨大な力を”継ぐ”存在。巨大な力を支配し、それを使役する権利を持つ者なのよ。
その予言によれば、その存在はこの時代に人の姿で現れると言い伝えられているわ」
「それが、俺って訳?」
竜一は頭痛を感じつつも確かめた。
「そうよ」
リザンはまたしてもあっさりと頷いた。
いい加減にして欲しい。それが竜一の素直な気持ちだった。
(俺は、今まで平穏無事な、極めて常識的な人生を送っていたはずだ。
それなのに、いきなりなんなんだこの展開は!)
竜一は内心頭を抱えた、こうなったら開き直りの一手あるのみである。
竜一はとことん付き合う事にした。可能な限り知識と情報を手に入れて、何とか逃げる機会を手に入れるために。
「それってどんな力を持っているんだ?」
「さあ、とにかく神にも比肩し得るほどの力を支配するって言われているわ。
手に入れれば、どんな望みも叶うほどの」
リザンはうっとりと、あらぬ方向を見つめていた。
「あのねえ、ご期待に背いて悪いんだけど、俺全然そんなこと知らないぜ。
人違いじゃ無いの?」
竜一は努めて冷静な口調でいってみた。
すると、リザンは今までとはうって変わった、実に恐い笑いをその美しい顔に浮かべた。
「その心配は無いわ。
貴方であることに間違いはない。
今までは、貴方なのかどうか自信が持てなかった。
だから失敗も随分としてしまったけれどね。
それがわかった今ならば、貴方が望もうと望むまいと、知っていようといまいと、そんなことはどうでも良いわ。
ようは、貴方に私たちの役にたってもらうことだけ・・・。」
(あ〜あ、やっぱりこうきたか。大体検討はついていたけどね。)
竜一は、自分の予想が当たったことを確信した。
だからと言って嬉しい訳ではない、むしろ、不快な位だったが。
だが彼は、直ぐにリザンの言葉に含まれていた不気味な意味に気がついた。
(まてよ? 随分と失敗した? ちょっと待て!)
竜一は、背筋に冷たいものを感じていた。
「おい、今、随分と失敗したとか言ったな?
ひょっとしてここ一週間ばかり世間を騒がせている、謎の男性消失事件ってえのは・・・。」
「そう、私たちの仕業よ。正確には、私たちを含めた各魔道組織による人狩り。
貴方の力を狙っているのは、私達だけでは無いわ。
力ある魔道士のほとんどが、貴方の存在を血眼になって捜しているのよ。」
「その男たちは、今どうしているんだ?」
リザンは、笑いながら、ゆっくりと尋ねる。
「彼等が無事に帰ったと言う噂は聞いた?」
竜一は首を横に振った。
「当然でしょうね、誰一人生き残らなかったのだから。
あの儀式は、”竜王の継承者”以外生き残れないようになっているのよ。
それ以外の者があの儀式を受ければ、肉片一つ残さず消え去るわ」
(じょ、冗談じゃねえ・・・・)
竜一は真っ青になった。
彼女は何人もの犠牲をだし、失敗を重ねたというその儀式の次の犠牲者に彼を選んだのだ。
「わああ!よせ辞めろ、俺は死にたくない。やめてくれえ、頼む」
「見苦しいわねえ、男のくせに」
「男だって死ぬのは嫌だ、死にたくない、嫌な物は嫌だー」
竜一は恥も外聞も無く喚き散らした。
このままでは、自分まで殺されてしまう。
竜一は慌てまくった。奴らは”継承者”なら無事に済むと言っているが、そんな話が当てになる訳がない。
第一、竜一がその”継承者”である補償等欠けらも無いのだから。
竜一の狂態に鼻白みながらも、リザンは余裕の笑顔を返した。
「大丈夫よ、貴方は間違いなく”竜王の継承者”なのだから。命に別状など無いわ」
しかしそれで、竜一が納得するはずはない。彼は噛付くように、リザンに向かって吠えたてた。
「いい加減なこと言うな!
なら何故今まで、そんなに失敗してきたんだ。
お前らの言うことなど当てになるか!」
竜一の怒鳴り声に、リザンは肩をすくめて見せた。
「だから言ったでしょう?
あの時、貴方の力を見失ってしまったのよ。
それまでは、探査の術をかければ直ぐに居所が分かったのにね。
何故か突然に。
だから、この町にいる19才の男を片っ端から調べなければならなかった。
それ故に失敗もしたけれど、これほどに近づいた今は貴方の力を感じるのよ。僅かだけれどね。
それも、この世界には存在しない異質の力をね・・・間違え様も無いわ。」
そんな事で竜一が納得する訳がない。なおも食ってかかる。
「それなら、何故今まで分からなかったものが、いきなり分かるようになった?変じゃねえか!!」
「その通りよ、私もその理由を知りたいわ。
私はてっきり、力の存在に気付いた貴方自身が、力を封じるか結界を張って隠れたかと思っていたのに ・・・。
本当に知らないの?」
リザンの口調は、穏やかでさえあった。
竜一がここから逃げ切れないことを確信しているのであろう。慌てる必要など無いのだ、その余裕故の優しさだ。
それは竜一にもわかった。そして悔しいことに、それは全くの事実だった。
例えこの部屋から逃げおおせても、この建物の構造が分からない以上、どう逃げれば良いのか、見当もつかないのだから。
「じゃあ、なんで19才の男ばっかり狙ったんだよ。」
「さっきも言った通り、探査の術で貴方の存在は分かっていたわ。
年齢も、性別も、居場所もね。
家の位置など私達は気にしていなかった。と言うよりも調べる必要などなかった。
なぜなら、いつでも見つけ出せると思っていたからよ。
ところが、私たちが動こうとした矢先に、貴方の存在が消えてしまった。
急がないと別の組織に先を越されるからね、手段を選んでいる暇は無かったの」
「それで、何人もの人間を殺したのか。」
「大袈裟ね、たったの二百人よ。それほど殺してやしないわ。」
(二百人?
それがたった?何を考えているんだこいつは!二百人も殺しておいて!)
竜一が怒りをあらわにすると、リザンが皮肉のこもった目を向ける。
「あら、不満そうね?」
リザンは竜一を可笑しそうに眺めながら呟いた。
「この世界を事実上支配しているのは、私たち一握りの魔道士なのよ。
魔力の無い人間は、私たちにどう扱われても仕方無いわ」
「そ、それって、無茶区茶じゃねえか!そんなことが許されると思ってるのか?
だいたい、魔道士が世界を支配しているなんて聞いたこともねえ。」
「当然よ、表の人間はなにも知らないわ。
知ったところでどうすることも出来ないけれどね。
私たちは、その気になれば、一国の首相も、思いのままに動かすことも出来る。
世界を思いのままにすることなど造作も無いこと。
魔力を持たない下等種族は、私たちが許す範囲でしか生きることの出来ない家畜に過ぎないわ。
家畜をどう扱おうと、私たちの自由よ。そうでしょう?」
竜一は開いた口がふさがらなかった。
いいたい放題というか、ここまで、でかいことを言うとは思わなかったのだ。
彼は段々腹が立ってきた。
(何だってこんな奴らの良いようにされなきゃならないんだ。
逃げてやる、絶対逃げてやる。
こんな奴にこれ以上付き合ってたまるか。
チャンスがあれば、な)
そう、堅く決意する竜一であった。
「さてと、無駄話はこれ位にして、儀式を始めましょうか」
頭の中で逃げ出す算段をあれこれ考えていた竜一は、その言葉で我に帰った。
(待て、もう少し時間をくれ、でないと考えがまとまらん)
竜一は慌てて、話を引き伸ばそうとした。
「ちょっと待て、その儀式ってのは何だ?」
「貴方を我々の仲間にするための儀式よ。我々に力を与えてくださる神に、貴方を捧げて、貴方の力を我々の物にするのよ。永久にね。」
背筋が凍り付いたように感じたのは彼の錯覚か。
時間を稼ぐために慌ててさらに質問する。
「待てよ、さっきから聞いていれば、世界を支配してるとまで言うあんた達が何だって俺の力を欲しがるんだよ。無意味じゃねえか。」
するとリザンは、呆れたような口調で言い返した。
「貴方はまだ自分の力の価値を理解していない様ね。
確かに私たちの組織は、他の組織に比べて強大だわ。
術者の質も量も、他の組織より抽んでている。でも、もしも貴方の力を他の組織が手に入れたら、それだけで今の私たちの優位は根底からひっくり返ってしまうのよ。
貴方を他の組織に渡すことなど出来ないわ。
貴方の力は私たちが有効に使ってあげますからね。心配しないで、総て私たちに任せなさい。」
(じょ、冗談じゃない!)
竜一は心の中で悲鳴を上げた。
どこの世界に、「お前をこれから奴隷にしてやる、有り難く思え」と言われて、喜ぶ馬鹿がいるものか。
こいつらは、竜一の人権も、人格も全く無視して彼を何かの力を持つ、便利な道具だと思っているのだから。
(冗談じゃねえぞ、俺を何だと思ってやがんだ。)
竜一は完全に頭にきていた。
(こうなったら強行突破あるのみ! 力ずくでも逃げ出しちゃる)
竜一がそう思ったその時、机の上にあった機能美最優先の安物のビジネステレホンが、けたたましく鳴り出した。
ピピピピピピピピ
「どうしたの一体。」
リザンが受話器を取る、そのうちに、やや声が粗くなってきた。
「何ですって? 侵入者が? それで被害の方は?」
魔道士が電話をしている図というのは、これでなかなか可笑しなものがある。
だが、魔法とて万能ではない。
確かに通話の手段としての魔法もあるが、よほど強大な力を持つ者でも無い限り、力の消耗もある。
何よりも電話の方が手間がかからないのだ。魔法にも向き不向きがあるのだった。
しかし今は笑って見ている時ではない。
はっきり言って、これはチャンスである。
竜一はゆっくりと足音を忍ばせてドアの近くまで来ると、ほとんど一瞬の内に外へ飛び出した。
走り出す彼の背中に、リザンの声がぶつかった。
「お待ちなさい、逃げても無駄よ」
その声は不思議と抑揚に欠け、感情を感じさせないものだった。
罵声でも怒声でも悲鳴でさえもなく、ただ、事務的な義務感から発せられたような声だった。
「こ、ここまで来れば、一安心・・・・」
肩で荒い息をしながら、竜一は壁に手をついて呼吸を整えていた。
あの部屋から脇目もふらずに一直線に逃げると、幸運なことにエレベーターにぶち当たった。
エレベーターの表示を見ると地上5階らしい。急いでエレベーターに乗り一階に降りる。
無事に一階につきエレベーターを降りると、そこからまた真っ直ぐな道に出た。
だが、少しおかしな感じもした。
あの女以外、誰一人、見張りにさえ出会わないのだ。が、考えている暇などない。
そしてその異様に長い一本道をやっと走破して、今、目の前には出口らしきドアが見えた。
「やった、出口だぜ」
竜一は喜々として、ノブに手をかけ、勢い良くドアを開けた。
「お帰り、早かったわね」
(・・・・一体何の冗談だ? これは・・・・)
竜一は一瞬、目の前が真っ暗になった。
なぜなら、彼の目の前には、見たくもない人物が悠然と椅子に座って、彼の帰りを待っていたからである。
竜一は確かに、あの部屋から飛び出して、一直線にエレベータに乗って一階に降りたはずだった。
確かに、そのはずなのに・・・・、今、彼は、その逃げたはずの部屋に舞い戻ってしまったのだ。
「ば、馬鹿な・・・。」
顎然とした竜一を見て、リザンは声を立てて笑った。よほど竜一の表情がおもしろかったらしい。勿論、笑われる方としてはたまったものではない。
「だから無駄だと言ったでしょう?この部屋一帯には結界が張ってあるの。
外からも中からも、私の許可なく、出入りすることは出来ないのよ。」
「嘘だ!」
竜一は一言そう言うと、再びきびすを返して出口を求めて走り出した。
彼は再び走った。出口を捜して。
同じ道を行けば、同じ結果が待っているだろう。
竜一は必死に、別の道、別の部屋を捜した。
しかし、エレベーターまでの道には、脇道も非常階段も別の部屋も無く、ただ、コンクリートの壁のみがあるだけであった。
「畜生、やっぱりあのエレベーターを使うしかねえのか」
そして、エレベーター前にたどりついた竜一は、周りを見回した。
結局、エレベーターに着くまでに、何の変化も無かった。
どこまでも、コンクリートの壁があるだけであった。
彼は再びエレベーターを確認した。
やはりここは5階である。
何度も何度も、しつこく見た。
しかし、5階は5階であって、1階でも、2階でもない。
「今度こそ・・・」
竜一はエレベーターに乗ると、1階のスイッチを押した。
グウウーン
低く唸りながら、エレベーターは、ゆっくりと降りて行く。
確かに降りている。エレベーターのランプは、5階から、4階3階と、順次点灯している。何より、彼の体に感じるこの感触は間違い無い。
更にエレベーターは降り続ける。
3階・・・、2階・・・、そして・・・、1階!
チーン!
軽快な音と共に、ドアが開く。
竜一は、エレベーターを降りると周りを注意深く見た。
やはり、コンクリートの壁が続く、それ以外は何も無い。
エレベーターを振り返ってみる。
エレベーターは、まだこの階に止まっているようだ。
ランプは、一階を示している。
・・・間違い無く1階である。多分・・・。
今度は、ゆっくりと、地面の感触を確認しながら歩いてみる。
てくてくてくてくてく・・・。
「1、2、3、4、5」
歩数を数えながら竜一は歩く、ひたすら歩く。
走りたくなる衝動を抑え、一歩一歩、確実に歩いていく。
歩数を数え、エレベーターを振り返りつつ、自分の位置を確認しながら歩き続けた。
「88・・・89・・・90・・・」
そして、エレベーターと、あのドアの調度真ん中当たり、歩数にして、きっちり100歩目で、突然、おかしな感じを受けた。
ふわりと、微かに浮いたような感じがしたのだ。
その異様な感覚は直ぐに消えた。竜一は急いで、エレベーターに駆け戻る。
「やっぱり・・・」
竜一は唸った。
エレベーターのランプに書き込まれている、現在位置の表示マークはきっちり”5階”になっていたのだ。
どうやら、エレベーターとドアの真ん中、あの異様な浮遊感のある所が、結界によるトラップになっているらしい。
「まったく、RPGじゃあるまいし・・・。」
竜一はもう一度エレベーターに乗り、1階へと戻った。
1階についた後、彼は99歩目で立ち止まっていた。
後一歩踏み出せば、さっきと同じ目に会うだろう。時間の無駄である。
何とかここを遣り過ごす方法を考えなければ、永久に同じ事になるのだ。
竜一は、ズボンのポケットから小銭入れを取り出した。
その小銭入れから、10円玉を取り出した。
貧乏性の竜一にとっては耐えがたいことである、はっきり言わなくても勿体ないが、背に腹は代えられないのだった。
この10円玉に、竜一は自分の身代わりを勤めてもらうつもりだった。
まず、無造作に、一歩手前の床に放り投げる。
床につく前に、十円玉はまるで空気の中に溶けるように消え去った。
その光景はまるでアニメかSFXである。この目で見ても、とても信じられない光景だった。
本当に、魔法の結界があるとは・・・・。
夢だと思いたいところであるが、残念ながら、現実逃避していたところで仕方ない。
それよりも、今はこの結界をどうにかして破らなければ、竜一に未来はないのだ。
もう一枚、十円玉を取り出す。
(うう、勿体ない・・・)
身を切られる思いで十円玉を手に乗せる。
何とか自分を自分を納得させると、今度はさっきより力を入れて、もう少し先の方へ投げてみる。
これがRPGなら、1歩先へ跳べばトラップに引っ掛からず、安全に行けるのがパターンなのだが・・・。
ちゃりーん
澄んだ音を立てた十円玉は、少し先の床に見事に落ちた。
余りにも呆気ない、意外な結果に竜一は目を丸くした。
まさかこんな簡単に結界を突破出来るとは・・・・、竜一自身とても信じられなかった。
どうやらこの結界、ゲーム並に安直な代物であるらしい。
「なめられたもんだぜ」
竜一はそう呟いたが、内心は小踊りしたい気持ちだった。
当たり前である。やっとこの得体の知れない所から、逃げられるのだから!
そうとわかれば、どうということはない。助走をつけて危険地帯をとび越えてしまえばいいのだ。
踏み切るポイントに、もう一枚の十円玉を置く。
後方に、20歩ほど下がると、呼吸を整えて走り出した!
目標の十円玉が、ぐんぐん近付いてくる。
(今だ!)
「はっ!」
短い気合いと共に、跳ぶ!
そして、着地した時、竜一の足元には、十円玉があった。
「やったね」
竜一は笑いながら、なにげなく後ろを見た。
(・・・おかしい・・・・・・)
竜一はそこで奇妙なことに気が付いた。
さっき、踏み切りのポイントに置いておいた十円玉が消えているのだ。
(ま、まさか・・・)
竜一は青くなりながら、急いでエレベーターに駆け戻る。
ちなみに十円玉であるが、しっかりと拾っていた。貧乏性は伊達ではない。
(あああ! やっぱりいい!!)
竜一は頭を抱えてしまった。
エレベーターの表示は、ここが5階であることを冷酷に告げていた。
それから5分後、再びトラップの手前に彼はたたずんでいた。
目の前には十円玉が二枚。
踏み切りポイントと、安全地帯を知らせる二枚であった。
竜一は悩んでいた。
十円玉は、ちゃんと外に出ている。
それなのに、何故自分はワープポイントを越えて外に行けないのであろう?
とにかく正面突破は無理らしい。彼は辺りを見回した。
パターンで行けば、この結界を維持するための魔法陣なり、魔法の品なりがあるはずである。それをどうにかすればここから出られるはずだった。
それから更に15分がたった。が、何一つ見付からない。
魔法の品や魔法陣どころか、悪戯書き一つ、埃さえもないのである。
ここには、結界を維持する物はないのだろうか? それとも、単に竜一に気付かないように作られているのか?
多分後者だろうと竜一は考えていた。
しかし、そうならば完璧にお手上げである。
脱出しようにも、出口は見付からない。
トラップのトリックを見破ることも出来ない。
なにより、トラップが魔法ときては、はっきり言ってルール違反、反則以外の何物でもない!
竜一が唸っていた時、突然、おかしな浮遊感が彼の体を包んだ。
(あのトラップと同じ感覚だ!)
竜一がそれに気付いた時、目の前には見たくもないあの女がいた。
「どう? 逃げられないって分かったでしょう?」
リザンは、勝ち誇った笑みを浮かべて竜一を見据えた。
「さあ、もう決心もついたでしょう。一緒に祭壇へ行きましょう」
「決心なんか出来とらん!」
竜一は大声で喚いたが、リザンは取り合わない。
何やらぶつぶつと呟いている、どうやら何かの呪文のようだが?
一体何をするつもりなんだ?
ぼーとしている竜一の体が、何かに縛り付けられたように、締め付けられる。
いや、本当に締め付けられているのだ。
ただ、その縄が、目に見えないだけなのだ。
(ちくしょー、なんでこんな事になるんだよお!)
竜一は内心で毒づいていた。
自分はもっと普通の、常識的な世界に生きていたはずなのに、どこでどう間違ってこんな事になったんだ。
運命の女神が目の前にいたら、文句の一つも、いや文句を百位は言ってやりたい気分である。
「お、おい! 俺をどうするつもりだ!」
「決まっているでしょう? 貴方に儀式を受けてもらうわ」
「その儀式って、どんなもんなんだよ」
「直ぐに分かるわ。それじゃ、行きましょうか」
「まて、もう少し質問してもいいだろう?」
リザンは、少しうんざりしながら頷いた。
「まあいいわ。私が答えられる範囲ならね」
「まず、あの結界、どういう理屈でなっているんだ?
10円玉は、ちゃんとあのワープポイントを越えて床に落ちるのに、俺が跳び越えても、結界の外に出られなかった」
「へえ、なかなかうまい手を思い付いたわね」
リザンは、感心したように竜一を見た。
「別にそれほどでもない。RPGをやってたからね、思い付いただけさ」
「なるほどね、でも残念ね。アイデアは良かったみたいだけどね。
あの結界は空間を歪めてつないでいるものなの。だから、あの結界は、ある程度の質量がないとその歪みに引っ掛からずに、外に出てしまうことがままあるのよ。
つまり、十円玉は質量が小さすぎたために、結界が作った歪みに引っ掛からずに外に出てしまったというわけ。
勿論、結界のポイントの真上に落ちれば、質量に関係無く歪みに引き込まれることになるけどね。」
なるほど、そーゆー訳だったのか。竜一はやっと納得がいった。
「あの結界を作っているのは、魔法陣か? それとも魔法の品か?」
「魔法陣よ。
もっとも、その魔法陣そのものも、特別な方法で空間の歪みの中に封じてあるから、貴方がどんなに頑張っても見付けることも壊すことも出来ないわ」
用意の良い奴である。まあ折角手に入れた獲物をみすみす見逃すほどお人好しでは無いと言うことだろう。
「もう満足した?」
「い、いや、もう一つ。
さっきの電話で侵入者がいたとか言ってたが、そいつは何者だ?捕まったのか?」
「ああ、それはもう片がついたわ」
そう言うと、リザンは、机の上にあった箱に歩み寄って、蓋を開けた。
竜一はその箱に見覚えがなかった。おそらく、竜一がこの部屋から飛び出した後で、この部屋に置かれたのだろう。
竜一が見ている前で箱を開けると、リザンはその中から、黒い小さな毛糸玉を無造作に取り出した。
黒い毛糸玉・・・・。
竜一の心臓に、冷たい棘が刺さった。
違う、毛糸玉じゃ無い、あ、あれは・・・・。あの黒い固まりは・・・・。
両目を閉じているため、その瞳の色はわからない。
しかし、額と胸に淡い銀色の輝き・・・・。
少し距離があるため、その銀の輝きがどのような模様を描いているのかは判断できない、しかし、漆黒の美しい毛並みに、そんなおしゃれなアクセサリーを持っている猫などほかにいるはずがない。
そう、それは・・・・、そのリザンの右手に襟首を捕まれて、ぐったりしているそれは・・・・。
竜一の可愛い同居人のミーであった!
「ミー!おい、しっかりしろ、おい、ミー!」
「あら?この猫知り合いなの?」
「俺の同居人だ!まさか、殺したのか?」
「まさか、ちょと派手に暴れて手が付けられないから、麻痺の呪文をかけておいただけよ。
ところで、この猫とはどうゆうきっかけで知り会ったの?」
うろたえる竜一に、リザンは真剣に聞いた。
それに、何の意味があるのかわからなかったが、竜一はとりあえず正直に答えた。
「一週間位前に道端で拾った。それだけだ」
「今日は一緒にいた?」
「昼前までは。午後から、どこぞのお嬢さんに誘拐されて、取り戻す為に彼女の家に行こうとして、お前らにとっ捕まった」
竜一の答えにリザンはうなずいた。
「そう、時期も合ってるわね。やっぱりこの猫の仕業だったのね」
「どいういうことだ?」
リザンが納得顔で頷いているのを見ながら、竜一は声を荒げた。
「さっき、貴方の存在が突然分からなくなったといったでしょう?
この猫が、貴方の存在を隠していたのよ。
この猫から魔力の波動を感じるわ。
あたしの結界を破ってこの建物の中へ入って来るほどだからね。
貴方が、この猫を作ったの?」
「作ったって・・・・」
一体彼女が何を言っているのか竜一は理解できなかった。いや、もしかしたら、うすうす気づいていたのかもしれない。
だが、竜一の理性がそれを拒絶していたのだ。
「ミーが、何だっていうんだ?」
竜一の問いにリザンは答えず、納得顔で頷くだけだった。
「どうやら貴方ではないようね。すると、どこの魔法使いの仕業かしらね?
こんな使い魔を貴方の傍に付けたのは。
まあ、あたし達同様、貴方の力を欲する奴らの仕業でしょうけどね」
(ミーが使い魔?)
それは、竜一にとって余りにも大きい衝撃だった。
竜一の心には致命的とも言うべき傷ができていた。
ミーも自分をそんな目でみていたのかだろうか?
自分の”力”とやらが目当ての奴等の仲間だと言うのか?
あの仕草も自分を騙し、自分の信用を得るための演技だったのか?
竜一は、今まで、孤独だなどとは思っていなかった。
だが、ミーに会って、初めて、プライベートな面において孤独であることに気がついた。
家に帰って、ミーの顔を見る度にほっとした。
ミーと話をするのが、何よりも楽しかった。
竜一は、自分が寂しかったことを、孤独だったことをミーに教えられた。
竜一にとって、ミーはもはや家族も同然、いやそれ以上のものとなっていたのだ。
そのミーが、魔法使いの使い魔?
あの可愛い仕草も、あの愛くるしい動作も、そしてあの美しい姿さえも、総て竜一を欺くためだったのだろうか?
彼を利用するために、見張るために、彼の傍にいたと言うのだろうか?
そして竜一は、今、愕然となっていた。
自分が、これほどまでに、ミーの存在に慰められていたことを思い知ったのだ。
その後、リザンが何か言っていたが、彼には何も聞こえなかった。
目の前が真っ暗になり、何も見えなかった、何も聞こえなかったのだ・・・・。
そして、竜一が次に正気に戻ったのは、祭壇の有る暗い一室でのことだ。
「な、なんだここは!」
竜一は慌てて動こうとしたが、両手両足に械を付けられて、ベットに仰向けに寝かされていた。
「お、俺をどうするつもりだ!」
動くに動けず、ガチャガチャと械を鳴らす竜一に、リザンは冷やかな目で彼を見下ろしていた。
「何を今更、儀式に決まっているでしょう。
大丈夫よ。苦しいのは、ほんの僅かな間だから。
その後、貴方は私たちの物となってその力を存分に奮うのよ。
素晴らしいでしょう?」
「待てよ、あんた達一体何をたくらんでいるんだ?
俺を他の組織に奪われることを恐れていると言ったが、それだけじゃあるまい」
「そうね、良いわ、どうせ貴方は私たちの物になるのだから。
貴方の力で是非ともして欲しいことがあるのよ」
「あんた達のために?」
「私のために」
リザンは微妙に訂正した。
「私の師であり、恋人でもある、大魔道士ラス・ディロス。
彼を冥府から呼び戻して欲しいのよ」
「冥府?あの世か?あんた、まさか死んだ恋人を蘇らせるために、俺の力とやらを欲しがっている訳?」
竜一は呆れてしまった。
なんて月並みな、なんて平凡な欲なのか。
もっとドラマチックで、度肝を抜かれるような事を期待していたのに・・・・・・。
「平凡だと思うでしょう?」
リザンは自嘲気味に笑った。
「でも、私たちの、いえ、人の”魔力”では、死んだ者を蘇らせるのは不可能なのよ。
どう頑張っても、ね。
確かに、”反魂の術”とか、かりそめの命を死体に吹き込む術は幾つもあるわ。でもそれは、あくまでも肉体を生かす術であって、魂を、その人本人を蘇らせる術ではない」
「そりゃそうだろうな。
死人を蘇らせるなんて、自然の摂理に反する。出来るわけがない」
竜一は胸をはって答えた。
ところがリザンは、妖艶な笑みを彼に向けた。
「ところが、”竜王の継承者”にはそれが可能なのよ。
前にも言った通り、その存在は神に等しい力を支配する。
死人を蘇らせるなどたやすいこと」
竜一は絶句した。
余りと言えば、余りである。
死人を生き返らせるだあ?
そんなこと自分に出来る訳がないではないか!
もしそんなことが出来るほどの力を持っているなら、とっくの昔にここから逃げ出してるわい!
竜一はそう叫んだ、だが、リザンはまるで取り合わず、祭壇にいる部下たちと共に儀式を始めようとしていた。
「おい! ミーはどうした?」
「そんなに、あの使い魔が気になるの?
大丈夫、殺したりしてはいないわ。
魔力を封じる結界を施したオリの中に入れているわ」
「そうか・・・・・・」
竜一は安堵の溜息をついた。
誰かの命令で自分を監視していたとしても、竜一にとっては、ミーはかけがえのない存在だった。
それに、リザンが言っていたではないか。
ミーが彼の存在を隠していたと。
少なくとも、ミーが傍にいてくれた間は、竜一は平和な生活をすることが出来た。
(そのために、無関係な人間を犠牲にしてしまったが・・・・)
ミーを竜一によこしたのが、どこの何者かは知らない。
何をたくらんでいるかもわからない。
だが、この女どもよりは、余程ましというものだった。
それに、ミーは竜一に安らぎをくれたのだ。これは紛れもない事実だ。
この女どもは、自分に何をしてくれた?
ミーのためなら、力とやらをくれてやってもいい、だが、何故、こいつらにいいようにされなければならない。
竜一は腹を立てた。
しかし、腹を立てようが、暴れようが、鋼鉄性の械を外せる訳がなかった。
だいたい主人公ってのは、ピンチに陥った時、今までにない力に目覚めてピンチから抜け出すのがパターンだ、
ここまでパターンで来たのなら、案外そのパターンで逃げられるかも知れない。
竜一はそう思い、必死に念じた。
普段の竜一なら、こんなばかばかしい事を思いつくことさえないはずだったが、
ここまで異常な状況に置かれたせいか、彼自身の思考パターンも微妙に歪んでしまったようだ。
自分の自由を奪う械を頭の中に思い浮かべ、それを、頭の中でひきちぎろうと努力した。
しかし、いくら頭の中で械をひきちぎろうと、実物は、1ミリの傷も付けることは出来なかった。
当たり前だった。
竜一にそんな力がある訳がない。
だが、竜一は、無駄だと分かっていても暴れない訳にはいかなかった。
ここで諦めたら、あのいけ好かない女の思い通りになってしまうのだ。
冗談では無かった。
あんな女の思い通りになるぐらいなら、いっその事・・・・。
そこまで考えていた時、不意に、竜一の耳に、何かの呟きが聞こえてきた。
リザンが呪文を唱えはじめたのだ!
竜一は、必死になってその呪文を耳に入れないように努力した。
どうせまたおかしな術を使うに決まっている。
竜一を眠らせるつもりか、それとも他の手かは知らないが、彼を無抵抗にするつもりなのは明らかであった。
両手の自由がきかないため、耳をふさぐことは出来ない。竜一は思いっきり暴れて、械を鳴らし、ありったけの大声を上げた。
械の音と、自分自身の大声で呪文を聞かないようにし、械に押さえ付けられた両手足の痛みで正気を保とうとした。
しかし、竜一の必死の努力を嘲笑うように、呪文は徐々に彼の心の中に染みわたってきた。
竜一は少しづつ、抵抗する気を無くしていった。
ついさっきまで竜一の心の中に居坐っていた、リザンに対する憎悪も反抗心も消え去り、抵抗する気力も無くしていた。
どうやら、先程の呪文は、反抗心や憎悪を押さえ相手を無気力にするものらしい。
もう、彼は考えることも億劫になっていた。
(・・・・もうこの儀式から逃げることは出来ないだろうな)
竜一は、朦朧とした頭でそう考えた。
(いいさ、もう、どうとでもするがいい。俺も嫌になった。)
竜一は呆然と考えていた。
(リザンには悪いが、また失敗だろうな、そうしたら俺は・・・・。
もう人間ではなくなる、それだけだ。死ぬだけだ。
そして彼女は、また懲りもせず新しい犠牲者を捜すだろう・・・・)
ふと、竜一の頭にあの居候の姿が浮かんだ。
そして次に、あの得体の知れない少女の姿が現れる。
少女は悲しそうに竜一を見つめている。
『何がそんなに悲しいのだ?』
竜一は心の中で、幻影の彼女を見つめた。
『何故? 何故、私の名前を呼んでくれないの』
『そんなこと言われても、俺は君の名前なんて知らないぞ』
少女は頭を振った。
『いいえ! 貴方は知っているわ!
ただ思い出さないだけ。思い出そうとしないだけ。
お願い、思い出して!
貴方が貴方でいるうちに!!』
悲痛な叫び。
竜一は、心にえぐられるような痛みを感じていた。
しかし、そう言われても知らないものは知らない。
竜一は、泣き続ける彼女をただ見つめるしか無かった。
そのうちに、彼女の姿がミーのそれとだぶってきた。
彼女とミーに、何かあるのか?
リザンは、ミーが使い魔だと言った。
すると、あの少女は、やはりミーのもう一つの姿なのか?
それとも、彼女が、ミーを作った魔道士なのだろうか?
そこまで考えて、竜一の意識は益々朦朧としてきた。
ああ、もうだめだな。竜一はそう思った。体が死ぬ前に、心が死にそうだった。
「やっとおとなしくなったわね。」
リザンが勝ち誇って竜一を見下ろす。
着々と、祭壇では儀式の準備が出来上がっていた。
準備を黙々と進めていたリザンの助手らしき覆面の男(体型で男女の区別くらいは付く)が一人、彼女の傍に寄ってきた。
「導師、本当にこの男が、予言書にある”竜王の継承者”なのでしょうか?
それにしては、非力過ぎます。異質な気配は確かにしますが、魔力と呼べるほどの力ではありませんし・・・」
(そうだよなー、俺もそう思うよ。)
その男の言葉に、竜一自身が頷いていた。
どうして無力な自分が、魔道士達にこんなに執着されるのか。
しかし、リザンの魔力のため、その思いもそれほど長続きはしなかった。もう、どうでもいい、そんな気持ちが竜一の心を支配していた。
だがリザンは、余裕の笑顔をその覆面男に返すと、ゆっくりと言った。
「予言の書にある”継承者”の章を覚えている?」
「はい」
「では、ここで暗唱してみなさい」
男は、その通りに、暗唱し出した。
「その者、偉大なる力を支配する。
その力、神をも凌駕しうるもの。
力ある者、それは三つの形を持って、継承者に従う。
一つは知識。
闇の奥にひそみし偉大なる知識を守る者、光の真理を見通す者、
光と闇の調停者、太陽と月を束ねる夜の女神。
その瞳に太陽と月の力を封じたる、偉大なる神なり。
一つは力。
万物をその足下に従わしめる、大いなる力の持ち主、
黄金の力と翼を持ち、大地の主たる誇り高き戦士、太陽の愛娘。
神々の技をその手に握る者、太陽の力をその身に宿す、無敵の戦士。
一つは命。
全ての生と死を、形あるものの始まりと終焉を見守りし者、
全ての生に慈しみを、全ての死にやすらぎを与える月の化身。
慈悲深き月の光の結晶、見目麗しき命の守護者。
その力を支配することを許される、ただ一人の者、
その者、”竜王の後継者”なり。
その者に求められるは、ただその意志。
なすべき事、望むもの、全てをその手に握る者。
全てはその御心にて、三つの力は全てを成す」
半分ぼやけた竜一の頭に、その声は響き渡った。
ああ、そうか・・・・。
ぼやけた頭で、竜一はふいに理解した。
”継承者”とは、その本人が力を持っていると言うわけではなく、力を持つ何者かに命令出来る立場、つまりその主人であるという事なのだ。
そして、その巨大な力を持つ者、それが三人もいると言うことなのだ。
(すげえなあ、何の取り柄もない俺とは偉い違いじゃねえか、なあ、ミー・・・・)
竜一は、消えかかっている幻想のミーと、不思議な少女の幻に笑いかけた。
竜一は縛り付けられたベットと共に、祭壇の上にある奇怪な邪神像のもとへと運ばれていた。
ベットは、魔力によって持ち上げられているのだろう、揺れも無く浮かび上がると、邪神の足元に作られた玉座の正面までの、20mほどの距離を音も無く滑るように進んだ。
「貴方はこれより、我が神、ディログラーズ様の中で、新たな存在に生まれ変わるのです。我等に力と繁栄をもたらす、ディログラーズ様の化身となるのです。」
リザンは、内面から沸き起こる歓喜に震えながら、それを隠そうともせずに、竜一に説明した。
その言葉は、竜一に言い聞かせているのでは無く、周りの部下たちに宣言していたのかも知れなかった。
竜一は頭を動かして、玉座の上に座っている邪神像を眺めた。
薄暗い上に、意識も朦朧としていたため良く判らなかったが、この邪神像は、かなり奇怪な形をしていた。
全体的な形は、サバトの雄山羊に似ている。
額に星を書いた、顔が山羊で、体が人間の裸身体というあれである。
だが、この像は更に、右に山犬の顔、左に鬼の顔を付け、六本の腕を持っており、手には槍や剣等の様々な武具を持っていた。
雄山羊に、阿修羅王に、鬼という、そこらじゅうの神話に出てくる邪神の特徴をごちゃまぜにしたような、そんな姿をしていた。
ただ、鬼の顔は良いとしても、山犬が何を意味しているかはわからなかったが。
それに名前も聞いたことが無い。おそらくは、彼等が勝手に作り出した邪神なのであろう。
まあ、今の世界に伝わる神話も、大昔の人間が好き放題に勝手に作った物が、生き残っただけなのだから、彼等が新しい邪神を作ったところで、別に、可笑しいことでは無いが・・・・・・。
「最後に何か聞くことはある?」
リザンは、悠然と竜一に尋ねる。
今更、竜一がどうしようも無いことを知っている。これは、彼女の余裕ある最後通告であった。
「この中に入った後、貴方は、私達のためにだけ生きる存在になる。私たちの言うことには何一つ逆らうことも、いえ、疑問を持つことも無く従う御神体となる。
今だけよ、私に質問出来るのは。」
「それじゃ・・・・、お言葉に甘えて、二、三質問させて貰おうか・・・・」
竜一は力無く呟いた。
しかし、その呟きを聞いて、彼女は驚愕の色を顔に浮かべた。
「呆れたものね・・・・。
私の術で心を縛られながら、まだそんなことを言う気力があるとは・・・・。
良いわ、その気力に敬意を表して答えて上げるわ。何を聞きたいの?」
「まず、ミーだ。あいつをどうするつもりだ?」
「どうするかは、まだ決めてないけどね。
まあ、それほど力はないようだし、離しても実害は無いと思うけど・・・・」
「そうか・・・・、それじゃせめて、儀式とやらが終わったら、あいつを自由にしやってくれないかな」
「いいわ、儀式が終わったら、あんな使い魔の一匹や二匹、気にする価値もない。
でもどうして、そんなに気を回すの?
あの猫だって、元々、貴方を狙った魔道士のスパイなのでしょう?」
「俺にはそうは思えないんだ・・・・。
それに、俺はあいつを気に入っていたんでね・・・・」
ふうん、とリザンは竜一を見ながら頷いた。
「それと、この像があんたらの神なんだろう?
それにしては、名前も聞いたことないし、この姿も初めて見た。これはあんたらが作った物か?」
「違うわ、これを作ったのは我々の始祖、大魔道士にして偉大なる予言者、カルツァー・ロイラン様よ。
カルツァー様によれば、この邪神ディログラーズ様は多重世界、総ての次元の闇を支配する、真の闇の王、魔王の中の魔王、邪神の中の邪神、偉大なる存在だとおっしゃっていたわ」
「ふーん・・・・、異世界の邪神ねえ・・・・。
それじゃ、最後に聞くけど、俺、これからどうなるんだ?」
「貴方はこれから、この玉座からディログラーズ様の体内に入って、洗礼を受けるのよ。
この像は、異世界の混沌の海につながっていて、そこから、ディログラーズ様の神気が送られてくるわ。
それを浴びて、貴方は、ディログラーズ様の御心と一体になるのよ」
「なんだ・・・・洗脳か・・・・・・」
竜一の呟きに、彼女は、みるみる不機嫌な顔になり、彼に罵声を浴びせた。
「洗脳ではない!
神と一体になるのよ!!その素晴らしい体験を、下衆な洗脳等と一緒にしないで!」
似たような物だろうと思ったが、口に出して言えば、耳元でまた喚かれることになる。竜一は質問の方向をかえた。
「俺以外の人間はどうなった?」
「普通の人間に、神との一体化など不可能。
ディログラーズ様の神気に体が耐え切れなかった者は、肉片一つ残さず消し飛び、精神が耐え切れなかった者は、発狂して、そのまま死んだわ」
「それで、二百人全員を殺したのか」
「二百人全員が、耐えられなかっただけのことよ」
彼女は、全く感情を見せずに言い切った。
「俺で二百一人目か。」
竜一はそう呟いたが、リザンは、それに答えなかった。
「さて、そろそろ時間ね。話はこれで終わり。また後で会いましょう」
その先を彼女は言わなかった、しかし竜一は、彼女が口に出さなかった心の呟きが聞こえたような気がした。
次に会う時は、貴方は既に貴方ではないけどね・・・・・・。
と。