[ 三妖神物語 第一話 女神降臨 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第五章 女神降臨
ベットは、竜一を乗せたまま、再び動き出した。静かに、滑らかに、玉座の正面にある穴へと。
その穴は、正に、闇その物だった。
暗く、そしてどこまでも深く、竜一の命も心も飲み込んで、総てを無に帰す闇、あの中に入ったら、彼も死体になるのだろうか・・・・・・。
(例え、無事に生き延びたとしても、あの女たちの体の良い奴隷になるんじゃ死んだも同じだなあ・・・・)
竜一はそう感じた。すると、彼の心を新しい感情が支配した。
それは、恐怖。
少し前までは、リザンたちに、憎悪と、嫌悪感をもっていた。
魔力で心を縛られてからは、無気力と無力感が、竜一の心を飲み乾した。
そして今、魔力で無気力になっていた彼の心を、恐怖が叩き起こそうとしていた。
しかし、もう遅い。
一体、今の自分に何が出来る?
この械を外すことが出来ない以上、竜一に逃げる術はなかった。
竜一に出来ることは、今、一つしか無かった。
彼の友人や家族に、心で詫びること。
こんな馬鹿な死に方をしようとしている自分を許してくれと、謝ることだけであった。
死ぬ前の人間は、自分の一生の思い出を、一瞬のうちに見るという。
そして彼は、自分の思い出の総て、記憶の総てを思い出していた。
そして心の中で、父に、母に、妹に、そして悪友たちに謝り続けた。
最後に、竜一の眼の前に、ミーと、あの少女の幻想が現れた。
「ごめんな、ミー。俺もうお前の面倒見れなくなっちまった。」
ミーは悲しそうに”ミュウー”と鳴いた。
「すまんな、名前も判らないお嬢さん。
せっかく助けてくれるって言ってくれたけど・・・・、結局、思い出せなかったよ、君の名前」
彼女は、じっと竜一を見つめる。
彼女は、まだ彼のことを諦めていないようだ。
「御免、そんな目で見られてもやっぱりわからないんだ。御免、でも・・・・」
竜一はそのとき、自分でも気付かずに、何気なく一言呟いていた。
「もう一度、お前の真実の姿が見たかったよ。ミューズ・・・・
我が愛しき友よ。」
その瞬間!
ドゴオオオオン!
竜一の耳に爆音が轟き渡った。
そして、邪神の祭壇の下に集まっていた奴等は、突然の事態の急変に、まるで対応できずに右応左応するばかり。
罵声と、悲鳴。
怒声と、叱咤の声が入り乱れている。
竜一自身、一体何が起こったのかわからず、しばらくぼーっとしていたが、はっと我に帰って、周りを見た。
爆音の主は、竜一を今にも飲み込もうとしていた邪神像その物だった。
あの異様な邪神像が、玉座も含めて、跡形も無くなっていたのである!
完全に。
それと同時に、竜一は、頭が妙にすっきりしていることに気付いた。
どうやら、彼の心を縛っていた魔法が解けたらしい。
(後は、体を縛っている械さえ外れたら、言うことはないんだがな)
竜一がそう思った時。
ピシン!
澄んだ音と共に、両手両足を硬いベットに縛り付けていた械が弾け飛び、空中で粉々に砕け散った。
あっけに取られている竜一の耳に、美しい、澄んだ音色の声が静かに流れ込んできた。
「やっと思い出してくれたわね。マスター」
竜一は、慌てて声のした方を振り向いた。そこには、美しい女性が立っていた。
年齢は18〜20と言うところか、腰まで伸びた漆黒のつややかな髪、銀糸と金糸で上品な刺繍のされた黒いマントに黒いドレス。
体をゆったりと包むドレスで隠されているはずだが、彼女の豊かな胸は、怪しくも魅惑的な脹らとなり彼の目を誘惑する。
ゆったりとしたドレスでありながら、それでも隠し様のない見事なプロポーション、そしてそのスタイルに負けない、美しい顔立ち。
前身黒ずくめだが、陰気さを微塵も感じさせない。いや、それどころか、神々しさと威厳さえ感じさせる、美しい、この上もなく美しい女性。
だが、竜一を驚かせたのは、その美貌でもなく、その気配でもない。
彼女の顔には、彼を驚かせるにたる特徴があった。
額には、見事な細工の銀と赤い宝石の、そして胸に同じく精巧な銀と青い宝石で飾られたアクセサリー、右の瞳は金色、左の瞳はかすかに青みがかった銀・・・・。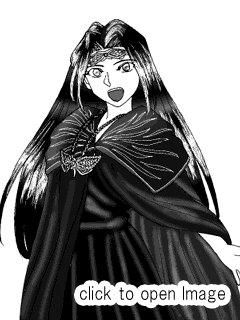
そう、彼女は、竜一がバイトのレストランであったあの少女と同じ瞳とアクセサリーをしていたのだ。
しかし、竜一は何となくそのことを当たり前のように感じていた。
竜一は、彼女の名前を呟いた。
あの時は、何かの偶然であったかも知れない。ただの弾みだったのかも知れない。
だが、その一言が彼の心の奥、記憶の底に封じられていた、あるものを呼び起こしたのだ。
「どうしたの?」
彼女は、心配そうに竜一を見た。
「ああ、余りに長い間お前たちに会っていなかったからね。
まだ記憶が完全じゃないんだ。それにしても、随分と遅かったじゃないか?ミューズ」
竜一は、ミューズに笑って言葉を続けた。
「猫の姿で私に近付いたり、子供の格好で現れたり・・・・随分とまどろっこしい真似をしたなあ。
お前らしくもない。」
「ご免ね。でも訳があるのよ・・・・。」
そこまでミューズが言いかけた時、後ろから、甲高いヒステリックな声が誰何した。
「この神聖な儀式を汚すとは! 一体何者!!」
「詳しい話はまた後で」
ミューズは竜一に微笑み返すと、ゆっくりと振り返った。
そこには、リザンが狼狽しきった表情で二人を睨んでいる。
先程までの自信と力に裏打ちされた、悠然とした態度はどこへやら、見苦しいほどの慌てぶりであった。
この儀式を邪魔されたのが、それほどにショックだったのか?
それとも、邪神像を破壊されたのが原因だろうか?
とにかく、先程までの彼女とは、とても同一人物とは思えなかった。
「神聖な儀式とは言ってくれるわね。
私のマスターをこんな醜悪な下等邪神に支配させようなどという愚考が、そううまくゆくわけがないでしょうに」
狼狽するリザンに、威厳に満ちた声と態度でミューズは対した。
「貴様、一体何者だ!
一体どこから現れた。我が結界をそうたやすく破れる訳がない」
「ほう、随分と大きく出たわね。
そなたの結界等、子猫にさえ破れるほどの御粗末な代物でしょう。
この私に破れぬとでも?」
あくまでも優雅に、ミューズは詰め寄る女を見下した。
勿論、子猫とは他でもない、ミューズ自身のことだが、勿論リザンがそのことに気付くはずもなかった。
「おのれ!」
そう一声吠えると、リザンは何やら呪文を唱え出した。
残念ながら、過去の記憶をほとんど思い出していない竜一には、何が何やらわからなかったが、ミューズは薄い笑みをその美しい顔に浮かべただけであった。
それが嘲笑であることは明白である。
リザンも、それに気付いた。
凄まじい、悪鬼もかくやという形相でミューズを睨み返し、一心に呪文を唱える。
「マスター、私から少し離れていてください」
リザンを見ながらミューズが竜一に忠告する。
「おいおい・・・・・・私を見捨てるのか?
おまえの側がこの世で一番安全なのに」
冗談混じりにそう言う竜一、ミューズの側がどんな所よりも安全なのは、彼が一番良く知っている。
相手がどれほどの魔力を持っているのかは、今の竜一にはわからないが、ミューズの防御を破れるとは思えない。
「マスター、大丈夫ですよ。ちゃんと防御結界は張っておきます。
それに、私と一緒にいたら、あの女と私の戦いを見物できませんよ」
その言葉に竜一は思わず苦笑した。
なるほど、わざわざ竜一を自分から離すのは彼を観客にしたいためなのだ。
「まあ、そこまで言うなら、しかし大丈夫か?ミューズ」
これはミューズ自身と竜一にかけられる結界の両方の事をさしていた。
それに対してのミューズの答えは簡潔を極めていた。
「大丈夫です!」
竜一の問いに、ミューズは自信満々に答える。
「それでは、雷神ミューズ様の御手並み拝見といきましょう」
竜一は、ミューズの忠告にしたがって、ミューズから5mほど離れた。
竜一が離れるのを見届けると、リザンはさらに早口で呪文の詠唱を続けた。
そして、リザンの術が完成した!
「滅びよ! 魔風烈!!」
”力ある言葉”がリザンの口から出ると同時に、彼女の周りに蓄えられていた力が、一気に収束し、大気に物理的な破壊力を与えた。
力は凄じい暴風となって、ミューズに向かって突っ込む!
それは確かにミューズを飲み込んだように見えた。
圧倒的な破壊力を持つ風は、崩れ落ちた邪神像の残骸を砂粒のように巻き上た。
その残骸には、竜一の身長の3倍はある巨大な岩の固まりも随分あった。
それらが、巨大な砲弾のように、風と共にミューズに向かって飛んでくる!
ミューズを中心に嵐は荒れ狂い、岩と岩が激突して粉々に砕け散る。
「そうか、さっきの呪文は嵐を起こす術だったのか」
その様子を見て竜一は、ポンと手を打ち納得顔で肯く。
端から見ているとマヌケ以外の何者でもない。だが、この程度でどうにかなるようなミューズではない。そのことを知っている竜一にとっては、リザンの魔法がどんなものなのか、のんびり見物する余裕がある。
竜一がそんなアホなことに感心している間にも、リザンが起した嵐は、凄じい勢いでミューズを襲っている。
流石に魔法の風らしく、風はミューズを集中的に狙っており、5メートル程度しか離れていないというのに、竜一の方には小石一粒飛んでこず、そよ風さえも吹かない。
竜一は感心しながらも、その様子を見ていた。
リザンは、薄く笑みを浮かべていた。
彼女は、ミューズを倒したことを確信していた。
あれほどの強烈な風をまともに受ければ、如何に結界をはったところで、防ぎ切れはしない。
更に、岩と岩に挟まれ、体中の骨が砕けている。
少なくともリザンはそう信じていた。
だが、次の瞬間、彼女の笑みは凍り付き、その顔に浮かんだのは驚愕であった。
その視線の先には、ミューズがかすり傷どころか、髪の毛一本乱す事なく悠然と立っていたのである。
その顔には、先ほどと全く変わらず嘲笑があるだけだった。
「ば、馬鹿な・・・・、そんなはずがあるものか!」
リザンはうめき声を絞り出した。
「あれほどの術に耐えきるなど・・・・。
い、一体どんな結界をはったのだ・・・・。
私には見えなかった・・・・」
リザンの狼狽に、ミューズは意地の悪い笑みを浮かべてこう言った。
「哀れな、一体何を基準にしているの?あなたは。
あのような児戯が、この私に通用するとでも思っていたの?」
「馬鹿な!
いくら結界があったとて、あの技をくらって無傷で済むはずがあるか!」
自らの力に絶対の自信を持っていた彼女にとって、ミューズが無傷であるという事実は受け入れがたいものであった。必死になってその現実を否定しようと、まるで誰かに言い訳をするように言葉を続けた。しかし・・・・
「現に私がこうして居るのにですか?」
それが現実である。どんなに否定しようと目の前の現実を打ち砕くことなど出来はしない。
したたかに、彼女のプライドを踏みにじりながら、ミューズは続けた。
「あまり自分を基準に考えないことね、上には上が居るのだから」
それはミューズの常套手段だ。
相手のプライドを踏みにじり、冷静さを奪って自分のペースに引き込む。
勿論そんな安っぽい手に引っかからない者達もいるし、ミューズにとっても、上手く行けば儲けもの程度のものだ。まあ軽いジャブと言うところだろうか。
「ほざくなあ!」
一声吠えたリザンは、呪文を唱えようとした。だが、彼女は一瞬躊躇し、そしてその眼を見開いた。
「ま、まさか・・・・おまえは」
リザンは気がついたのだ、自分が相手にしている存在がなんなのか、それが何者なのか。
太陽の輝きを封じたかのごとき黄金の瞳、慈愛深き月の欠片のごとき淡く青みがかった銀の瞳。
その漆黒の髪は、まさに太陽と月を抱く夜そのものではないか!
リザンはあわてて呪文を唱え出した。
先程とは、少し違う呪文のようである。動作も少し異なっていた。
別の呪文を唱えていることは明白だが、それがどんな術なのかは、竜一にはさっぱりわからない。
「無駄なことを・・・・」
嘲笑を浮かべつつ、そう言いかけたミューズは、不意に表情を変えちらりと竜一に視線を向けた。
竜一は、その呪文がなんなのかさっぱりわからず、ただぼーっとしているだけである。
「なるほど・・・・、そういう事ですか・・・・」
竜一の表情を盗み見て、ミューズは苦笑した。
ミューズの笑みをどう理解したのかはわからないが、その瞬間にリザンの術が完成した。
「心操縛鎖!」
リザンは、竜一の顔を見つめて、”力ある言葉”を叫んだ。
今度は何もおこらなかった。少なくとも、物理的には。
彼女は、ミューズに視線を向けて、勝ち誇った笑みを浮かべた。
「ふふ、確かにお前の力は素晴らしい。正面から力ずくで攻めては、如何に私でもそれほど勝算は大きくはあるまい」
その戯言を、ミューズは笑って受け流した。
「あらあら、まだ力の差を完全に把握していないのねえ。
あなた程度の貧弱な”奇術師”が百億人束になろうとも、勝ち目等欠けらも無いのに」
リザンは一瞬、不快げに顔を歪めたが、直ぐに表情を変えて言い捨てる。
「せいぜいほざくがいい!すぐにその鼻をへし折ってやる!!」
そして、竜一にその鋭い眼光を向けると、命令口調で言い放った。
「さあ!”竜王の継承者”よ、その女に、”夜の女神”に命じよ。私に跪(ひざまず)けと!!」
彼女は、竜一とミューズやりとりやミューズの力量から、そして何よりもその外見から、彼女が竜一に仕える”力”の一人であることに気付いたのだ。
それなら、竜一の言うことにミューズは服従する。
彼を支配して、ミューズとの戦いにけりを付けるつもりだった。
たしかに着眼点は良かったのだ。だが、まだ彼女はミューズを甘く見すぎていた。
「と、彼女は申しておりますが、いかが致します?」
ミューズは、竜一に悪戯っぽい笑顔を向けて、口調をわざわざ変えて問いかけた。
その中には、明らかにリザンへの嘲笑が込められている。
竜一も、それに答えて、苦笑しながら肩をすくめた。
「お前はそうしたいか?ミューズ」
「まさか。私が膝を屈する相手は、この世にもあの世にもただ一人、マスターだけよ」
竜一は頷き、リザンに笑顔を向けた。
「と、言う訳だ。貴方のご期待に答えられず申し訳ないが、まあ諦めてくれ」
彼女は、驚愕のあまり目をみひらいて、口を動かす事すらままならないように、そこに立ち尽くしていた。
リザンが、呻き声とも、泣き言ともつかない言葉を絞り出したのは、しばらくしてからである。
「馬、馬鹿な・・・・、何故お前に我が術が効かぬ?
その女ならまだしも、何故お前に・・・・」
彼女は全く信じられなかったらしい。
まあ無理もないだろう。
ミューズはともかく、竜一は、魔道に関してはまったくの素人である。術を防ぐ所か、それがどんな術かもわからないのだ。
そんな彼に術を破る方法などある訳がなかった。
だからこそ彼女は彼に、術を掛けようとしたのだ。
先程の”心操縛鎖”という術は読んで字のごとく、相手の心を支配し、コントロールする洗脳の術である。ただし、持続時間が短くもってせいぜい一日、それゆえ、長時間人を支配するのは向かないものだ。
彼女は竜一を洗脳し、間接的にミューズを支配しようとしたのだった。
だが、すでに竜一にはミューズの作った結界が働いていた。そのために、彼は無事にすんだという訳である。
もちろん、そのことは竜一も知っている。
未だにほとんどの記憶を取り戻していないとはいえ、ミューズがどういう能力を持っているのかぐらいは思い出していた。というよりミューズの力に関する記憶を、僅かばかり思い出したと言うべきだろう。
「おのれ・・・・、もはやこれまで!
貴様ら生かしては返さぬ!この祭壇、いや、この建物毎葬り去ってくれる!!
覚悟しろ!!」
背中に呪いの炎を背負い、瞳に憎悪と狂気の炎を燃え立たせて、リザンは二人を見据えた。
再び朗々と歌うように呪文を詠唱する彼女、それを聞いて驚いたのは、彼女を後ろから見守っていた彼女の手下たちであった。
「お、お辞め下さい導師!この神殿を破壊するおつもりですか!」
「ど、どうかお気を確かに、お辞め下さい!」
竜一はその言葉を聞くと失笑した。
何を今更、彼らはリザンの言葉をちゃんと聞いていなかったのだろうか、彼女はさっき、はっきりと言ったではないか。
『この建物毎葬り去ってくれる!』と。
今までは、竜一をどうにか利用することを最優先にしていた。
だからこそ、ミューズだけを狙い、竜一には危害を加えようとはしなかった。物理的・肉体的には。
しかし、ここに至って、竜一を利用することはもはや不可能と悟ったのだろう。
竜一を他の者の手に投げ与えるよりは、彼に自由を与えるよりは、ここで決着を付けた方が良いと判断したらしい。
この神殿とやらがどれ程の規模なのか竜一は知らないが、本当にこの建物を破壊することが出来るのだろうか?
彼の心の疑問に、ミューズは苦笑しつつ答えた。
ミューズは、竜一の安全を守る範囲で、彼の心の動きを読み取ることが出来る。
というより以前、それを許したのだ。
「あの呪文が、この世界でどう呼ばれているのかは知らないけど、そこに存在する物体を空間ごと破壊するタイプの術のようね。
彼女の力を考えると、直径数百キロは無に帰るかな?」
涼しげな顔で、恐ろしいことをさらりとミューズは言う。
その手の呪文は空間ごとその存在を解消するために、物理的にどんなに頑強な存在でも完全に消し去ることができるのだ。と
「特殊セラミックの核シェルターだろうが、ダイヤモンドで固めた要塞だろうが、綺麗に消し去るわよ。」
ミューズの冗談混じりの補足説明に、竜一はげんなりした表情で問いかけた。
「で、そこまで無茶苦茶な術を使って、術者本人は無事にすむのか?」
「勿論よ。魔術の中で術者自身をも危険にさらす物はそうはないわ」
「中心部だけ安全ってわけか、台風みたいだな。」
竜一は舌打ちした。
リザンはどうやら、仲間諸共、彼らを葬り去るつもりらしい。
何人かは、リザンを止めようと必死になっている。そして残りの者はこの建物から脱出しようとやっきになって走りだした。
「あいつら逃げ切れるかね?」
竜一はミューズに尋ねた。別に彼らに同情している訳ではない。できればここで始末しておきたいとも思った。
彼らの口から自分たちの事が漏れることを恐れたのだ。
もしも漏れたら、自分たちの生活が平穏なものからかけ離れてしまうことは確実だったのだ。
「彼等の魔力じゃ、彼女の呪力結界の干渉を振り切って術を使うことはまずムリね。
術なしで、あの術が完成する前に安全圏に逃げることは不可能だし。
ま、このままなら絶対に助からないわ」
ミューズは説明した。
呪力結界とは、術を使う時に発生する力場である。
本来、術者をその術そのものの影響から守るために生まれる。
それは、強い威力を持つ術ほど強い力場を作り、その力場は、物理的にも魔力的にも、その周りに干渉する。
例えば、相手の魔力をそいだり、術を無効にする。あるいは、相手の動きを封じたり、物理的な攻撃を跳ね返す。というように。
「そして、あの術はかなり強い呪力結界を作るわ。
まあ、威力を考えれば当然だけど。あの連中の中には、そんなに強力な魔力を持つものはいないわね。
彼女が術をつかえば、全滅よ」
「そうなると、あいつは結局助かるのか。問題が残りそうだな。」
リザンが生き残れば、またしつこく竜一達を追い掛け回すのは目に見えている。
どうにかして彼女を始末しなければなるまい。
女を手にかけるのは竜一の趣味ではないが、あの女は、既に二百人の命を奪ったのだ、同情してやる必要はないはずである。
竜一はそう思ったが、肝心なことに気が付いた
「ミューズ、あの術は空間ごと全ての存在を無に帰すと言ったな。それじゃ、この当たりに存在している精霊達はどうなる?」
そこまで言って、さらに気が付いた。この術の破壊規模は、ゆうにメガトン級の水爆に匹敵する。
いや、”無”を生みだし、物理法則そのものを破壊するとなれば、その破壊力はギガトン級の核爆弾にも勝るかもしれない。
そんな術をここで使わせれば、精霊のみならず、物理的な地球環境にも莫大な影響を与えるに決まっている。
「ミューズ!」
竜一の意図を、ミューズは正確に把握していた。
「心配ないわ、私に任せて」
竜一は、頷いた。
「任せる。すきにしろ」
そこにあるのは、絶対の信頼。疑問も懸念もない。その信頼を受けて、ミューズはリザンをその美しい瞳で見据えた。そして、何事かを口の中で呟く。
ミューズが唱え終わると同時に、リザンが吠えた。
「爆呪砕!」
必死に彼女を止めていた覆面たちは、悲鳴を上げた。
「おやめ下さい!」
「導師様!」
だが、そんな悲鳴も、”力ある言葉”にしたがって出現した巨大なエネルギーのうねりと、その圧力によって歪んだ空間の軋む音に飲み込まれる。
リザンの放った力は、彼女の部下の命を生け贄として要求し、圧倒的な破壊力を持って荒れ狂う。
力は空間をさらに歪め、物理法則を崩壊させる。その歪みは付近の物質を飲み込んで、粉々に砕き、無へと還元してゆく。
人間たちの悲鳴は、きしんだ空間が上げる、より大きな悲鳴にかき消され、悲鳴を上げた本人もまた陽炎のように揺らいで消えていく。
全てを無に帰す力は、術者であるリザンを唯一の例外として、全てを滅ぼす。
あの忌まわしい、高慢な女もろともに・・・・・・
完全な勝利を確信していたリザンだった。
この術は、彼女の全ての魔力を代償として要求する。
しかしその威力は、現在人類が行使し得るものの中で最大最強のモノである。
この術に比べれば、科学の粋を極めた核兵器やレーザー兵器でさえおもちゃに等しいモノなのだ。この術にさらされて、その存在を許されるモノなどあり得ない。
はずであった・・・・・・
だが、リザンはあり得ない光景を目撃してしまった。
そこには何一つ変わらない世界が存在していた。
リザンは確かに”力ある言葉”を放った。あの時巨大な力が生まれたはずであった。
しかし、目の前には、あの見たくもない高慢な女とその側に立つ男、さらには、彼女の部下の覆面達が右往左往する様や、破壊された邪神の残骸までもが、全く変わらずに存在していた。
「何の冗談なの・・・・これは・・・・・・」
リザンの呟きは罵声でも、怒りでもなく疑問だった。いや疑問でさえもなかったのだろう、それは放心した彼女の溜息だったのかもしれない。
だが、その呟きが彼女の心を急激に現実に引き戻した。
「バカな! あり得ない! こんな事が!!」
それはリザンにはあり得ない、信じられない事だった。だが、彼女の真実は現実の前に打ち砕かれた。
彼女の最強の術は、全くあっけなくミューズの力の前に屈したのである。
ミューズはその力のごく一部を使って、リザンの魔力に干渉し、その力の解放を打ち消してしまったのである。
「なぜ!私の最強の、いいえ!人間の最強の術なのに!!
何故おまえに通じないの!!」
リザンは完全にヒステリーに陥っていた。彼女はもはや暗黒の世界を支配する最強の魔術組織の長ではなかった。
全ての力を失った、あらゆる手段を封じられた非力な女でしかなかった。
だが、リザン自身の言葉は偽りではない。彼女の魔力は確かに人類の中で最強の部類にあった。
闇の結社であり邪神を奉じながら、独善的なキリスト教、バチカンからの攻撃や圧力を受けずにすんでいたのは、その巨大な力故であった。
力のない魔術結社は、ことごとくバチカンの”聖騎士団”によって抹殺されていった。
生き残ったのは、リザン率いる”ミザリー”を含めごく僅かである。
なにしろ、バチカンはキリスト教社会の全てを支配する巨大な存在であり、ヨーロッパ各国やアメリカなどキリスト教が力を持つ国の事実上の支配者なのだ。
各国の政府でさえも、自国に対して極端に不利益なモノでもない限りバチカンの決定には逆らえなかった。
世界の裏を支配するバチカン、その組織と政治力と人智を越えた力に、純粋に”力”で拮抗しうる存在でもない限り、彼らの手から逃れる術はない。
そして、それらの力を打ち破るだけのモノが彼女達にはあったのだ。
「残念ね。確かにあなたの力はこの世界の人間としては大したモノだけど、それだけの事よ」
むしろ優しいとさえ言える口調でミューズはリザンに答えた。
そう、それが全ての答えだった。
人間として最強の力を持とうと、”雷神”と賞されるミューズにとっては虫けらのごとき力なのである。
”格”いや”次元”そのものが違いすぎていたのだ。あまりにも・・・・
「さて、そろそろあなたにお仕置きをしなくてはね。
私のマスターに手を出すと、どう言うことになるのか、見せしめになってもらわなきゃ」
にっこりと微笑むミューズ。
しかし、眼は笑ってはいなかった。
リザンがどれほどむごい思いをすることになるのか、竜一は祈らずにはられなかった。
「ひい!」
ひきつったリザンが、恐怖の悲鳴を上げて逃げ出す。全ての魔力を失った彼女にできることは、自分の足で逃げることだけだった。しかし、そんなことで、ミューズから逃げ切れるはずがない。
「さようなら、お嬢さん」
そしてミューズは呪文を唱え、その力を解放した。
リザンの姿が空気に溶けるように消えたのだ。
「消えた?」
竜一の呟きにミューズは頭を振った。
「いいえ、良く見てください」
ミューズが指さすその先に、緑色の小さな物体があった。よく目を凝らしてみると、それは小さな生き物だった。
「蛙?」
竜一は思わず呟いた。
そう、それは緑色のヒキガエルだった。それだけなら別に驚くこともなかったのだが。
「なに! 一体どうなったの? 何がおこったの」
狼狽したリザンの声、そのうろたえた声を出しながら、おろおろしているのは・・・・
あの緑色のヒキガエルだった。
「・・・・蛙に変えたのか・・・・」
竜一はしばし、呆然としていた。
はっきり言って、悪趣味の極みである。しかも、醜い蛙が妖艶な女性の声を出す様は、醜悪の一言であった。
「あの女には見せしめになってもらうわ。
たとえこの世界最強の魔術師といえど、私たちに手を出すとどういう運命をたどるのか。
他の連中に思い知らせてやらなければね」

確かにこれは脅しとして申し分ないことだろう。
ただ蛙にされたと言うだけなら、人は信じないかもしれないし、たとえ信じたところで、蛙そのものになっても楽に生きていけると思うかもしれない。しかし、姿は蛙で心が人間のままだと言うなら、これは死に勝る屈辱であり、最悪の拷問である。
人と同じ心と知識を持ちながら、飢えを凌ぐために虫を食い、人間の娯楽を楽しむこともできず、ただ、生きるだけの姿。
人の言葉を話せば、化け物扱いされて石を投げられるか、研究材料として実験体にされあげくに解剖される事にもなるだろう。
少なくとも、世界の闇を支配していたエリート魔道士としての誇りはズタズタ、それだけでも、彼女にとっては死以上の屈辱であるに違いない。
そして、うろたえる覆面達にミューズは朗々とした声で宣言した。
「命を惜しむならば、そして、人としての幸せを望むのなら、他の”奇術師”どもに伝えるといいわ。私達に手を出すものが、どのような末路をたどるのかを。生きながらの地獄を味わうことになると、あのような姿になって生き恥をさらすことになると言うことを」
その指先には、未だに自分の姿を知ることのできない哀れな蛙が、悲しい声を上げていた。
「なんなの! 一体何が起こったの!」
(しかし・・・・これじゃ、おとぎ話の悪い魔女そのものだな・・・・)
竜一は、ミューズの後ろ姿を見ながら、苦笑した。
苦笑するしかなかった。