[ 半熟妖精記 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
第五章 決着
「なっ……!!」
「そんな……」
ダークエルフ達の驚愕に気付かぬように戦士は頷く。
「ああ……だが、まだまだ修行が足り無いな……
姉貴なら、その程度のなまくらなど髪の毛一本で切り捨てられただろうが……
今の俺ではこれが精一杯か……」
刃こぼれした手の中の剣を見つめ呟くように答える。それが己の未熟さへの憤りであることは明らかである。
「貴様の姉……貴様の姉の名は何という!!」
レザイアは信じられなかった。信じたくなかった。だが、もしもこの男の姉が彼の知っている存在ならば、この男の人間離れした能力も納得が出来る。いや、納得せざるを得ない。あの存在が力を貸した相手ならば、むしろ、この異常な能力は有って当然のものである。全てのつじつまが合うのだ。
「姉貴の名前? それを聞いてどうする?」
戦士の疑問に、レザイアはなおも吠える。
「貴様の姉がもしも我々の知る者ならば、全ての謎が解明するのだ!!
さあ! 答えろ」
必死に己を鼓舞して言葉を荒げる。しかし、そのレザイアの言葉の端々に怯えが含まれていた。
「……"メイル"だ。メイル姉貴。それがどうかしたのか」
「……武帝……王……」
「邪神殺し!!」
「ひ……ひいぃぃい……」
その名を聞いてダークエルフは全員恐怖の表情にひきつった。有る程度予想をしていたレザイアでさえ恐怖にがくがくと膝が震え、タムなど完全に腰を抜かしている。
武帝王、
その絶大な力で竜族と共に邪神の天敵と呼ばれる存在。
神ではないが、そのあまりの強さ故、誰ともなしに"闘神"あるいは、"武帝"と呼ばれる
滅びを与えし"雷神"、慈悲深き"薬神"と共に神に有らざる身でありながら、神と尊称されし者達。"神に有らざる神"。
彼女達はまさに邪神の天敵。邪神を奉ずるダークエルフにとっては最も憎むべき相手であり、最も恐るべき敵であった。
だが、この世界を滅ぼす邪神の天敵であり、この世界の守護者でありながら、竜族や他の神魔と違い彼女達の名は人間達の間では殆ど知られていなかった。
実は、彼女達はかつて人間を生み出した神、人間の創造神ヤフェイと敵対したことがある。そして、絶大な力でヤフェイを叩き潰し、この世界のあり方――人間と他種族との関わり――を決定づける原因となったのだが、そんなことが知られればヤフェイ神の名は文字通り地に落ちることとなる。そのため、ヤフェイは必死にその事実を隠蔽し、一般の人々から彼女達の存在を隠すことを選んだのだ。
勿論、彼女達"神に有らざる神"が黙ってそれを受け入れた訳ではない。
ヤフェイのその弱みを握り、人間達がこれ以上この世界を荒らさぬよう、他の存在と共存させることをヤフェイに黙認させる取引材料としたのである。ヤフェイにしてみれば屈辱以外の何物でもなかったが、彼女達の圧倒的な力の前にそれを承諾せざるを得なかった。もしも首を横に振れば、今度は人間達の目の前で完膚無きまでに叩き潰されることは火を見るよりも明らかであったのだ。
そして、彼女達の名と存在は人間達には伏せられた。彼女達の名が人間達の間で広まることはヤフェイにとって死に勝る屈辱だったのである。
その見返りとして彼女達"神に有らざる神"達は、自分の主人の自立と人間界での生活の保証。そして、この世界における人間達の行動原則を"人間による支配"から、"他の命達との共存"へと変更させる事を条件とし、それをヤフェイに飲ませたのであった。
その後、自然神を崇拝する宗教がいくつも生まれたが、ヤフェイとの取引により彼女達は人間界では無名の存在となり、未だに、彼女達を神と崇める人間は存在しなかった。
実は、ヤフェイと戦った当時、"神に有らざる神"は"恐怖の雷神"と"邪神殺しの闘神"の二名だけであった。その後、最後の一人である"慈悲深き薬神"が現れ彼女達と行動を共にするようになり、彼女も"神に有らざる神"として崇拝されることとなった。
そのため、彼女達の名を知る者は人間界では今の所ただ一人しか居なかった。だが、その辺りの事情は人間以外の存在にはあまりにも有名すぎるほどに有名な話であり、当然の事ながら人間以外の存在にとって彼女達は既に、神と同列に扱われ信仰されるほどの存在だったのである。
それは、ダークエルフ達にとっても変わらないことだった。ただし、ダークエルフの場合は崇拝の対象ではなく、自分達の神に敵対する存在という扱いであったが。
そして、"剛破斬"は武帝王メイルが好んで使う技の一つである。その技を伝授された人間が居るなど信じられないことではあるが、もはや信じるほか無い。いや、その技を与えるために武帝王が彼を鍛えたと仮定すれば、彼の人間離れした、怪物じみた能力の謎が一気に氷解するのだ。それにしても、これが"竜翼の剣聖"の常識外れの強さの秘密だったとは!!
「"
「複雑な家庭の事情と言うやつさ」
レザイアの呻きに戦士は平然と答えた。
「す……すると、先ほどの炎は……
セリジェの呟きにも戦士は律儀に答える。
「いや、アレはミューズ姉貴の部下だ。俺のお目付役でね」
「な!
タムの言葉は完全に悲鳴となっていた。それにしても"邪神殺し"のみならず、"恐怖の雷帝"まで身内に持つとはなんと非常識な男か! だが、それを聞けば、先ほどの意味不明の彼の発言に納得がいく。確かに"闘神"メイルや"雷神"ミューズならば"念"で相手を吹き飛ばす程度の芸当など出来て当然だろう。しかし、それを人間に要求するのはどう考えても非常識ではある。
(武帝王様の申し子が人間界に居るというのは、噂で聞いていましたが……
まさか、彼のことだったなんて)
「そんなに凄い存在なの? 武帝王って」
(ええ、勿論です)
フィレンは少女の疑問に答えながら、戦士を見つめていた。
「ど……どうします……レザイア様」
「ここは逃げた方が……」
セリジェとタムは怯えた視線でレザイアを見る。レザイア自身、この場から逃げ出したい衝動に駆られているが、逃げるわけには行かなかった。
ダークエルフ界屈指の魔剣を与えられたことを考えても上官達がどれほど今回の任務を重要と考えているか、どれだけ自分に期待しているか分かろうと言うものである。何より、ここでこの男の手に彼女を渡すわけには行かなかったのだ、断じて。
何しろ、あの少女は大妖術士ベフェル様の落とし子である。その能力は未知数だが、力の覚醒していない今でさえ恐ろしいほどの切れ者であり、放置しておくには危険な存在だ。それが、よりにもよって邪神の天敵である"
ちらりと自分の左手に握られている魔剣の刀身を見る。傷ついていたその刃には既にその傷跡さえ見えない。ダークエルフが誇る最強の魔剣には自己修復能力までもが備わっていた。
そして、相手の剣に目を走らせれば、相手の剣には相変わらず傷が残っている。間違いなく唯の剣である。あの剣には再生能力の類は付加されていないらしい。
勝てる!!
レザイアは確信した。
確かに"剛破斬"の威力はすさまじい。唯の剣をダークエルフ界最強の魔剣と互角の神剣に変える力を持っているのだから。だが、いかに"剛破斬"と言えども、傷の付いた剣でこの魔剣と互角に渡り合えるとは思えない。例え傷のない場所で上手くさばいたとしても、何度も刃を交えれば剣全体に傷が出来るだろうし、激しい打ち合いに傷ついた刀身がいつまでも耐えれるはずもない。
後は、彼の魔力や"お目付役"を上手く封じれば勝つこともそれほど難しいことではない。レザイアには本気になれば彼に劣らぬ早さと技が有るのだから。
自信はあった、だが、隊長として部下の安全を確保する義務がレザイアにはある。彼は自分の部下達に命じる。
「お前達は下がれ、戦いに巻き込まれてはならん」
「し、しかし……」
不安げな部下達にレザイアは笑って見せた。
「案ずるな。
確かに腕は奴の方が上だろう。だが、武器の能力はこちらの方が遥かに上だ」
ダークエルフ語でそう言いながら自分の剣をさりげなく部下達に見せる。彼等の不安を取り除いてやるために。そして、相手に悟られぬように上手く刃の部分を戦士の死角になるように傾ける。
「おお! 傷が!!」
「流石は、我らの最強魔剣!!」
彼等は感嘆の声を上げた。勿論、ダークエルフ語で囁くように。それだけの自制心は持っていた。
彼等もまた、レザイアと同じ思いを持った。確かに無傷となった魔剣と傷ついた剣とでは、勝敗の行方は分かろうというものだ。技と早さは殆ど互角なのだから。ただ、不安は相手に魔力と何より"雷帝"の部下が付いているという事だ、だが、それさえ何とか出来ればこの戦い、勝つのは難しくはないかも知れない。
部下に刀身をさりげなく見せた後、レザイアは何気ないそぶりで剣を鞘にしまう。そして、再び抜刀術の構えをとった。
彼にとって抜刀術の速さが唯一、目の前の敵と互する技だ。そして、鞘に隠すことによって傷の事を相手に悟らせぬ事も可能となる。まさに一石二鳥の構えだった。
「……お前に戦士としての誇りがあるなら、剣の腕で勝敗を決めようではないか」
レザイアは切り出した。
勿論、魔剣が無傷となったことなどおくびにも出さず。この辺り戦士の誇りなどと言ってはいるが流石にダークエルフらしく、なかなか立派な卑怯ぶりである。
「私と貴様の運と実力、どちらが上か。もしも私が負けたら大人しく去ろう」
「……俺がそれに応じず、魔力を使ったら?」
「ダークエルフ全てがお前の敵になるだろう。寝ている時も、食事の時も、貴様に隙があれば、いつでも狙われることになる。」
「……お前と正々堂々戦っても、勝てば同じ様な気もするが……」
「どうする? 嫌だというなら、今直ぐに仲間に連絡するぞ」
彼の問いを無視してレザイアは畳み掛けた。こういう場合相手に考える時間を与えないことが作戦を成功させる鍵となる。レザイアはそう考えていた。
このまま、一気に片を付けても良かったのだ。戦士の力量を未だにダークエルフ達は過小評価していたのだから。だが、彼の懐にしまわれていた短剣が小さく震える。"彼女"も戦いを望んでいたのだ。
「いいだろう、受けよう」
戦士はそう言うと無造作に剣を鞘に収めた。
「何のつもりだ?」
いぶかしむレザイアに彼は余裕を見せた。
「俺はこれを使わせてもらう」
そういって、懐から短剣を取り出し、鞘から引き抜く。
「なに?」
それはあまりにも小振りな剣だった。
短剣と言っても盗賊などが使う物よりさらに短く、武器と言うにはあまりに頼りない。護身用に使うにしても短すぎる。短剣と言うより殆ど果物ナイフに毛が生えた程度の物で、あえて言えば子供が訓練に使うような頼りない代物である。
レザイアは驚いた。あんな頼りない短剣よりも刃こぼれした剣の方が余程ましではないか。
あんな短すぎる剣では満足な戦いなど出来るわけがない。相手の懐に飛び込んでから使うというなら別だが、初めから短剣で長剣を向かえうつなど無謀としか言いようがない。
第一、あんな短い刀身では受けることさえ満足に出来るとは思えない。何しろ、大人の手の中にすっぽりと収まってしまう程度の長さしかなく、十分な厚さのある皮鎧でも防げそうな代物なのだ。
「なめているのか?」
憤慨したレザイアに、戦士はぎこちなく口の端を僅かに上げた。それが、彼にとって会心の笑みの表現であったことに一体誰が気がついただろう?
「心配無用。メイル姉貴がプレゼントしてくれた短剣だ。そこらにある神剣や魔剣なんぞより遥かに頼りになる」
その自信にあふれた言葉に驚いて、改めてレザイアは剣を見つめる、そして、レザイアは知った。戦士の言葉が真実であることを。
その刀身を見てレザイアは言い知れぬ恐怖に震えた。確かに戦士の言うとおり、なまはんかな剣ではない。その輝きだけでこちらの戦意さえ削ぎ落としてしまいそうな力を感じる。
「……まさか、"
震えながら問いかけるレザイアの顔にはひきつった笑いが浮かんでいた。彼は今更ながら思い出したのだ。"
「良く分かったな、その通りだ。
俺の7才の誕生祝いにお守り代わりに作ってくれた物だ」
「な!」
戦士の頷きに、レザイアは完全に凍り付いた。
闘神メイルが、自分の身内の誕生日を祝うために作った剣ならば半端な気持ちで作った代物ではあり得ない。恐らく余程の想いを込め丁寧に作ったのであろう。
唯でさえ彼女の作った武具は神や魔王に珍重されるほどの名品なのだ。それが、誕生祝いのための贈り物となれば、その性能は非常識極まりない代物に違いない。
あの短剣に比べれば、今自分が持っている"滅びの魔剣"さえ、なまくらに等しいかも知れない。
「……くっ」
もはや、先ほどの余裕も何も完全に吹き飛んでしまっていた。形は短剣だが、果たして見た目通りですむものか。
下手をすれば剣を振り下ろしたとたん、不可視の刃がいきなり間合いの外から襲いかかってくる。等ということさえあり得る。
「卑……卑怯な!! こちらの剣は先ほどの打ち合いで刃こぼれを起こしているのだぞ!
そんな傷物の剣を相手に"
「……よく言う。とっくに傷など無くなっているのだろう?
確か"滅びの魔剣"には再生能力があると聞いたことがある」
レザイアの非難に戦士は悠然と答える。
「ちぃ!」
自分の手の内を全て読まれていたことにレザイアは小さく舌打ちた。
それにしても、"滅びの魔剣"の威力は人間界にも広く知れ渡っているが、再生能力についてはダークエルフでさえ極ごく一部の者にしか知られていないはずだった。そんな極秘情報が何故、彼の耳に届いているのか。一瞬怪訝に思ったが、メイルならばそのくらいのことはお見通しかも知れない。
あらゆる武器に精通している"闘神"ならば……
抜刀術の構えをしたままで、レザイアは部下に向かって叫ぶ。
「セリジェ、タム! お前達は一足先に戻って居ろ!!
奴のことを仲間に報告するのだ!!」
最後の一言をダークエルフ語で言い放ち、レザイアの姿はかき消えた。セリジェとタムはその言葉を聞くと直ぐにその場から逃げ出す。高速飛行の術を使って。
二人を逃がせば後々やっかいなことになる。だが、自分に攻撃を仕掛けているレザイアを無視するわけには行かなかった。他の何者に見えなくとも、彼の鋭い目は正確にレザイアの動きをつかんでいたのだ。
戦士は心の中で"お目付役"に頼み込む。
(朱雀、あの連中を頼む!)
(はい)
直ぐに答えが返ってきた。それを確認する暇もなく、戦士は短剣で向かって来るまがまがしい輝きの刃を受けとめる。
それはレザイアの必死の気合いを込めた一撃必殺の居合いであった。
魔剣の力と、己の技量の全てを賭けた最強の技だった。
滅びの魔剣自身が怪しい輝きを放つ。
全ての存在を無に帰す"虚無の欠片"。その力を解放した今の魔剣は、半端な聖剣や神剣など一瞬にして塵と化す力を持つ。まさしく"滅び"そのものだった。
そして、その力を解放した魔剣には居合いと"加速"によって目にも留まらぬ"早さ"、すなわち、破壊的なまでの加速力という"運動エネルギー"までもが付加されている。まさに必殺の技であった。
これで倒せねば二度目はない。捨て身とも言えるまさしく一撃必殺の技。その次はなかった。しかし、悲しいかな彼――レザイア――の必死の思いと決死の覚悟は正しく報われなかった。
シュキュイィィン!
滑るように、なめらかに。
涼やかな音を響かせて、戦士が握っていたその短剣の刃。大人の手にすっぽりと収まる程の短い刃は、まるでリンゴの皮をむくかのように全く抵抗を感じることなく空間を切り裂いた。
だが、勿論、そこは唯の空間ではない。短剣がなめらかに切り裂いたその軌跡上にはダークエルフの誇る魔剣と、ダークエルフ屈指の勇者の身体が存在していた。
レザイアの誇りと技、そして最強の魔剣。
その全てをあざ笑うかのように、いや、そもそも、そんな物など初めから存在しなかったかのように、美しく、何気なく、あっさりと彼女、"闘神"メイルの生み出せし小さな
滅びの欠片、虚無の剣。
今までただの一度も敗北を知らなかった最強の魔剣。それが全く相手にならなかったのである。そして、相手の子供の遊びに使われそうな小さな、玩具のような剣のその刃に傷つけることはおろか、その輝きを曇らせることさえ出来なかったのだ。
「そ……そん……な……」
恐怖?
驚愕?
いや、それは疑問だった。
レザイアは己の身に起こったことを信じることが出来なかった。
だが、彼の疑問に答えたのは冷酷な現実。彼の全てを嘲笑するかのように、彼の身体は魔剣共々見事に上下に両断され虚しく大地に転がっていた。
「……やり過ぎではないのか?」
あまりにも相手をあざ笑うような、まさに身も蓋もない問答無用な勝ち方に、戦士は手の中にいる彼女に語りかけた。
彼自身としては、二・三合打ち合って戦士としての礼儀を果たしてから打ち倒すつもりだったのだ。だが、彼女はそんな彼の考えを無視してあっさりと決着を付けてしまった。その余りと言えば余りなやり方に多少の不満があったのである。
しかし、その手の中にある短剣には答える気はないようだ。沈黙したまま何の反応も返さなかった。
「……冷たい奴……」
苦笑と憐憫。
戦士の殆ど動かぬ感情に、僅かにそれらの微粒子がわき上がったとき、彼の耳元に美しい声が囁いた。
「ダークエルフ二人の始末。終わりました」
戦士は静かに頷く。彼女の仕事は正確無比、疑う余地など無い。
「終わったよ。お嬢さん」
彼の声に、おっかなびっくりでハーフ・ダークエルフの少女は彼の元へと駆け寄ってきた。
「……凄い剣ね」
少女は彼の手にある短剣と、鞘にしまわれた剣を交互に見ながらそう言った。
「まあな」
短剣を懐にしまい、長剣の方を再び鞘から引き抜いて、剣に付いた傷を見つめる。
「俺が未熟なせいでこんな傷を付けてしまって……すまん」
静かに剣に謝る戦士。そして一人呟いた。
「さて、どうしようか……メイル姉貴に鍛えなおしてもらうのが一番確実だな」
彼が呟いたとたん!!
キュイイィィィ!!
彼の懐にしまわれた短剣が抗議の声を上げた。
"闘神"メイルに鍛え直されれば、確かにこんな小さな傷など一瞬で無くなるだろう。だが、メイルに鍛えられれば、この剣は冗談でなく強力無比な神剣となってしまう。何しろ、彼がこれほど愛用する剣だ。魔剣や聖剣ほどの力はないが、それでも余程腕のいい鍛冶士の手による業物らしく、なかなか"いい仕事"をしている物なのだ。メイルが鍛え直せばかなりの剛剣になることは疑いない。
そんなことにでもなれば、自分の立場が無くなってしまう。それを"彼女"は危惧したのだ。
キイィィィィイイン
「うるさぁいぃ!!」
あまりにしつこい彼女の抗議に、少女が両耳を押さえて悲鳴を上げる。なにしろ、普通の人間でも頭痛がするような甲高い音である。人間を遥かに越える聴力を持つハーフ・ダークエルフの彼女にしてみれば、まさに拷問である。
これにはさすがの彼も閉口したらしい。諦めたように呟いた。
「分かったよ。今回は我慢するよ」
その言葉でやっと納得したのか、"彼女"は直ぐに声を止めた。
「……なんか……凄く我侭な剣みたいね……」
脂汗を流しながらひきつった顔で尋ねる少女に戦士は微かに頷いた。
「切れ味は文句無しなんだが……な」
実の所、彼が旅に出るとき"メイル"は新しい剣を作って与えるつもりだった。
確かに切れ味については十分にあるが、所詮、"彼女"は彼が幼い時に与えたお守りであり、実戦向けで無いことはメイル自身が誰よりも良く知っていた。
旅に出れば望む望まないに関わらず戦いに関わることになる。そのために実戦向けの長剣を与えてやるつもりだったのだが、彼女が強行に反対し、長い間付き合ってきた手前彼も彼女に逆らえず、町の武器屋で適当に見繕うことになったのである。
そして、たまたま立ち寄った武器屋の倉庫の中で埃を被っていた剣を見つけた。それが、今彼が愛用している剣だった。
その剣はまさに彼と出会うために生まれたと言っても過言ではなかった。"闘神"メイルが旅に出る前彼に言っていた「人との出会いと同じように道具との出会いにも縁がある。その縁を大切にすることだ」と言う言葉を証明するような出会いだったのである。
そして、その剣の魂、"精霊"もまた彼を愛し始めた事を"彼女"は知っていた。ここでメイルに鍛え直され"神剣"にでもなられては、わざわざメイルが剣を与えるのを邪魔した甲斐がないというものである。我侭と言われようがなんと言われようが、どんなことをしても妨害してやろうと固く誓っていた"彼女"であった。
傷ついた剣を見つめ戦士は再び呟く。
「しかたがない、ファフェニールで鍛冶屋を探すか」
当面の目的地であるファフェニールは目と鼻の先であった。とりあえず、そこに逗留して腕のいい鍛冶屋を探すのが最も妥当であろう。
「……あ……あの……さ……」
言いにくそうに少女は何かを言葉にしようと四苦八苦していた。
「え……と……その……あのね……え……と……」
なかなか踏ん切りが付かず、しどろもどろになっている彼女を戦士は黙って見つめていた。
彼は感情が殆ど欠落しているためか、焦ったり苛立ったりすることはほとんど無い。このまま日が暮れるまで待つことも彼にとっては苦痛ではなかった。
何より、少女がよほど重大なことを決意しようとしていることを理解している彼にとっては、それを聞くために消費される時間はそれほど重要なことではなかったのだ。
「……そ……その……ご……ご免なさい!!」
意を決して少女は頭を下げた。
「あたし……あなたの財布を……その……」
「ああ、知っていたよ」
「……え?」
「俺があの時眠っていたと思うのかい?」
「………」
男の言葉に少女は絶句していた。
「どうして? なんで、黙ってたの!? 一体どういうつもりよ!!」
少女は叫んでいた。はっきり言ってこれは屈辱だった。まるで、子供の悪戯を見て見ぬ振りをする大人のような自分を見下した彼の態度は、彼女のプライドをずたずたに引き裂いていた。
「別に困るような事もないからね。俺は金が無くても稼げばいい。
だが、君の場合はそうもいかないだろう? 稼げるときに稼ぐのは当然のことだ」
「………あ………あんたって……何考えているの?」
少女は呆然と呟いた。感情がほとんど無いと言うことには気が付いていたが、ここまで、ずれまくった考え方の持ち主とはまるで気が付かなかった。金に苦労してきた彼女にしてみれば彼の考えは全く理解不能だった。
「……姉貴の話では俺は欲望が希薄なんだそうだ。俺自身はそんな自覚はないがね。
ただ、そのせいか、金品に対して執着心って言うのかな? 無くしても"惜しい"って気にならないんだ」
呆然と自分を見つめる少女に言葉を続ける。
「まあ、金が無くても生きる方法はいくらでも学んだし、金を稼ぐ方法も姉貴達から徹底的に仕込まれているから、人間の居る所ならいくらでも稼げる自信はある」
その自信にあふれた言葉が少女の激した感情を宥めた。
「稼ぐって言ったて……戦争が少ないのにどうやって稼ぐの?」
怒りが収まると今度は好奇心が急激に頭をもたげた。
「別に俺の特技は戦いだけではない。
ミューズ姉貴からは魔法と色々な学問を叩き込まれた、そこらの町で家庭教師や呪い士をする程度の知識はある。
メイル姉貴からは道具の作り方なんかも学んだから、町工場の職人にだってなれる。
シリス姉貴からは色々な医学知識を仕込まれたから、開業医だって出来る。
つまり、人間の居る町なら、どんな商売でもできると言うわけさ」
少女は絶句していた。魔法や医学に精通している人材というのはどんな町でも不足している。その両方が出来るというのなら、まさに引く手あまたである。
「で……でも、初めてあったときはそんなこと全然言わなかったじゃない!」
「別に言う必要もなかったからな」
少女の疑問に彼はあっさりと頷いた。
「じゃあ……どうして今頃になって言うのよ?」
「君が俺と一緒に来ても、俺の懐は痛まないと言うことを説明しただけだよ」
「!!!」
「俺の財布のことを言い出したのは……そう言うことなんだろう?」
「……え……と……その……
今更こんなこと言うのは……その……都合がいいって……思われるかも……知れないけど」
彼に言われて少女は意を決したのだろう、言葉を絞り出すように話し出す。
「家も無くなっちゃったし……ダークエルフにも狙われることになっちゃったし……あたし一人じゃ……もうやっていけないから……」
今までの彼の行動から、彼が女に手を出すようなタイプの男でないと彼女は思っていた。根拠はその無骨な言動である。見るからに頭の固そうな武人タイプ。こういう男は大抵、女に対してそういう行動に出にくいものなのである。
勿論、確証ではないが、いざとなったら上手くごまかせばいい。彼女の計算高い頭脳はそう判断していたのだ。それなら、一緒に旅をした方が自分にとって利益が大きい。一緒に行動する事で金の問題も解決するが、何より、その知識を吸収する事が出来れば、それは自分にとって極めて大きな財産となるはずだ。
貞操の危険が多少は有るが、それを差し引いても利益の方が遥かに大きい。それどころか、彼女は知識を教えてもらう見返りなら多少のことは許してもいいとさえ思っていた。
金は使えば無くなってしまうが、知識を得ればそれはそれこそ一生の財産になるのだから。ただ、自分の提案には一つの大きな問題がある。ダークエルフに狙われると言う危険を彼が承諾するかどうか、それが彼女にとっては不安材料では有った。
(私からもお願いします。私だけの力では、この子を守りきる自信がありません。
どうかお願いします)
フィレンも頭を下げる。
「ああ、かまわんさ」
あまりにあっさり言ってのけた男に少女は絶句する。
「……い……いいの? そんなにあっさり決めちゃって……私はダークエルフに狙われているのよ?」
彼女の懸念にも彼は無頓着に答えた。
「ああ、一人旅にも飽きてきたところでね、同行者が欲しいと思っていたところだ。
ダークエルフのことなら心配ない。手を出してきたら返り討ちにしてやるよ」
キュイイィィィ!!
(あら? 私達が同行者では不満ですか?)
彼がそう言うと、いきなり懐から不満の声があがり、かれの耳元で涼やかな女性の
「お前達とじゃ、道中話すこともできないしな。誰も居ないときならともかく、町中でお前達と話をしてたら変質者だと思われる」
精霊や妖魔の類と話せるような力の持ち主は人間にはまだまだ少ない。
町の中で彼女達と話していては問答無用で変態扱いされるのが落ちである。彼としては人間が不審に思わないような話し相手が欲しかったのだ。
(……ハーフ・ダークエルフがまともですか?)
微かに笑いを含んだ彼女の
「変態扱いされるよりはましだ……と思う」
(そうですね、変態ではありませんね。変人になるだけですね)
「……」
さすがの彼もこれには絶句した。その彼に少女は尋ねる。
「さっきから女の人の声が聞こえるけど……ひょっとしてあなたの
「ああ、聞こえていたのか?」
珍しそうに尋ねる彼に少女は頷く。
「なんか、ぼんやりと影のような姿も見えたから……」
「流石に
彼の言葉が終わらぬうちに、彼の傍らに紅蓮の炎が燃え上がる。それが消えた瞬間、そこには真紅の髪を肩でそろえた朱色の瞳を持つ美女が立っていた。
「我が名は朱雀。
炎の神に命を与えられ、神に有らざる神、
以後御見知りおきを……お嬢さん」
「あ……いえ……こちらこそ」
優雅にお辞儀した朱雀につられ、彼女も慌てて頭を下げた。
(朱雀様!? そんな、朱雀様が人間の守護を!?)
フィレンが驚きの声を上げる。
「どうしたのよフィレン。そんなに驚くことなの?」
(朱雀様は火の精霊でも最高位の力をもつお方のはず。
それほどの方が守護に付くなんて)
驚いたフィレンに戦士はぶっきらぼうに答える。
「なに、別に俺が気に入られたわけじゃない。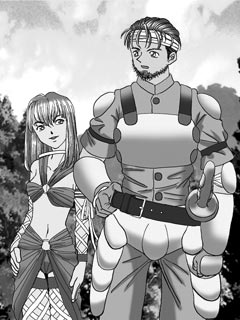
戦士の言葉に朱雀は肩をすくめた。
「酷いですね。これでも誠心誠意お仕えしているつもりなのですけど」
「ふむ、まあ、そう言うことにしておこう」
(ひえええぇぇ)
戦士と朱雀の何気ないやりとりに肝を冷やしたのはフィレンである。
彼等はたわいない会話のつもりなのかも知れないが、最上級精霊と無表情な男の言葉の投げ合いは聞きようによってはとてつもなく物騒だった。
(あ……あのう……少しお聞きしてもよろしいでしょうか?)
戦士と朱雀のやりとりに神経をすり減らしていたフィレンは何とか話題をそらそうと話しかけた。
「なんだ?」
(あなたがあの"竜翼の剣聖"で有ることは分かりました。ですが、私が知る"竜翼の剣聖"とは微妙異なっておいでです。
その辺りの説明を、もし、差し支えなければお聞きしたいのですが……)
「ふむ、君の言いたいことは分かった。共に旅をするなら打ち明けておく必要が有るな。」
戦士は一つ頷くと言葉を続ける。
「今のこの姿は本当の姿ではないんだ」
「え?」
彼がそう言うと同時に風と光が彼の周りを踊り……そこに現れたのは……。
「……こ……こど……も?」
(……やはり……)
少女の目は完全に点になり、フィレンはやっと納得したといいたげに頷いた。
そこに現れたのは少女よりさらに一回り小さい、まさに子供であった。あまりのことに少女は呆然となったが、直ぐに気を取り直して問いつめる。
「あ……あんた一体何歳なのよ!!」
「14だ」
「な!! あたしより5才も下なの!!」
子供らしい声で先ほどと変わらない大人びた口調は恐ろしく違和感がある。先ほどまでの大人の姿をしていた彼ならば問題ないのだが、この姿でこの口調はあまりに不自然である。
第一、14才と言えば大きな町なら義務教育で必ず学校に通っていなければならない年齢のはずであり、一人旅など言語道断であった。
平均年齢170才のこの世界では30才でやっと一人前とされる。20〜30才で青年(または学生)。10〜20は子供であり10歳以下は幼児と呼ばれている。
14才で一人(?)旅とは厳しい等というレベルではない、殆ど狂気である。
「……な……何考えているのよ……あんたの姉達は……」
(雷帝様や武帝王様を誹謗するのはよした方が……)
囁くようにフィレンが忠告するが、少女はまったく気にとめなかった。
「まあ、そういわんでくれ。
姉貴達が言うには、俺は人の世で学べる知識は全部身につけたんだそうだ。俺にあと必要なのは体験なんだそうだ。」
「………」
少年の言い分に少女は絶句するほか無い。どういう教育を施せば半人前以前の未熟者としか言えない年齢の少年にこの世の知識全てを与えられると言うのか。しかし、彼の自信をみるとあながち嘘とも言い切れない。まあ、それは過信であるかも知れないが、その自信――あるいは過信――を抱かせるほどに知識を与えたのは確かであろう。
「いいな……あたしもそれだけの知識が有れば……」
少なくとも医学や魔法の知識が有れば、犯罪に頼らずに金を稼ぐ事が出来るようになる。知識はそれだけで力となる。彼女は知識がどれほど貴重な物かよく知っていた。
「でも、どうして"変身"なんてしているの?」
「いくら知識や実力があっても子供の姿ではなめられるからね。だから大人の姿をしているのさ。これからも俺は大人として行動する。その方が君のためにもなるはずだからな」
その言葉が終わる前に再び彼の周りで風と光が舞う。それが収まるとそこには少女が見慣れた一人前の戦士が佇んでいた。
「……確認しておきたいんだけど……本当にあなた人間?」
呆れと脅えが半々に混じった声で少女は目の前にいる男に問い掛けた。
彼が使っているのは"変身"である。"幻覚"で騙していたわけではない。戦いを見ていれば分かる。"幻覚"で体格をごまかしていたなら剣の間合いで直ぐにばれる。
人間の肉体は元々変身するようには出来ていない。まして、成長途中の子供にこんな術を使えば肉体に恐ろしい負担を与える。術を使えば数時間で身体中に激痛が起こり身動き一つ出来なくなるはずである。それなのに、彼は平然としている。一体どういう身体の構造をしているのか?
ダークエルフを圧倒する戦闘力といい、あれだけの攻撃魔法を喰らって無傷な身体といい、そして、肉体に異常なまでに負担をかける術を使いながら平然としている事といい、彼を見ているととても人間とは思えなかった。彼女の疑問は極めて当然のことである。
「……自信はないが……そのはずだ……」
(雷帝様や武帝王様に鍛えられたなら、人間離れしても仕方有りませんよ)
少女の問いに男は自分自身に言い聞かせるかのように呟き、フィレンは苦笑しつつ頷く。
「少なくとも俺の姉貴達はそう言っていた。俺の両親は人間だったというし、生まれは人間のはず……だと思う」
彼の微妙な言い回しに少女は聞いてはいけないことを聞いてしまったと後悔した。
「あ……ご免なさい。」
「何故謝る?」
少女の謝罪に男が首を傾げる。
「……だって……"だった"って……。
その……御亡くなりになったのでしょう?」
遠慮がちに言う彼女が言う。
「いや、今でも何処かで生きているはずだ。
ただ、俺が化け物じみた力の持ち主だったことを知って、生後数カ月で捨てたらしい」
「!!!!」
あっさりといいのける男に少女は絶句した。
自分を捨てたと簡単に言う彼も理解しがたい。それとも、感情がないとはこういう物なのだろうかと感心さえした。が、さらに信じられないのは生まれて間もない自分の子供を簡単に捨てる親の精神構造である。
彼女の母親はダークエルフに犯され自分という"鬼子"を生んだ。にもかかわらず、彼女の母は"鬼子"であるはずの自分を愛し育ててくれた。そのために母親は故郷を追い出され、家族から絶縁され身一つで放り出されたのである。そして、たった一人で自分を育て、その無理がたたって不帰の人となった。そんな母親を見て育った彼女は母親の愛を絶対の物だと信じていたのだ。その彼女にしてみれば簡単に子供を捨てる母親など、存在自体信じられない。
「……本当にそんなことがあるのかしら……そんなことの出来る人が居るなんて信じられない」
「人それぞれさ。愛せる者もいればそうでもない者もいる。それだけのことだ」
彼女の素朴な疑問に、男はまるで他人事のように答えた。
(…………)
フィレンは何も言えなかった。
風の精霊として彼女は人間の多くの行動を見聞している。そして、むしろ、少女の母親より、戦士の親のような人間が圧倒的に多いことも知っていた。そして、戦士もそれを十分に承知していた。
彼女の母親が少女を捨てなかったのはダークエルフの呪いか、さもなくば、彼女の母親が特別だったかのどちらかであろう。だが、それを彼女に言う気は戦士にはなかった。彼女にとって母親は神聖な存在となっているに違いないし、それが彼女の心を今まで支えていたのは疑いようがない。それを傷つけるつもりなど、彼には無かった。
「さて……それじゃ行こうかお嬢さん」
戦士は少女にそう呼びかけた。ただ、自分より年下の相手に"お嬢さん"呼ばわりされているにも関わらず、それほど腹は立たなかった。
言葉使いといい落ちついた物腰といい、何より、ダークエルフを難なく倒したその圧倒的な実力といい、彼が自分より遥かに経験も能力も優れている。それを認めているためか、それともその大人の姿が余りにも堂に入っているせいか、全く違和感がなかったのだ。なにより、自分より年下の相手が自分より優れていると考える方が腹が立つ。それを考えれば、今の姿が彼の真実の姿だと思った方が、まだ精神衛生上いいかも知れない。
彼が少女を促して歩き出そうとした時、少女が突然声を上げた。
「あ! ちょっ……一寸待って!! あたし、あなたの名前知らないわ!!」
それを聞いて、戦士はその事実に初めて気が付いたらしく、完全に硬直していた。
ぎこちなく少女の方に向けられた顔には、表現しがたい表情をしていた。おそらくは、驚愕かあるいは苦笑の類の表情を作ろうとして失敗したのだろう。彼は、まだまだ自分の感情を完全に制御することができないのだ。
「確かに……言われてみればその通りだな……」
そうは言ってみたものの、これだけ深い仲になってから改めて自己紹介するのもなかなか間抜けな話ではある。だが、だからといって名乗らないですませる訳には行かない。
(………………)
「………………」
フィレンと朱雀も相手を見て言葉を失った。自分達が紹介しようかとも思ったのだが、今更紹介するのも何かマヌケで言いづらい。
しばらくの間、気まずい沈黙が辺りを支配したが、少女が意を決して顔を上げた。
「いいわ、あたしが先に名乗る。相手の名を尋ねた方が先に名乗るのが礼儀だもの」
そして、一呼吸置いて彼女は口を開いた。
「あたしの名前は………」
彼女の名がその愛らしい唇から流れてくる頃、太陽はゆっくりと地平線へと降り始めていた。