[ 三妖神物語 外伝 裁きし者 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke
その参、甘いお誘い
「う・・・・ううぅ・・・・」
小さなうめき声を上げて慶喜が目を開ける。
自分はいったい何をやっていたのだろうか?
ぼんやりとした頭を何とか清浄にしようと軽く頭を降ってみると、ずきりと鈍い痛みが走った。
その痛んだ場所、頭頂部に手を回してみれば、ばかでかいタンコブが出来ていた。
「い・・・・いってえ・・・・」
さわっただけでずきずき痛むこぶ、その痛みが寝ぼけていた彼の意識を覚醒させる。
「そうか・・・・あの訳のわかんねえ大女に殴り倒されたんだ・・・・
するとここはどこだ?」
殴り倒されて意識を失ったことは思い出したのだが、それなら自分達はあの路地裏でのびていなければならないはずだ。しかし、目の前の光景は汚い路地裏では無かった。
豪華でふかふかのベッド、美しいシャンデリア。一目見ただけで一流の高級品と思われる調度品の数々。
あまりにも高級な品々に廻りを囲まれ、慶喜は居心地の悪さを感じていた。
「ここはいったい・・・・そうだ! 啓介の奴は?」
啓介のことを思いだし、慶喜はベッドからでると側にきちんとたたんであった服を着る。
彼の着替えがちょうど終わった頃、まるで見計らったようにドアをノックする男が聞こえた。
トントン・・・・
その音にぎょっとしてドアを凝視していると、涼やかな優しい声が聞こえた。
「もしもし、入ってもよろしいでしょうか?」
「だ・・・・誰だ!」
思わずそう大声を出した慶喜だったが、この家の人間だろうと考えた。
それが、正しい答えであることを訪問者は証明した。
「私は、この家の娘です。
あなたのお友達が心配していらっしゃいましたので、お迎えにあがったのですが・・・・」
その返答に慶喜は安堵すると同時に、一つの考えがひらめいた。
まだ実物を見ていないので、その行動を行うべきかどうか決めてはいないが、声から察するとおそらく美女に違いない。もしも、そうならば・・・・
果てしなく膨らむ妄想。助けられたことをきれいさっぱり忘れて、恩を仇で返そうと言うのである。
だが、それを慶喜は極めて自分勝手な理由を付けて納得した。
「俺のように逞しく、いい男に抱かれるのは女にとって最高の幸福だ。やはり、助けてくれた相手には礼をするべきだからな、俺の逞しく美しい体で礼をするとしよう」
他人が聞いたら、極めて自分勝手な理屈に腹立たしくなるところだが彼は本気でそう思っているのだから始末に負えない。
慶喜は、別途から立ち上がりドアへと向かって歩き出した。
「ああ、すぐにいく」
丁重とはほど遠い返答をしながらドアを開ける。これではどちらが家の主なのか全く分からない。
すでに、彼はこの家を自分の物にするつもりになっていた。
彼女を抱いて自分達の奴隷という”名誉”を与える、彼女の体とこの家は当然自分達の物になる。それは、彼にとって当たり前のことだった。
問題はドアを開けたときだった。
相手の顔が自分の好みの物でなかったらこの計画もおじゃんである。
ガチャ
ノブを回してドアを開ける、正面に声の主が待っていた。
・・・・一瞬目の前にいる者が、いったい何なのか、慶喜には理解できなかった。
目の前にいる女性。
はたして、それは美女だった。
声から想像していたとおりの、いや想像を遥かに超える絶世の美女だった。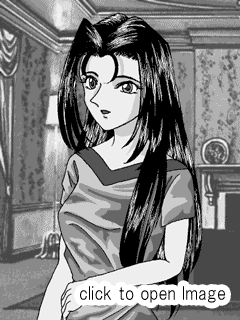
”絶世の美女”という形容詞そのものが安っぽく聞こえるほどの背筋に寒気がするくらいの美女だった。
果たして、これほどまでに美しい存在が”人間”と言えるのだろうか。
女性を玩具か奴隷としか考えないような慶喜でさえ、その余りの美しさに得体の知れない恐怖を感じていた。
この美しすぎる存在は何なのか?ただの人間とは思えない、危険すぎる。
本能はそう告げる。
ここから逃げた方がいい。この美しさは人の持ちうる物ではない。これは魔性の美しさだと。
それは生き物としての生存本能。想像を超えた、自分を越えた存在に対する畏敬の念だった。
だが、もう一つの男としての本能がそれを拒絶した。
こんないい女この先一生お目にかかれない、絶対にものにしてやる。と
これほどの獲物を目の前にして逃げられるか、例え相手が何であろうと俺達ものにしてやる。
両手を握りしめて強く自分に言い聞かせる。
必ず俺のものにしてみせる、例え相手が魔女だろうと、女神だろうと。
そう堅く決意する慶喜だった。
彼女は”冥子”と名乗った。
「冥子、何か縁起の悪そうな名前だな」
慶喜が眉をしかめて言うと、冥子は笑った。
「皆さん、そうおっしゃいますわ。父が言うには、私は生まれ落ちたとき心臓が動いてなかったのだそうです。
お医者様が何とか心臓マッサージで動かして下さって・・・・それで父があの世から帰ってきたからと”冥子”と名付けたと」
他人が聞いたら縁起が悪いと言われるが、自分はこの名前を気に入っている。はにかみながら彼女はそう答えた。
二階の彼が寝ていた部屋から、一階へと降りて応接室に案内される。
そこに一足早く啓介が座って待っていた。
重厚な作りのテーブルの上に缶ビールやカップ酒を積み上げ、相棒の来るのを待っていた。
もっとも、既に封を切られたビール缶がいくつか床に転がっている所を見ると、待ちきれなくて飲んでいたのだろうが、他人の家で遠慮をするということを彼は知らないらしい。
あるいは慶喜のように既にこの家を自分の物にしたつもりなのだろうか?
既にこの家の住人のようなでかい態度の啓介に彼女は怒りもせず注意さえしなかった。彼らの態度を気にしていないのか。それとも、気にならないのか。
多少の疑惑を覚えた慶喜だったが、それもすぐに泡のように消え去った。
これほどいい女を手に入れるのだ、多少の危険は覚悟していた。
お互いの無事を喜び、慶喜と啓介はそのまま酒を飲み交わした。
「全く、あの野郎、今度会ったら叩きのめしてやる」
慶喜が酒の勢いにまかせて吐き捨てる。あの野郎とは言うまでもない、先ほど自分達のお楽しみをじゃました大柄の美女のことだ。
「おいおい、あれは女だったんだから”女郎”だろう?」
啓介が笑いながらそう言うと、慶喜は鼻を鳴らした。
「ふん! あんな男女、野郎で十分だ!」
再び吐き捨てるように言うと、手の中にあった缶ビールを一気にあおる。
「どうやって叩きのめす? 奴は手強いぞ」
そう思ったが啓介は口には出さなかった。もともと、慶喜も別に本気で言っているわけではない、単に景気付けと酒の勢いで乗りで言っているにすぎない。
もしも、この場に彼女がいたら、すぐに土下座して謝るだろう。
彼らは、今まで女性を腕力で従えてきた。純粋に腕力のみを頼みとしてきただけあって彼らはそれなりに腕が立つ。相手の力量を見抜く程度の実力はあった。そして、彼女の力がけた外れであることを、彼らはその身で知ったのだから。
やがて、数十個の缶ビールと、数個のカップ酒を飲み干した二人は、テーブルの向かいでワインをちびちび味わっている美女に視線を向けた。
じっくりと値踏みするように、なめるように彼女を無遠慮に眺める二人、その瞳には既に理性の欠片も見られ無い。
元々それほど自制心の高い人間ではない、おまけに酒が入っているのだ。彼らにはもはや理性も良心も恥も外聞も残っていない(はじめからあったかどうかも疑わしいが・・・・)。ただ、美しい獲物を自分の物にしたいという欲望があるだけだ。
「お嬢さん、この家に家族はいないのか?」
「ええ、両親とも仕事で帰りは遅いんです」
慶喜の質問に警戒心の欠片もないような答えが返ってくる。
「へえ、そおかあ・・・・」
冥子の答えに、満足げに頷いた啓介がちらりと慶喜を見た。慶喜も僅かに頷く。
「なあ、なんで俺達を助けたんだ?」
「偶然通りかかっただけです。苦しそうなうめき声が聞こえたので覗いてみたら、あなた達が倒れていたので家に運ばせたのです」
思えば、このとき気づくべきだったのだ、その不自然さに・・・・
しかし、欲と酒に酔っていた彼らは既に正常な判断力を失っていた。
「いや、助かったよ。
おかげでだいぶ楽になった、ただ、もう少し楽になりたいんだが、手を貸してくれないか?」
「どうすればよろしいのでしょうか?」
慶喜に冥子が答える。
「その・・・・飲み過ぎて少し気分が悪くなってきたんだ、ベッドまで付き添ってほしいんだが・・・・」
その厚かましい見え見えの誘いに、しかし、冥子は疑う素振りも見せずに頷いた。
「分かりました、ごいっしょします」
「俺はもう少し飲んでるぜ」
わざとらしく啓介は慶喜にそう言った。慶喜は静かに頷く。
二人が階段を上っていくのを横目で見送って、啓介は傍らにある8mmビデオカメラに視線を向けた。