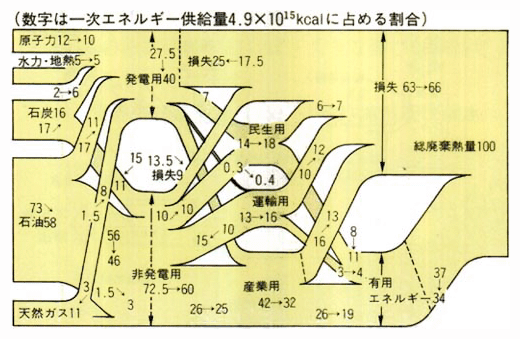|
|
|
日本において電力会社vs.ガス会社の本格的な戦争が始まった。 以前にも述べたが、日本においては、電気事業法・ガス事業法は電気事業者・ガス事業者がほかの業務を行うことを厳しく制限してきたが、99年5月の両事業法の改正によってこの条項(いずれも第12条)が削除された。 この改正は、それ程大きなニュースとならず地味であったが、エネルギー産業の規制改革の文脈においては、パンドラの箱を開けた意味を持ち、事態はもはや後戻りできないものとなった。 さて、電力会社vs.ガス会社という対立項をあえて設定したが、 この戦争は、海外における歴史を観てみると、本来なら自由化後の早い段階で自律的に両者の吸収・合併に繋がっていくものであるが、前近代(プレモダーン)のわが国では、そうはいかない。両者の消耗戦が続き、お互いのダメージが拡がって、時既に遅しという段階にまで来なければ、吸収・合併は叶わない。 結論を先取りして言えば、 エネルギー事業体の枠組みでいえば、この戦争は電力会社の勝利に終わる。電力会社が扱う液化天然ガス(LNG)は、ガス会社のそれよりもはるかに多いため、その気になれば、小さなガス会社へのLNGの卸供給はいくらでも行えるし、資本主義が貫徹するなら、規模で圧倒的に優位な電力会社が買収にどんどん乗り出すはずである。 拙論文で述べたように、分散型エネルギーシステム(燃料電池、マイクロガスエンジン、マイクロガスタービン等による電気と熱の供給)はもはや世界的な大潮流である。 かっては、太陽光発電、風力発電などの自然エネルギーを使った発電が脚光を浴びたが、これらも分散型エネルギーシステムの枠内に囲い込まれてきている。 もはや既存の電力会社の大規模発電、巨大送電線網による送電システムは理論的には、経済性、環境負荷ともに、分散型エネルギーシステムに劣ることは決着がついているため、紆余曲折があろうとも、社会は自律的に分散型エネルギーシステムの社会へのステップを踏みつつあるのである。 参考にヨーロッパでのガスvs電力の状況を報告した記事を、ガスエネルギー新聞から引用する。(ガスエネルギー新聞2002年10月16日号) (引用はじめ) 英国では電力会社が発送配分離され、さらに配電会社は12に分割された。その状況下ではガス会社が電気供給事業に進出することが可能であったが、おおよそ規模で勝る電力会社がガス事業に進出し、拡大成功を収める例の方が多い。(ガスエネルギー新聞2002年10月16日号) 里屋和彦です。 ここで、再度既存の大規模発電システムが、分散型エネルギーシステムに比べて経済性に如何に劣るかを証明するポピュラーな見解を、ガスエネルギー新聞から紹介する。 下図は、1975年度および1992年度(→の左側が1975年度、右側が1992年度を表す)の日本のエネルギーフローである。左側から一次エネルギーが、燃やされて、発電用に使われるエネルギーと、非発電用に使われるエネルギーとに分かれる。発電用、非発電用ともに、民生用、運輸用、産業用にとその用途は分かれる。
この図についての説明を、ガスエネルギー新聞から引用する(ガスエネルギー新聞 2002年10月30日)。 (引用はじめ) もともと発電部門のエネルギー利用率は30%台で、非発電部門の50%台よりかなり低かった。従って、オフィスや家庭の電化などによる電力需要増大に応じて電力化率が急速に上昇すると、発電効率が多少改善されてもカバーできず、全体の効率は低下することとなった。 国内の電力需要は、今後ともOA化や空調の普及などによる増大が見込まれ、電力化率の上昇は避けられない。発電効率は大型化やコンバインドサイクルなどの導入によって最近約40%まで改善されてきたが、大規模発電所の立地は最大需要地である都市部からますます離れていくため、送電ロスと熱利用の困難さによって、それ以上の改善は容易ではない。 たとえ発電効率が50%となっても、郊外の発電所では残りのエネルギー50%は利用できず、熱として環境中に廃棄せざるを得ない。(ガスエネルギー新聞 2002年10月30日) 里屋和彦です。 この意味で、もう一度繰り返すなら、将来のエネルギーシステムにおいては、エネルギー体の観点でいえば、ガスの圧倒的勝利なのであるが、日本における既存の事業体の観点でいえば、巨大な液化天然ガスを持ち、ガス会社のパイプラインを借りることができ、また、旺盛な資本力でガス事業を営む(あるいは買収)ことが可能な電力会社の圧倒的勝利で終わる。 戦国時代に突入したエネルギー業界において、この事態が、近代化への契機になることを期待したいが、気をつけなければならないのは、この混乱の間隙を抜って、国家の生命線を担うエネルギー業界が外資の草刈場と化すことだけは避けねばならない。(了)
2002/11/30(Sat) No.01
|